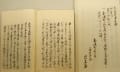江戸時代、庶民だけではなく幕臣や藩士など武士も様々な罪で刑
に処されている。その中には武士だからこそ厳しく罰せられた罪も
あった。
「寛保世説抄録」(全1冊、華族徳川昭武の所蔵を写書、修史館旧
蔵)には、寛保元年(1741)7月6日未明、700石の旗本・関内記が熟
睡中に妾に斬りつけられ重傷を負った事件(その後死亡)の経緯が記さ
れている。

内記は被害者であるにもかかわらず“碑女に疵つけられ、あまつさ
えそのままに座をさらしめ事越度なり“という理由で、改易の処分が
下される。油断して妾に斬りつけられたばかりか、加害者を取り押
さえられなかったのが、旗本としてあるまじきこととされた。


また、同書には寛保2年(1782)8月に江戸と関東各地を襲った豪
雨による洪水の記録他、寛保年間(1741~43)の出来事を書きとめた
雑録も収められている。
(国立公文書館:千代田区北の丸公園3-2)
に処されている。その中には武士だからこそ厳しく罰せられた罪も
あった。
「寛保世説抄録」(全1冊、華族徳川昭武の所蔵を写書、修史館旧
蔵)には、寛保元年(1741)7月6日未明、700石の旗本・関内記が熟
睡中に妾に斬りつけられ重傷を負った事件(その後死亡)の経緯が記さ
れている。

内記は被害者であるにもかかわらず“碑女に疵つけられ、あまつさ
えそのままに座をさらしめ事越度なり“という理由で、改易の処分が
下される。油断して妾に斬りつけられたばかりか、加害者を取り押
さえられなかったのが、旗本としてあるまじきこととされた。


また、同書には寛保2年(1782)8月に江戸と関東各地を襲った豪
雨による洪水の記録他、寛保年間(1741~43)の出来事を書きとめた
雑録も収められている。
(国立公文書館:千代田区北の丸公園3-2)