本日、第5回検討会が開催され、資料が公表されています。
法人設立手続オンライン・ワンストップ化検討会(第5回)
新しい経済政策パッケージ(平成29年12月8日閣議決定)に沿った議論を展開している模様です。
経済対策等 : 経済財政政策 - 内閣府
今回のテーマは「定款認証の合理化」
事務局見解
・面前確認によって不正行為が心理的に抑止される効果について、客観的説明は無い
・定款認証を必須とする理由として、当該効果を挙げるのは不適当ではないか
・代理人による申請の場合/発起人が複数でその一部しか出頭しない場合、発起人は面前確認を経ないため、上記で言及されている現に「客観的な効果」は発生しないのではないか
・原始定款認証を必須とする理由として、真意の確認等の効果を挙げるのは不適当ではないか
・合同会社についても「重大な法的効果」の発生は防止されるべきということを考えると、電子定款の場合は電子署名の添付で真正性の確認が充足されるということではないか
・会社が定款の規律に反する行為等のコンプライアンス違反を、定款認証という設立前の一時の行為で防止できる説明に、合理性があるか
・代理人申請では結局のところ発起人の意思は委任状にある電子署名(電子の場合)に基づいており、これで真正性が認められるのであれば、電子定款に電子署名が付されている場合に真正性が認められない合理性はあるか
・定款の特に電子定款の場合、公証人が保存する情報と、発起人または代理人が請求できる情報を異なるものとして区別する意味があるか。それが改変不可能であることが確保されていれば、内容に質的な違いがあるか
・適法性の確認・適法性が担保されたモデル定款の作成に関する論点については、年明けの検討会において具体例を示しつつ、課題があれば今後解決すべき点を個別具体的に明らかにし、議論を深堀りすることとしたい
・認証で実施される行為の主体を公証人に限定する合理性があるか
・導入の経緯を踏まえても、現在も電子署名や電子定款も想定されていなかった当時の手法で制度を持続する合理性は無いのではないか
・認証を不要化しうる場合・条件を特定できないか
・① 電子署名が添付された電子定款、かつ、② モデル定款を採用している場合は、面前も含め公証人とのやりとりを必須とする合理性が無いのではないか
・①発起人の電子署名が添付された電子定款、かつ、②モデル定款を採用している場合は公証人を経由することなく、登記手続時に提出するワンストップ手続としてはどうか
法人設立手続オンライン・ワンストップ化検討会(第5回)
新しい経済政策パッケージ(平成29年12月8日閣議決定)に沿った議論を展開している模様です。
経済対策等 : 経済財政政策 - 内閣府
今回のテーマは「定款認証の合理化」
事務局見解
・面前確認によって不正行為が心理的に抑止される効果について、客観的説明は無い
・定款認証を必須とする理由として、当該効果を挙げるのは不適当ではないか
・代理人による申請の場合/発起人が複数でその一部しか出頭しない場合、発起人は面前確認を経ないため、上記で言及されている現に「客観的な効果」は発生しないのではないか
・原始定款認証を必須とする理由として、真意の確認等の効果を挙げるのは不適当ではないか
・合同会社についても「重大な法的効果」の発生は防止されるべきということを考えると、電子定款の場合は電子署名の添付で真正性の確認が充足されるということではないか
・会社が定款の規律に反する行為等のコンプライアンス違反を、定款認証という設立前の一時の行為で防止できる説明に、合理性があるか
・代理人申請では結局のところ発起人の意思は委任状にある電子署名(電子の場合)に基づいており、これで真正性が認められるのであれば、電子定款に電子署名が付されている場合に真正性が認められない合理性はあるか
・定款の特に電子定款の場合、公証人が保存する情報と、発起人または代理人が請求できる情報を異なるものとして区別する意味があるか。それが改変不可能であることが確保されていれば、内容に質的な違いがあるか
・適法性の確認・適法性が担保されたモデル定款の作成に関する論点については、年明けの検討会において具体例を示しつつ、課題があれば今後解決すべき点を個別具体的に明らかにし、議論を深堀りすることとしたい
・認証で実施される行為の主体を公証人に限定する合理性があるか
・導入の経緯を踏まえても、現在も電子署名や電子定款も想定されていなかった当時の手法で制度を持続する合理性は無いのではないか
・認証を不要化しうる場合・条件を特定できないか
・① 電子署名が添付された電子定款、かつ、② モデル定款を採用している場合は、面前も含め公証人とのやりとりを必須とする合理性が無いのではないか
・①発起人の電子署名が添付された電子定款、かつ、②モデル定款を採用している場合は公証人を経由することなく、登記手続時に提出するワンストップ手続としてはどうか











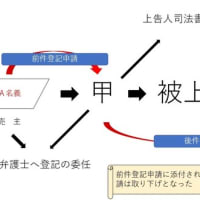
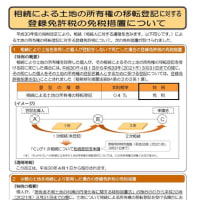
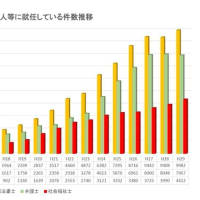
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます