仕事帰りに早稲田松竹にて北野武監督の『首』を観てきた。遅ればせながら、だろうか。普段ほとんど映画を観ないのだが、僕は歴史として戦国時代に興味があり、テレビゲームでも信長の野望はほとんどプレイしてきた。今も「新生」で1546年の毛利元就でプレイしているところでもある。ちょうど『首』の舞台の一つでもある備中高松は、毛利輝元と織田信長の中国方面軍の羽柴秀吉の交戦地帯であり、映画では備中高松城の清水宗治の切腹シーンもあり、ゲームでも今、清水宗治を使っているところでもあった。ゲーム上では、現在尾張の国で織田氏を滅ぼした後、武田氏と対峙している。まあそれはともかくとして、戦国時代のエピソードが好きな僕としては、『首』を映画館で見ておきたいと思っていたが、ロードショー期間には見に行かず、しまったなあと思っていたが、早稲田松竹が上映するということで観に行った。

内容としては、ギャグ要素もあって面白かった。きちんと「時代劇」をしているなとも思った。登場人物の言葉遣いや方言は現代語や共通語が入り混じっているのだが、バランスが悪くないので不自然に感じない。ところどころの要点では歴史的考証やセットにリアリティがありそれが際立つので、歴史性を感じることもできる。最近の大河ドラマはこの部分のバランスが悪い気がするので、北野武に監督となってもらって大河ドラマを作ってほしいな、とも思わないでもなかった。映画の役柄としては、ビートたけしが「羽柴秀吉」の役をしているのだが、観る前はたけしで大丈夫か?と思っていたが、これが案外似合っている。とぼけた顔をしたり、はにかんだ顔を見せたり、身も蓋もないプラグマティックな残酷さも見せるのだが、憎めない、所謂「人たらし」的な側面もうまく出ていた。秀吉はことあるごとに、他の役柄の明智光秀や滝川一益らとは差別化して、「俺は百姓だ」というシーンがあるのだが、秀吉役のたけしの顔が晩年のマルティン・ハイデガーにむちゃくちゃそっくりで、確かにハイデガーも「農夫」とか言っていたなと思って、感慨にふけっていた。やはり「俺は百姓だ」ということの存在論的強度はある。
『首』というタイトルだけあって、「首」が次々と切り落とされるシーンは、爽快でもあったし、基本的人権なんてないのだから、この時代の人間の扱いなどこんなものかもしれないな、とも思った。織田信長の近習には「弥助」と名付けられた、黒人男性が実際にいたわけだが、その存在を啓蒙的な形ではなく、いかんともしがたい人間が引き起こす人種差別の意識として物語要素に盛り込んでおり、その弥助が最終的に信長の「首」を持ち去ってしまうのは、少し考察すべき箇所であると思った。邪魔だから殺し、首を切り、見た目が違うから警戒し、笑い、遠ざけ、支配し、あるいは近づける。ここに合理的な説明ができない人間の恣意的で偶然的な暴力性があるわけだが、そういう暴力性の塊として戦国大名を描きたかったのかもしれない。人を殴ってはいけません、人を不快にしてはいけません、安全第一に、怒らず冷静に、という啓蒙が果たして、そういう人間の恣意的で偶然性としか言えない暴力的側面を説明することができるのか。あるいは、そういう暴力性をコントロールできるのか。暴力の無底性をどのように考えるべきなのか、という問題がここにはある。基本的に僕は暴力性という恣意的で偶然的な存在は、作品という偶然的なものでしか説明できないのではないかと思っている。
本能寺の変が起こり、秀吉は京にとって返すために、備中高松城で毛利の代表者である安国寺恵瓊と和睦の談合をするのだが、安国寺恵瓊が広島弁でしゃべるのは安芸の毛利だからいいとして、恵瓊が『仁義なき戦い』の「広島極道は芋かもしれんが、旅の風下に立ったことは一遍もないんで」という小林旭の台詞のオマージュを大声でぶちまけていた。この和睦の談合に先だって、怪僧恵瓊の存在を心配した浅野忠信扮する「黒田官兵衛」と大森南朋の「羽柴秀長」が、秀吉に「恵瓊は大丈夫ですか?」と問うのだが「そんなこと知るかばかやろう」と返していて、恵瓊の扱いにしばらく声を出さずに笑ってしまった。恵瓊はこの秀吉との和睦の約20年後、関ヶ原の戦いで石田方について、石田三成と小西行長と共に、六条河原で斬首されることとなる。

内容としては、ギャグ要素もあって面白かった。きちんと「時代劇」をしているなとも思った。登場人物の言葉遣いや方言は現代語や共通語が入り混じっているのだが、バランスが悪くないので不自然に感じない。ところどころの要点では歴史的考証やセットにリアリティがありそれが際立つので、歴史性を感じることもできる。最近の大河ドラマはこの部分のバランスが悪い気がするので、北野武に監督となってもらって大河ドラマを作ってほしいな、とも思わないでもなかった。映画の役柄としては、ビートたけしが「羽柴秀吉」の役をしているのだが、観る前はたけしで大丈夫か?と思っていたが、これが案外似合っている。とぼけた顔をしたり、はにかんだ顔を見せたり、身も蓋もないプラグマティックな残酷さも見せるのだが、憎めない、所謂「人たらし」的な側面もうまく出ていた。秀吉はことあるごとに、他の役柄の明智光秀や滝川一益らとは差別化して、「俺は百姓だ」というシーンがあるのだが、秀吉役のたけしの顔が晩年のマルティン・ハイデガーにむちゃくちゃそっくりで、確かにハイデガーも「農夫」とか言っていたなと思って、感慨にふけっていた。やはり「俺は百姓だ」ということの存在論的強度はある。
『首』というタイトルだけあって、「首」が次々と切り落とされるシーンは、爽快でもあったし、基本的人権なんてないのだから、この時代の人間の扱いなどこんなものかもしれないな、とも思った。織田信長の近習には「弥助」と名付けられた、黒人男性が実際にいたわけだが、その存在を啓蒙的な形ではなく、いかんともしがたい人間が引き起こす人種差別の意識として物語要素に盛り込んでおり、その弥助が最終的に信長の「首」を持ち去ってしまうのは、少し考察すべき箇所であると思った。邪魔だから殺し、首を切り、見た目が違うから警戒し、笑い、遠ざけ、支配し、あるいは近づける。ここに合理的な説明ができない人間の恣意的で偶然的な暴力性があるわけだが、そういう暴力性の塊として戦国大名を描きたかったのかもしれない。人を殴ってはいけません、人を不快にしてはいけません、安全第一に、怒らず冷静に、という啓蒙が果たして、そういう人間の恣意的で偶然性としか言えない暴力的側面を説明することができるのか。あるいは、そういう暴力性をコントロールできるのか。暴力の無底性をどのように考えるべきなのか、という問題がここにはある。基本的に僕は暴力性という恣意的で偶然的な存在は、作品という偶然的なものでしか説明できないのではないかと思っている。
本能寺の変が起こり、秀吉は京にとって返すために、備中高松城で毛利の代表者である安国寺恵瓊と和睦の談合をするのだが、安国寺恵瓊が広島弁でしゃべるのは安芸の毛利だからいいとして、恵瓊が『仁義なき戦い』の「広島極道は芋かもしれんが、旅の風下に立ったことは一遍もないんで」という小林旭の台詞のオマージュを大声でぶちまけていた。この和睦の談合に先だって、怪僧恵瓊の存在を心配した浅野忠信扮する「黒田官兵衛」と大森南朋の「羽柴秀長」が、秀吉に「恵瓊は大丈夫ですか?」と問うのだが「そんなこと知るかばかやろう」と返していて、恵瓊の扱いにしばらく声を出さずに笑ってしまった。恵瓊はこの秀吉との和睦の約20年後、関ヶ原の戦いで石田方について、石田三成と小西行長と共に、六条河原で斬首されることとなる。













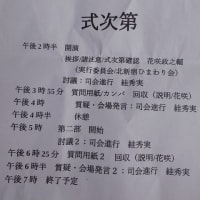






※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます