数日前に「「性別」破壊党」の機関誌『月刊 性別』の創刊号を買った。党首自ら?の手書きの添書が同封されていた。「「性別」破壊党」を知ったのは、このブログでも以前に『情況』の2024年夏号の「特集 トランスジェンダー」の名古屋での討論会について書いたが、その特集の論文の中で、阿部智恵のものが一番「唯物論的」であり、本来左翼雑誌というのは唯物論的であるべきだと僕は思うのだが、この雑誌の特集は阿部論文のような唯物性を受け止められるものであったのか、という疑義を呈した時である。その疑義については繰り返さないので、以前の記事を読んでもらいたい。僕自身は「性別」あるいは「性的差異」は、「精神」と「物」との連関を考える上でのアポリアであると考えている。伝統的に「精神」と「物」は二項対立的に捉えられており、主に西洋形而上学の内側では、「精神」が優位性をもっている。ただ、形而上学もこの「精神」と「物」の矛盾をどのように揚棄するかという問題は思索されていて、近くわかりやすいところでいえば、デカルトやカント、ヘーゲルなどは、僕のような哲学を専門的に知らない読者でも、その内容から理解できる部分も多い。例えばカントの「構想力」は様々なレベルでの解釈が可能であるが、「悟性」と「感性」の矛盾を図式化して連関させる能力だと考えれば、それは「精神」と「物」の間の矛盾を繋げる、何らかの認識論的能力といえるのだろう。ハイデガーはこの図式化を「時間」の様態として捉えていたと思うが、それを「差延」として読み換えれば、デリダも「精神」と「物」の間に、そのような差延を見ていたことになる。つまり、「精神」と「物」は矛盾しているが、それを連関させる何がしかの論理や理論を、これまで哲学者は考えて来たということである。芸術や文学というものは、「精神」と「物」を繋げる「構想力」の産物であると思うので、エクリチュールが「精神」でも「物」でもない、例えば「痕跡」として捉えられるのも、文学や芸術は「精神」と「物」を連関させる何ものかであるということに他ならない。
僕は「性的差異」もそのような「精神」と「物」を繋げるものであり、あるいは「精神」にも「物」にも還元できない何かだ考えている。そういう意味で「性的差異」は思考することそれ自体の条件であり、同時に限界であるとも思っている。このような「性的差異」が「精神」や「物」へと還元されていく時に、現実的な意味での男根中心主義のロゴスが働き始める。デリダは、それを男根ロゴス中心主義というものを、何かの著作で、男根が性的欲望に関わること自体を否定しているのではなく、男根がジェンダー・セクシュアリティの認識論的・存在論的な布置を決定してしまう、そのロゴスの中心性を批判すべきだということを書いていたはずだ。それは当然で、男根もまた、本来は「精神」にも「物」にも還元できないエクリチュールの問題を持っているものだが、それが精神性や肉体性に還元されるとき、男性優位を司るものになる。しかし、男根という差異を排することはできない。何故なら男根をなくせば、その男根を脱構築する論理もまた動かなくなってしまうからだ。だから、脱構築は形而上学を「男」としてなくすものでもなければ、男根をなくすものでもなく、「精神」と「物」の関係を「差延」の関係として考え直す試みといえよう。それこそが「性的差異」を差異として、「精神」や「物」に還元できない〈モノ〉として考えることである。これはカントの「物自体」や精神分析のフェティシズムの問題、それはマルクスの「商品」のフェティシズムにも通じるものである。そういう意味では「性的差異」を思考するフェミニズムは唯物論的なもののはずだ。
阿部は機関誌の記事で、自らが肩幅を狭めるときに切り取った鎖骨を「鎖骨ペンダント(呪物)」として写真でも示している。ヘーゲルは『精神現象学』の中で、「精神」を無理やり弁証法的に例えるならば、「頭蓋骨」だといえるだろう、という書き方をしていたと思う。僕はここを読むたびに奇妙な感覚に襲われる。というのも、ヘーゲルは何かここに言いにくいものを感じている気がするからである。砕けた言い方をすると、「「精神」は「頭蓋骨」として矛盾として現れている、これが矛盾としての弁証法だ!」というような感じで、ヘーゲルはそんなに堂々と言っている気がしない。どちらかというと、「「精神」という目に見えないものを、あえて言えば不承不承だけど「頭蓋骨」というしかないけどねえ……」というような形で僕は捉えている。何かここに言い難いというか、ヘーゲルが認めたくない何かがある気がする。そういう意味で、阿部の「鎖骨ペンダント(呪物)」とはまさしく、「性的差異」そのもののことだろう。ヘーゲルの言葉を借りれば、「性的差異とは鎖骨である」ということになるはずだ。
また時間があれば、改めてエルンスト・ブロッホの著書については書きたいが、僕は最近仲間と読書会でエルンスト・ブロッホ『この時代の遺産』(池田浩士訳、水声社)を読んだ。その著書の中ではブロッホが、1910年代から40年代にかけて、反資本主義の〈地盤=遺産〉をマルクス主義とナチ、そしてスピリチュアリズムと争っている状況下で、いかにマルクスの唯物弁証法を堅持するかということを思索しており、現代というブロッホの言葉でいえば「多孔的」でグズグズの状況を考える上で、大変良い書物だと思った。ブロッホによれば、ナチやファシズム、スピリチュアリズムもまた反資本主義的な〈地盤=遺産〉を相続し、継承していこうとするが、結局はブルジョワに奉仕するようになるということであった。ブロッホは唯物弁証法、それは先の言葉で言い換えるならば、「精神」にも「物」にも還元されない、「精神」と「物」の間の差延的弁証法を考え抜くことで、そのようなファシズムとスピリチュアリズムを批判しようとする。しかし、「精神」と「物」を考えるという意味で、ブロッホもスピリチュアリズムを完全に脱していない。しかし、そのスピリチュアリズムと唯物論をどうやって「モンタージュ」(唯物弁証法と言い換えられるだろう)して反資本主義の〈地盤=遺産〉を創り出していくのか、ということを唯物論的に考えている。ブロッホのいう「ユートピア」はこのような「モンタージュ」、それはマルクス経済学に基礎に置いた弁証法の運動を基礎に置いた世界を作ることと解釈できる。しかし、その〈地盤=遺産〉はファシズムやスピリチュアリズムが簒奪し、結果的にはあれほど反資本主義の見せかけをなしながらも、結局はそれらが裏切り、ブルジョワに奉仕する世界を作っていくのである。
もちろんブロッホは、ファシズムやナチの「情熱」は「本物」であるとし、それを嘘といっているわけではない。ブロッホは本来は反資本主義をマルクス主義が領導するはずが、その反資本主義をめぐる「情熱」を理論的に弁証法化し得ていないという批判をしているのだ。その反資本主義の「情熱」を「俗流マルクス主義」が軽視しながら、ファシズムやスピリチュアリズムに傾倒している奴らもいずれ眼を醒まし、その後は共産党が「情熱」の主導権を握るはずだと考えていたわけだが、そのような「俗流マルクス主義」の期待(観念論)は裏切られ、1933年以降のナチの台頭を招く。ブロッホは「俗流」に対抗して唯物弁証法を堅持しようとし、その弁証法が実は芸術や文学と連関しており、それが「遺産」でもあるとしている。これも「精神」と「物」の差延的弁証法につながるが、「俗流マルクス主義」はそのような弁証法を無視するので、反資本主義の「情熱」を理論化できないのである。そしてその「情熱」はナチやスピリチュアリズムに流れ込んでいく。これは現代においては「リベラル」がこの「情熱」をつかまえることができず、参政党やカルトにその「情熱」を横領されていく過程にも似ている。この「情熱」こそ、本来は「精神」と「物」の差延的弁証法の中で、反資本主義の欲望を現実に定位していかなければならないものであり、前衛党がそれを指導しなければならないはずである。しかし、なんの人気取りか、マルクスや唯物弁証法を前面に押し出さなくなった党は、そういう「情熱」を全く掬えなくなった。結果的にその情熱は観念論に横領される。「リベラル」と呼ばれるイデオロギー集団は、その意味で「情熱」を取り逃がしている。この「情熱」が掬えない状態のことを、僕は「ポリコレ」として批判されているのだと思う。この「情熱」はマルクスならばフェティシズム、精神分析の対象a、カントの物自体のように、観念にはどうしても包摂できない欲望のはずだ。前衛党自体もそういう対象だったはずである。しかし、そういう「情熱」を掬おうとせず、自民党を批判して左派的正しさを主張して、彼らを啓蒙すれば、いずれまた正常な世界がやってくるという「観念論」を信じている限り、ブロッホが経験したナチの台頭と似た状態を招くだろう。
少なくともブロッホは、ナチやスピリチュアリズムの「情熱」を否認せず、反資本主義の「遺産」に関わるものとして真剣にとらえている。では現代の所謂「リベラル」はどうだろうか。「情熱」を掬い取る唯物弁証法を「リベラル」は保持しようとしているだろうか。僕は非常に懐疑的である。現実の問題として自民党を批判したり、不平等や差別を批判すること自体には、僕は全く異論はないし、それを差延的現実の運動でやっている人はいる。しかし、「情熱」を掬い取る理論に関しては、それほど真剣に考えられていないのではないか。いずれ別に書きたいが、パチンコやラーメンなどもそうだ。パチンコに並んでいる人、油とでんぷんのかたまりとしてのラーメンに並んでいる人、彼らの「情熱」をどうやって掬うのか。掬わないといずれ参政党などがわかりやすい形で横領していくのではないだろうか。僕は真剣にマルクスの唯物弁証法をやり直すしかないと思う。
そういう意味で「鎖骨ペンダント」は一つの「情熱」であり、「性的差異」という欲望の形態そのものといえる。現代の科学技術においては生物学的男性は妊娠ができない中で、妊娠を目指すという矛盾的弁証法は、単純な意味でのスピリチュアリズムや観念論では思考することは無理だろう。「精神」と「物」の間にしか「情熱」は存在しないからである。読書会でも言ったのだが、「性的差異」「トランスジェンダー」「女性」の問題を、前衛党は唯物弁証法の柱として徹底すべきだ。ジェンダー・セクシュアリティの話題ばかりしていたから大衆が離れていく、それをテーマにするから選挙に負けるなどという、男根主義者のくだらない戯言など真に受けず、ジェンダー・セクシュアリティを唯物論的に考えることこそ「情熱」を掬い取ることになるという立場に立つべきである。そうしないと「ポリコレ」を越えることはできない。ジェンダー・セクシュアリティ、あるいはケアの問題には、その唯物弁証法と「情熱」の問題が結集している。前衛党がここに関わらなくて、何が前衛だといえるのだろうか。ブロッホの著書は、まさしくこの前衛性を問うているといえる。マルクスと唯物弁証法を避ける、ブロッホの時代でいう「俗流マルクス主義」としての「リベラル」は、この「精神」と「物」の間の「情熱」を理論的に考えないと、ファシズムやスピリチュアリズムとしての参政党に抗せなくなるだろう。この「情熱」は「善悪の彼岸」にあるのだから、「ポリコレ」を越えて、唯物論的に「正しく」考えないといけないはずだ。

僕は「性的差異」もそのような「精神」と「物」を繋げるものであり、あるいは「精神」にも「物」にも還元できない何かだ考えている。そういう意味で「性的差異」は思考することそれ自体の条件であり、同時に限界であるとも思っている。このような「性的差異」が「精神」や「物」へと還元されていく時に、現実的な意味での男根中心主義のロゴスが働き始める。デリダは、それを男根ロゴス中心主義というものを、何かの著作で、男根が性的欲望に関わること自体を否定しているのではなく、男根がジェンダー・セクシュアリティの認識論的・存在論的な布置を決定してしまう、そのロゴスの中心性を批判すべきだということを書いていたはずだ。それは当然で、男根もまた、本来は「精神」にも「物」にも還元できないエクリチュールの問題を持っているものだが、それが精神性や肉体性に還元されるとき、男性優位を司るものになる。しかし、男根という差異を排することはできない。何故なら男根をなくせば、その男根を脱構築する論理もまた動かなくなってしまうからだ。だから、脱構築は形而上学を「男」としてなくすものでもなければ、男根をなくすものでもなく、「精神」と「物」の関係を「差延」の関係として考え直す試みといえよう。それこそが「性的差異」を差異として、「精神」や「物」に還元できない〈モノ〉として考えることである。これはカントの「物自体」や精神分析のフェティシズムの問題、それはマルクスの「商品」のフェティシズムにも通じるものである。そういう意味では「性的差異」を思考するフェミニズムは唯物論的なもののはずだ。
阿部は機関誌の記事で、自らが肩幅を狭めるときに切り取った鎖骨を「鎖骨ペンダント(呪物)」として写真でも示している。ヘーゲルは『精神現象学』の中で、「精神」を無理やり弁証法的に例えるならば、「頭蓋骨」だといえるだろう、という書き方をしていたと思う。僕はここを読むたびに奇妙な感覚に襲われる。というのも、ヘーゲルは何かここに言いにくいものを感じている気がするからである。砕けた言い方をすると、「「精神」は「頭蓋骨」として矛盾として現れている、これが矛盾としての弁証法だ!」というような感じで、ヘーゲルはそんなに堂々と言っている気がしない。どちらかというと、「「精神」という目に見えないものを、あえて言えば不承不承だけど「頭蓋骨」というしかないけどねえ……」というような形で僕は捉えている。何かここに言い難いというか、ヘーゲルが認めたくない何かがある気がする。そういう意味で、阿部の「鎖骨ペンダント(呪物)」とはまさしく、「性的差異」そのもののことだろう。ヘーゲルの言葉を借りれば、「性的差異とは鎖骨である」ということになるはずだ。
また時間があれば、改めてエルンスト・ブロッホの著書については書きたいが、僕は最近仲間と読書会でエルンスト・ブロッホ『この時代の遺産』(池田浩士訳、水声社)を読んだ。その著書の中ではブロッホが、1910年代から40年代にかけて、反資本主義の〈地盤=遺産〉をマルクス主義とナチ、そしてスピリチュアリズムと争っている状況下で、いかにマルクスの唯物弁証法を堅持するかということを思索しており、現代というブロッホの言葉でいえば「多孔的」でグズグズの状況を考える上で、大変良い書物だと思った。ブロッホによれば、ナチやファシズム、スピリチュアリズムもまた反資本主義的な〈地盤=遺産〉を相続し、継承していこうとするが、結局はブルジョワに奉仕するようになるということであった。ブロッホは唯物弁証法、それは先の言葉で言い換えるならば、「精神」にも「物」にも還元されない、「精神」と「物」の間の差延的弁証法を考え抜くことで、そのようなファシズムとスピリチュアリズムを批判しようとする。しかし、「精神」と「物」を考えるという意味で、ブロッホもスピリチュアリズムを完全に脱していない。しかし、そのスピリチュアリズムと唯物論をどうやって「モンタージュ」(唯物弁証法と言い換えられるだろう)して反資本主義の〈地盤=遺産〉を創り出していくのか、ということを唯物論的に考えている。ブロッホのいう「ユートピア」はこのような「モンタージュ」、それはマルクス経済学に基礎に置いた弁証法の運動を基礎に置いた世界を作ることと解釈できる。しかし、その〈地盤=遺産〉はファシズムやスピリチュアリズムが簒奪し、結果的にはあれほど反資本主義の見せかけをなしながらも、結局はそれらが裏切り、ブルジョワに奉仕する世界を作っていくのである。
もちろんブロッホは、ファシズムやナチの「情熱」は「本物」であるとし、それを嘘といっているわけではない。ブロッホは本来は反資本主義をマルクス主義が領導するはずが、その反資本主義をめぐる「情熱」を理論的に弁証法化し得ていないという批判をしているのだ。その反資本主義の「情熱」を「俗流マルクス主義」が軽視しながら、ファシズムやスピリチュアリズムに傾倒している奴らもいずれ眼を醒まし、その後は共産党が「情熱」の主導権を握るはずだと考えていたわけだが、そのような「俗流マルクス主義」の期待(観念論)は裏切られ、1933年以降のナチの台頭を招く。ブロッホは「俗流」に対抗して唯物弁証法を堅持しようとし、その弁証法が実は芸術や文学と連関しており、それが「遺産」でもあるとしている。これも「精神」と「物」の差延的弁証法につながるが、「俗流マルクス主義」はそのような弁証法を無視するので、反資本主義の「情熱」を理論化できないのである。そしてその「情熱」はナチやスピリチュアリズムに流れ込んでいく。これは現代においては「リベラル」がこの「情熱」をつかまえることができず、参政党やカルトにその「情熱」を横領されていく過程にも似ている。この「情熱」こそ、本来は「精神」と「物」の差延的弁証法の中で、反資本主義の欲望を現実に定位していかなければならないものであり、前衛党がそれを指導しなければならないはずである。しかし、なんの人気取りか、マルクスや唯物弁証法を前面に押し出さなくなった党は、そういう「情熱」を全く掬えなくなった。結果的にその情熱は観念論に横領される。「リベラル」と呼ばれるイデオロギー集団は、その意味で「情熱」を取り逃がしている。この「情熱」が掬えない状態のことを、僕は「ポリコレ」として批判されているのだと思う。この「情熱」はマルクスならばフェティシズム、精神分析の対象a、カントの物自体のように、観念にはどうしても包摂できない欲望のはずだ。前衛党自体もそういう対象だったはずである。しかし、そういう「情熱」を掬おうとせず、自民党を批判して左派的正しさを主張して、彼らを啓蒙すれば、いずれまた正常な世界がやってくるという「観念論」を信じている限り、ブロッホが経験したナチの台頭と似た状態を招くだろう。
少なくともブロッホは、ナチやスピリチュアリズムの「情熱」を否認せず、反資本主義の「遺産」に関わるものとして真剣にとらえている。では現代の所謂「リベラル」はどうだろうか。「情熱」を掬い取る唯物弁証法を「リベラル」は保持しようとしているだろうか。僕は非常に懐疑的である。現実の問題として自民党を批判したり、不平等や差別を批判すること自体には、僕は全く異論はないし、それを差延的現実の運動でやっている人はいる。しかし、「情熱」を掬い取る理論に関しては、それほど真剣に考えられていないのではないか。いずれ別に書きたいが、パチンコやラーメンなどもそうだ。パチンコに並んでいる人、油とでんぷんのかたまりとしてのラーメンに並んでいる人、彼らの「情熱」をどうやって掬うのか。掬わないといずれ参政党などがわかりやすい形で横領していくのではないだろうか。僕は真剣にマルクスの唯物弁証法をやり直すしかないと思う。
そういう意味で「鎖骨ペンダント」は一つの「情熱」であり、「性的差異」という欲望の形態そのものといえる。現代の科学技術においては生物学的男性は妊娠ができない中で、妊娠を目指すという矛盾的弁証法は、単純な意味でのスピリチュアリズムや観念論では思考することは無理だろう。「精神」と「物」の間にしか「情熱」は存在しないからである。読書会でも言ったのだが、「性的差異」「トランスジェンダー」「女性」の問題を、前衛党は唯物弁証法の柱として徹底すべきだ。ジェンダー・セクシュアリティの話題ばかりしていたから大衆が離れていく、それをテーマにするから選挙に負けるなどという、男根主義者のくだらない戯言など真に受けず、ジェンダー・セクシュアリティを唯物論的に考えることこそ「情熱」を掬い取ることになるという立場に立つべきである。そうしないと「ポリコレ」を越えることはできない。ジェンダー・セクシュアリティ、あるいはケアの問題には、その唯物弁証法と「情熱」の問題が結集している。前衛党がここに関わらなくて、何が前衛だといえるのだろうか。ブロッホの著書は、まさしくこの前衛性を問うているといえる。マルクスと唯物弁証法を避ける、ブロッホの時代でいう「俗流マルクス主義」としての「リベラル」は、この「精神」と「物」の間の「情熱」を理論的に考えないと、ファシズムやスピリチュアリズムとしての参政党に抗せなくなるだろう。この「情熱」は「善悪の彼岸」にあるのだから、「ポリコレ」を越えて、唯物論的に「正しく」考えないといけないはずだ。















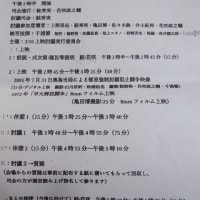

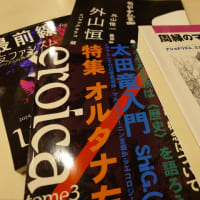



※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます