参政党の「躍進」が話題となり、その危機感も手伝って、僕の見ているSNSのタイムラインを見ても、参政党への批判があふれているといってもよい状態である。僕が見るところ、その批判はネトウヨへの批判に通じるものがある。つまり、「参政党=ネトウヨ」という構図がそこから見て取れる。ただ、参政党がネットでも公開している「政策」だけを読むと、いわゆる「常軌を逸した」ものではなく、広く「国民」のナショナリズムや不安に応えようとしている側面が強調されており、その部分だけが受け取られれば、支持する人が増えると予想はできる。僕は前から思っており、かつてSNSにも書いたが、実際は「国民」こそが「ネトウヨ」であると思っている。これはベネディクト・アンダーソン『想像の共同体』(白石隆+白石さや訳、書籍工房早山)のいう「国家語」を通した形で想像的に共同体化されている「国民=国家」の枠組みを念頭にしたものだ。参政党の掲げる「日本人ファースト」という「想像の共同体」も、変異しながらもそれへの回帰と見ることができるだろう。金融資本主義やグローバリゼーションの中で、その「想像の共同体」が危機に瀕すると、そのナショナリズムが「○○ファースト」という形で回帰してくる。それは日本だけではなく、特に金融資本主義とグローバリゼーションの恩恵を強く受けている(いた)国々で起こっていることだといえそうだ。僕はその意味で「日本人ファースト」を掲げる「参政党」こそが「国民」そのものだと見做している。即ち僕の中では「参政党=(日本)国民」が成立する。だから参政党の支持率が上がるのは当然だろう。自民党がかつて担っていた「国民ファースト」のリベラリズムを参政党がある部分で担おうとしているからである。かつてあったとされる「一億総中流」という「想像の共同体」は、もちろん日本の内外からの搾取によって成り立っていたわけで、その搾取構造が「マジョリティ」としての「国民」のナショナリズムを支えてきた。この「マジョリティ」のリベラリズムをもう一度取り戻そうという欲望が、自民党から参政党へと向き始めているのではないだろうか。
その意味で「参政党」は「国民」という「マジョリティ」の欲望を「代表=代行」(代表制)する、一端の政党となってしまうのだ。参政党の環境問題や食糧問題、そして「国体」に関わる身分制度を肯定する差別的で排外主義的な主張を見ると、そこにカルトやスピリチュアリズムの問題など、批判すべき問題を見出すことはできる。だが、「国民」という「想像の共同体」や、「一億総中流」等もまた立派なスピリチュアリズムだろう。それは様々な人が論じてきたように、ロマン主義的ナショナリズムに支えられた「国民の歴史」も含めたスピリチュアリズムである。その「国民」のリベラリズムというスピリチュアリズムは、国の内外の「植民地」からの搾取が支えていたわけで、その意味では厳然とした搾取の下部構造が「国民」というスピリチュアルな上部構造を決定していたといえる。その搾取構造を否認し、あるいは隠蔽しながら、参政党はカルトとスピリチュアリズムに毒された異端で、「国民」のリベラリズムを壊すものだと批判するのは、おかしなこととなるだろう。むしろ「国民」という「想像的=スピリチュアル」な搾取構造で維持されてきた「国民=マジョリティ」こそ参政党と同根だと言いたくなるくらいである。もし参政党を批判するならば、まずは「国民」という「マジョリティ」のスピリチュアリズムを批判しなければならない。「日本人ファースト」とは「国民」ということだからだ。そして、それはとりもなおさず「マジョリティ」への批判であり、その「マジョリティ」が日常から抱き続けるスピリチュアルな上部構造を支える、搾取の下部構造としての資本主義への批判へと至るしかない。そもそも「国民」のリベラリズムを守るために、それを破壊しようとする参政党を批判するというのは、おかしな話だといえる。何故なら、批判しようとする参政党の主張は、ほとんど「マジョリティ」としての「国民」の主張と何ら変わりがないからである。「国民=国家」とそれを支える資本主義への批判なしに参政党を批判しても、自家撞着しか起こさないのはそのためだ。
ただここでいう「国民=国家」やナショナリズムへの批判は、安易なグローバリゼーションの擁護や「国民=国家」の解体のことではない。アメリカのトランプ大統領を見てもわかるように、「国民=国家」を超えグローバリゼーションを推し進めるように見える新自由主義的な金融資本主義は、「国民=国家」のスピリチュアリズムと「○○ファースト」という排外主義を媒介として、その支配を広げようとするからである。ナショナリズムやスピリチュアリズムによるGestell(ハイデガーのいう)の作用を利用して、新自由主義的金融資本主義は、その下部構造(Gestell・骨組み)を獲得している。そして、それによって「マジョリティ」としての「国民」は自分たちを支える搾取構造を、リベラリズムの中で合法的に肯定していく。そういう意味では、新自由主義的資本主義は「国民」としての「マジョリティ」と結託するしかない。参政党を批判するには「マジョリティ」としての「国民」への批判をするしかないだろう。それは「国民」のスピリチュアリズムを支える資本主義批判へと至る。かつて「マジョリティ」としてのブルジョワを批判する「プロレタリアート」という立場があったわけだが、ブルジョワ政党としての参政党を批判するには、「参政党=国民」のスピリチュアリズムを批判する唯物論的左翼性とその理論が必要だと僕は思う。前にも書いたがその意味で、左翼を自認する政党は性的少数者やケア労働も含め、労働やそれをめぐる物質的な問題を「国民」と資本主義批判とに結びつけて、もぐらたたき的に参政党的主張、即ち「国民」の主張を批判して叩きつづけて回るしかない。共産党も含め、本来有していなければならない自らの唯物論性をポピュリズムから否認して、天皇制批判まで引っ込めて「国民に寄り添う」などということをしていたら、それは「参政党に寄り添う」こととなってしまい、「マジョリティ」には最初から負けざるを得ないだろう。そうではなく「国民=マジョリティ」に対して、その下部構造を露呈させることで、「お前たちは国民(参政党)ではない」というべきだと思う。グローバリゼーションへの批判と「国民」(排外主義者)への批判という二方向への批判は、資本主義を支える搾取という矛盾的構造への批判を通してやれるはである。参政党を批判する人は、やはり「マジョリティ」とその「国民」のスピリチュアリズムを批判する唯物論性と左翼であることが必要であろう。当然、参政党を批判する右翼(保守)も、この唯物論性と左翼性を持つ必要がある、と僕は考える。
また、マスメディアの参政党に対する報道に対し、その参政党への批判者から、参政党の宣伝になっている、参政党を肯定している、などの批判が頻繁になされているが、あれは意識的にも無意識的にも、マスメディアによって「意図的」になされていると思う。それはマスメディアが「国民」のためのメディアだからである。そして根拠なく言えば、マスメディアに携わるリベラルな記者の中にも多くの参政党支持者がいるはずだ。それは自分が民主主義者でリベラルであるという意識と葛藤なく同居しているはずであろう。そしてこれは「読解」のレベルだが、SNSで参政党への批判を引用などを駆使してやっているツイートや記事の、そこそこの数が、まるで参政党の宣伝やよく読まないと参政党と同じ意見のように見えてくるものが存在する。これも「国民」という「マジョリティ」の意識を、その批判者も共有しているからだと、僕は判断している。
その意味で「参政党」は「国民」という「マジョリティ」の欲望を「代表=代行」(代表制)する、一端の政党となってしまうのだ。参政党の環境問題や食糧問題、そして「国体」に関わる身分制度を肯定する差別的で排外主義的な主張を見ると、そこにカルトやスピリチュアリズムの問題など、批判すべき問題を見出すことはできる。だが、「国民」という「想像の共同体」や、「一億総中流」等もまた立派なスピリチュアリズムだろう。それは様々な人が論じてきたように、ロマン主義的ナショナリズムに支えられた「国民の歴史」も含めたスピリチュアリズムである。その「国民」のリベラリズムというスピリチュアリズムは、国の内外の「植民地」からの搾取が支えていたわけで、その意味では厳然とした搾取の下部構造が「国民」というスピリチュアルな上部構造を決定していたといえる。その搾取構造を否認し、あるいは隠蔽しながら、参政党はカルトとスピリチュアリズムに毒された異端で、「国民」のリベラリズムを壊すものだと批判するのは、おかしなこととなるだろう。むしろ「国民」という「想像的=スピリチュアル」な搾取構造で維持されてきた「国民=マジョリティ」こそ参政党と同根だと言いたくなるくらいである。もし参政党を批判するならば、まずは「国民」という「マジョリティ」のスピリチュアリズムを批判しなければならない。「日本人ファースト」とは「国民」ということだからだ。そして、それはとりもなおさず「マジョリティ」への批判であり、その「マジョリティ」が日常から抱き続けるスピリチュアルな上部構造を支える、搾取の下部構造としての資本主義への批判へと至るしかない。そもそも「国民」のリベラリズムを守るために、それを破壊しようとする参政党を批判するというのは、おかしな話だといえる。何故なら、批判しようとする参政党の主張は、ほとんど「マジョリティ」としての「国民」の主張と何ら変わりがないからである。「国民=国家」とそれを支える資本主義への批判なしに参政党を批判しても、自家撞着しか起こさないのはそのためだ。
ただここでいう「国民=国家」やナショナリズムへの批判は、安易なグローバリゼーションの擁護や「国民=国家」の解体のことではない。アメリカのトランプ大統領を見てもわかるように、「国民=国家」を超えグローバリゼーションを推し進めるように見える新自由主義的な金融資本主義は、「国民=国家」のスピリチュアリズムと「○○ファースト」という排外主義を媒介として、その支配を広げようとするからである。ナショナリズムやスピリチュアリズムによるGestell(ハイデガーのいう)の作用を利用して、新自由主義的金融資本主義は、その下部構造(Gestell・骨組み)を獲得している。そして、それによって「マジョリティ」としての「国民」は自分たちを支える搾取構造を、リベラリズムの中で合法的に肯定していく。そういう意味では、新自由主義的資本主義は「国民」としての「マジョリティ」と結託するしかない。参政党を批判するには「マジョリティ」としての「国民」への批判をするしかないだろう。それは「国民」のスピリチュアリズムを支える資本主義批判へと至る。かつて「マジョリティ」としてのブルジョワを批判する「プロレタリアート」という立場があったわけだが、ブルジョワ政党としての参政党を批判するには、「参政党=国民」のスピリチュアリズムを批判する唯物論的左翼性とその理論が必要だと僕は思う。前にも書いたがその意味で、左翼を自認する政党は性的少数者やケア労働も含め、労働やそれをめぐる物質的な問題を「国民」と資本主義批判とに結びつけて、もぐらたたき的に参政党的主張、即ち「国民」の主張を批判して叩きつづけて回るしかない。共産党も含め、本来有していなければならない自らの唯物論性をポピュリズムから否認して、天皇制批判まで引っ込めて「国民に寄り添う」などということをしていたら、それは「参政党に寄り添う」こととなってしまい、「マジョリティ」には最初から負けざるを得ないだろう。そうではなく「国民=マジョリティ」に対して、その下部構造を露呈させることで、「お前たちは国民(参政党)ではない」というべきだと思う。グローバリゼーションへの批判と「国民」(排外主義者)への批判という二方向への批判は、資本主義を支える搾取という矛盾的構造への批判を通してやれるはである。参政党を批判する人は、やはり「マジョリティ」とその「国民」のスピリチュアリズムを批判する唯物論性と左翼であることが必要であろう。当然、参政党を批判する右翼(保守)も、この唯物論性と左翼性を持つ必要がある、と僕は考える。
また、マスメディアの参政党に対する報道に対し、その参政党への批判者から、参政党の宣伝になっている、参政党を肯定している、などの批判が頻繁になされているが、あれは意識的にも無意識的にも、マスメディアによって「意図的」になされていると思う。それはマスメディアが「国民」のためのメディアだからである。そして根拠なく言えば、マスメディアに携わるリベラルな記者の中にも多くの参政党支持者がいるはずだ。それは自分が民主主義者でリベラルであるという意識と葛藤なく同居しているはずであろう。そしてこれは「読解」のレベルだが、SNSで参政党への批判を引用などを駆使してやっているツイートや記事の、そこそこの数が、まるで参政党の宣伝やよく読まないと参政党と同じ意見のように見えてくるものが存在する。これも「国民」という「マジョリティ」の意識を、その批判者も共有しているからだと、僕は判断している。














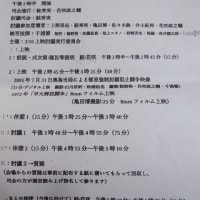

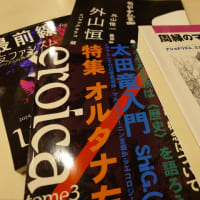



※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます