ちょうど前回、映画の『ゲバルトの杜』と『レフト・アローン』の比較?を書いたのだが、それについて友人と話した。その話は、『ゲバルトの杜』への評価であって、友人とおおむね評価は一致したのであるが、その後帰宅すると、東京大学の学費値上げ反対闘争をしていた学生に対して、学内に大学当局が警察権力を介入させたということで、SNS上で批判がなされていた。それこそ『レフト・アローン』の中で発言されていたと思うが、大学が自治の問題において警察を介入させるのは、学生を含む大学の構成員に生命の危機がある緊急事態の場合のみではないか。そういう意味で、今回の総長団交後に警察権力を介入させたというのは、大学の自治や学問の自由を守る立場の大学の行為としては、非難されるべきだろう。
それを見ながら、ちょうどその友人と映画との絡みで、東大の学費値上げ反対闘争の話になり、しかしそれ故その時点では東大への警察権力の介入は知らなかったが、その会話のなかで、僕は津村喬の『われらの内なる差別』(三一書房)の中にある「部落、沖縄、朝鮮があるから帝大がある」という言葉を思い出して話していた。津村は「管理社会」の構造として「企業・大学」の「〈異邦人〉」に対する差別構造を批判し、この言葉は『ゲバルトの杜』でも問題にするべきはずの、大学(「帝大」)という生政治的空間、生権力の支配構造への批判の中で記されたものであった。このことは現状の東京大学にいえることだろうし、「管理社会」のモデルとなっているほとんどの大学に当てはまることだろう。僕は友人に、この言葉は「天皇がいるから部落差別がある」という差別構造の問題とも相同的なものだともいえるし、大学の構造でいえば、「教員がいるから学費値上げがある」というべきなのかもしれないなというと、友人は「そうですよ」というと、教員は「天皇の側」にいるんだから、それをちゃんと自覚しなければならないと、批判した。本来ならば、学費値上げ反対闘争における「管理社会」の構造の問題は、学費に注目する場合、それは教職員の人件費の構造的な問題に行きつく。そこには当然、国からの補助金による支配なども全て含まれている。友人の言葉は、現状において大学から給料をもらって生活している、僕への批判にも当然繋がっているのである。
そのため、この「天皇の側」に存在し、「管理社会」の構造自体を支える教職員が、学費値上げ反対闘争の学生に対峙した時の認識は、自分が飯を食べているこの給与の環境を変革されて倒されてしまうかもしれない、という恐怖になるのではあるまいか。そういう意味では学費値上げ反対闘争は、教員にとって恐怖の対象となるはずである。この「恐怖」を前提として、運動にどう接するかは、その教職員個々人の対応としか言えないが、だがそれでもその「恐怖」は拭い去れないし、「恐怖」なしでこの問題が解決できるというのは欺瞞になるだろう。仮に「天皇の側」にいる自分たちの生活や待遇はそのままで、何ものも変化しない中で学費も上がらないという状況を願うとしたら、それは要は何も変わらない、変えないための運動を支持するという、かつてスラヴォイ・ジジェクがいった、現状を変えないための運動という、倒錯の問題である。
この「恐怖」の問題抜きには、おそらく運動はないはずだ。
それを見ながら、ちょうどその友人と映画との絡みで、東大の学費値上げ反対闘争の話になり、しかしそれ故その時点では東大への警察権力の介入は知らなかったが、その会話のなかで、僕は津村喬の『われらの内なる差別』(三一書房)の中にある「部落、沖縄、朝鮮があるから帝大がある」という言葉を思い出して話していた。津村は「管理社会」の構造として「企業・大学」の「〈異邦人〉」に対する差別構造を批判し、この言葉は『ゲバルトの杜』でも問題にするべきはずの、大学(「帝大」)という生政治的空間、生権力の支配構造への批判の中で記されたものであった。このことは現状の東京大学にいえることだろうし、「管理社会」のモデルとなっているほとんどの大学に当てはまることだろう。僕は友人に、この言葉は「天皇がいるから部落差別がある」という差別構造の問題とも相同的なものだともいえるし、大学の構造でいえば、「教員がいるから学費値上げがある」というべきなのかもしれないなというと、友人は「そうですよ」というと、教員は「天皇の側」にいるんだから、それをちゃんと自覚しなければならないと、批判した。本来ならば、学費値上げ反対闘争における「管理社会」の構造の問題は、学費に注目する場合、それは教職員の人件費の構造的な問題に行きつく。そこには当然、国からの補助金による支配なども全て含まれている。友人の言葉は、現状において大学から給料をもらって生活している、僕への批判にも当然繋がっているのである。
そのため、この「天皇の側」に存在し、「管理社会」の構造自体を支える教職員が、学費値上げ反対闘争の学生に対峙した時の認識は、自分が飯を食べているこの給与の環境を変革されて倒されてしまうかもしれない、という恐怖になるのではあるまいか。そういう意味では学費値上げ反対闘争は、教員にとって恐怖の対象となるはずである。この「恐怖」を前提として、運動にどう接するかは、その教職員個々人の対応としか言えないが、だがそれでもその「恐怖」は拭い去れないし、「恐怖」なしでこの問題が解決できるというのは欺瞞になるだろう。仮に「天皇の側」にいる自分たちの生活や待遇はそのままで、何ものも変化しない中で学費も上がらないという状況を願うとしたら、それは要は何も変わらない、変えないための運動を支持するという、かつてスラヴォイ・ジジェクがいった、現状を変えないための運動という、倒錯の問題である。
この「恐怖」の問題抜きには、おそらく運動はないはずだ。














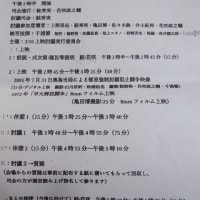





※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます