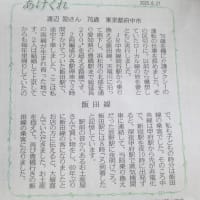未だ会社勤めだった1991(平成3)年3月、青木鈴慕師のご指名により、FHKFM「邦楽のひととき」(現在は午前11:20~11:50)に出演させていただいた。
邦楽のうち、箏と尺八は毎週月曜日に放送である。
最初に出演したのは「明治松竹梅」で、箏は米川社中の藤代文津奈、斉藤文香代ら3人の賛助出演だった。(私はNHKに出演出来るオーディションを受けていないが、多分青木先生の推薦だったから出演出来たのであろう)
大田区大森の「米川会館」へ2回程伺って練習し当日も練習後、箏屋さんのワゴン車で一緒にNHKスタジオに入った。
録音は一発録りだった。初めてにしては、あまり極度の緊張はしていなかった。
この「明治松竹梅」が放送された時の、曲の紹介アナウンサーは有名な葛西聖司氏だった。
独特の丁寧で、やさしく包むような声で紹介していただけて、大変光栄だった。
初めて放送されて、名前が出た時は身震いした。
それから15~16年位経ったのであろうか。飲食店で偶然隣り合わせでお会いした件は、以前グログに記載したが、改めて記すと西新宿の相撲料理「方屋」での昼食時の事である。
葛西氏とは面識は無い。テレビの邦楽番組で顔を知っており、本当に千載一隅のチャンスでここで声をかけなかったら、一生悔いが残ると私の放送時の事を話してみた。
当然、葛西アナはラジオの「ニュ-ス」や「邦楽番組」で忙しく、一つ一つの事は覚えている筈がない。「そうでしたか」で済まされてしまった。止むを得まい。
ただ、お礼を言って邦楽界の世間話をした。
さて、2回目の放送は1991(平成3)年7月の「泉」だった。
箏は上條妙子。青木先生に依頼され、高田馬場の研究所(稽古場)で練習は一回のみだった。
しかし、私はこの曲は習ってなかったので、楽譜の間違いはその場で指摘された。
一通り練習した後、先生に「うん、いいものを持っているね」と褒められて、うれしかった。
録音当日、NHKスタジオには箏の運搬を手伝った青木鈴慕師のご子息、彰時氏も入っていた。
先ず、一回リハーサルしたのだが、音がかすれて出ない。非常事態宣言である。心臓はバクバク、顔面蒼白。
しかし。本番では心を強く持って、開き直り、無事上手く演奏出来た。
この時の状況は1991年9月、高校卒業25周年記念誌に掲載されたので引用する。
NHK録音のこと(6月25日)
「本番行きます。エー泉」NHK509スタジオの広い空間にマイクから太い声が流れる。緊張の一瞬だ。
イントロは箏の独奏で「シャンシャンシャンシャン」と始まる。順調なスタートだ。さあ頑張るぞと自分に言い聞かす。直前のリハーサルでは緊張のため唇がこわばって、尺八の音がスカスカしていた。本番は大丈夫だろうか、不安の気持ちが頭をよぎる。
箏の独奏が終わった。さあ合奏の始めの小節だ。きれいに吹こう、そう思って音を出す。
あっ、リハーサルより音が良い。律も良い。調子は良さそうだ。尺八は本来音の狂い易いことこの上ない。穴が五つしか開いていない。メリ・カリの奏法で♯・♭等正しい音を出すのは困難である。
何がそうさせたのか、尺八が好きだ。楽器の単純さゆえの奏法の難しさ。奥の深さに魅かれる。オーケストラも入る広いスタジオは残響も十分だ。
途中までどうにか来た。さあ次は尺八の独奏だ。気合を入れる。無難だった。再び合奏。テンポを速めてテクニックを必要とする終わりに近づいた。掛け合い良し。後はハのトリルだ。ちょっと短かったが箏がうまくつないでくれた。
「ハイ、御苦労様でした」一発で決めたうれしさがあった。
7月29日NHKFMにオンエア。全国に流れた。
本番で上手く行ったのは幸運だった。お蔭様で多分好評だったのだろうか、1992年6月に再放送された。
残念ながら、あの時以上の演奏がもう出来ないのである。
3回目の放送も米川社中で「末の契」だった。1992(平成4)年3月に放送。
今度は箏 米川文威清(現米川文清)、三絃 五月女文紀の賛助出演である。
米川文勝之(ふみかつ=現米川文子人間国宝)先生の指導の下、やはり2回ほど練習に伺った。
この時、米川先生の調絃時の音に圧倒された。もう音そのものが芸術だった。
この曲は本番で手事に入って高音の連続ヶ所で間が合わず、大変残念だったが録音は一回で終了した。一般の人には判らないかも知れないが、私には悔やまれる演奏となってしまった。
邦楽のうち、箏と尺八は毎週月曜日に放送である。
最初に出演したのは「明治松竹梅」で、箏は米川社中の藤代文津奈、斉藤文香代ら3人の賛助出演だった。(私はNHKに出演出来るオーディションを受けていないが、多分青木先生の推薦だったから出演出来たのであろう)
大田区大森の「米川会館」へ2回程伺って練習し当日も練習後、箏屋さんのワゴン車で一緒にNHKスタジオに入った。
録音は一発録りだった。初めてにしては、あまり極度の緊張はしていなかった。
この「明治松竹梅」が放送された時の、曲の紹介アナウンサーは有名な葛西聖司氏だった。
独特の丁寧で、やさしく包むような声で紹介していただけて、大変光栄だった。
初めて放送されて、名前が出た時は身震いした。
それから15~16年位経ったのであろうか。飲食店で偶然隣り合わせでお会いした件は、以前グログに記載したが、改めて記すと西新宿の相撲料理「方屋」での昼食時の事である。
葛西氏とは面識は無い。テレビの邦楽番組で顔を知っており、本当に千載一隅のチャンスでここで声をかけなかったら、一生悔いが残ると私の放送時の事を話してみた。
当然、葛西アナはラジオの「ニュ-ス」や「邦楽番組」で忙しく、一つ一つの事は覚えている筈がない。「そうでしたか」で済まされてしまった。止むを得まい。
ただ、お礼を言って邦楽界の世間話をした。
さて、2回目の放送は1991(平成3)年7月の「泉」だった。
箏は上條妙子。青木先生に依頼され、高田馬場の研究所(稽古場)で練習は一回のみだった。
しかし、私はこの曲は習ってなかったので、楽譜の間違いはその場で指摘された。
一通り練習した後、先生に「うん、いいものを持っているね」と褒められて、うれしかった。
録音当日、NHKスタジオには箏の運搬を手伝った青木鈴慕師のご子息、彰時氏も入っていた。
先ず、一回リハーサルしたのだが、音がかすれて出ない。非常事態宣言である。心臓はバクバク、顔面蒼白。
しかし。本番では心を強く持って、開き直り、無事上手く演奏出来た。
この時の状況は1991年9月、高校卒業25周年記念誌に掲載されたので引用する。
NHK録音のこと(6月25日)
「本番行きます。エー泉」NHK509スタジオの広い空間にマイクから太い声が流れる。緊張の一瞬だ。
イントロは箏の独奏で「シャンシャンシャンシャン」と始まる。順調なスタートだ。さあ頑張るぞと自分に言い聞かす。直前のリハーサルでは緊張のため唇がこわばって、尺八の音がスカスカしていた。本番は大丈夫だろうか、不安の気持ちが頭をよぎる。
箏の独奏が終わった。さあ合奏の始めの小節だ。きれいに吹こう、そう思って音を出す。
あっ、リハーサルより音が良い。律も良い。調子は良さそうだ。尺八は本来音の狂い易いことこの上ない。穴が五つしか開いていない。メリ・カリの奏法で♯・♭等正しい音を出すのは困難である。
何がそうさせたのか、尺八が好きだ。楽器の単純さゆえの奏法の難しさ。奥の深さに魅かれる。オーケストラも入る広いスタジオは残響も十分だ。
途中までどうにか来た。さあ次は尺八の独奏だ。気合を入れる。無難だった。再び合奏。テンポを速めてテクニックを必要とする終わりに近づいた。掛け合い良し。後はハのトリルだ。ちょっと短かったが箏がうまくつないでくれた。
「ハイ、御苦労様でした」一発で決めたうれしさがあった。
7月29日NHKFMにオンエア。全国に流れた。
本番で上手く行ったのは幸運だった。お蔭様で多分好評だったのだろうか、1992年6月に再放送された。
残念ながら、あの時以上の演奏がもう出来ないのである。
3回目の放送も米川社中で「末の契」だった。1992(平成4)年3月に放送。
今度は箏 米川文威清(現米川文清)、三絃 五月女文紀の賛助出演である。
米川文勝之(ふみかつ=現米川文子人間国宝)先生の指導の下、やはり2回ほど練習に伺った。
この時、米川先生の調絃時の音に圧倒された。もう音そのものが芸術だった。
この曲は本番で手事に入って高音の連続ヶ所で間が合わず、大変残念だったが録音は一回で終了した。一般の人には判らないかも知れないが、私には悔やまれる演奏となってしまった。