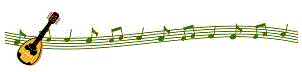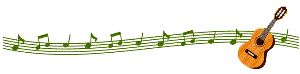秋晴れの11月4日(土)立川市市民会館(たましんRISURU大ホール)にて毎年恒例の立川マンドリンクラブ第36回定期演奏会を開催致しました。
プログラムは
[オープニング] グリーン グリーン (B.Sparks/B.McGuire)
[第1部]
亜麻色の髪の乙女 (C.Debussy)
赤いスイートピー (呉田軽穂)
幸せの黄色いリボン (I.Levine)
黄昏のワルツ (加古隆)
碧空 (J.Rixner)
虹彩 (丸本大吾)
[第2部]
バラ色のメヌエット (P.Mauriat)
雪~ロマンツァとボレロ~ (H.Lavitrano)
黒い瞳 (ロシア民謡)
カルメン組曲より6曲 (G.Bizet)
[アンコール] にじいろ (絢香)
[エンディング] 虹の彼方に (H.Arlen)
今年のテーマは「色彩」、プログラムに色に因む曲を配しステージ衣装も第1部は思い思いの色のカラーシャツやブラウスを着用、第2部では女性メンバー手作りの赤いバラのコサージュを襟につけて演奏致しました。
またカルメン組曲の編曲者、久保田孝先生にご来聴いただくという記念の演奏会となりました。
いつものことながら弾きにくい箇所も多々ありましたが私も精一杯演奏致しました。
3連休の中日で行楽日和でしたが、ほぼ満席のご来場者においでいただくことができました。
まことに有難うございました。
関連ブログ:
・第36回立川マンドリンクラブ定演のちらしができました(2017.09.10)
・立川マンドリンクラブ第35回定演終わる(2016.12.11)