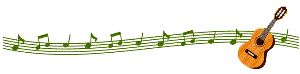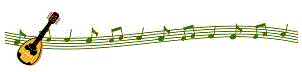
コロナの影響で自粛、自粛、どこにも行けず巣ごもり状態、自然と家で静かにCDを聴く機会も増えていますが、最近このCDを取り巻く環境はいいとは言えないようです。
何もわざわざCDを買わなくても安価なレンタルサービスやサブスク(サブスクリプション)、ストリーミング配信、ダウンロードなど選択肢が増え、CDが売れなくなってCDショップが姿を消したり中古CDの買取店がなくなったりしているようです。
買ったCDをiTunesに入れてしまえばCD自体はお役目を終えてゴミ同然、新品のCDを惜しげもなく捨ててしまう人さえいます。
このような折CDを自作しようという試みは時代に逆行しているようにさえ思えてしまいます。
私自身PCには1万曲以上のmp3音楽ファイルを保存して聴いていますが、それでも自分で作ったCDには格別な愛着を感じます。
今回HPに「マイ音楽CDを作ろう」と題してCDの作り方をアップしました。
ついでにトップページの「マンドリン玉手箱」に別館を設け、「マイ音楽CDを作ろう」は別館のほうに載せることとしました。
内容は
1 どんなCDを準備するか
(1) CDの種類
(2) 音楽用かデータ用か
(3) CDの容量
(4) CDの記録速度
(5) レーベル印刷する場合
(6) CDメーカー
(7) CD収納ケース
2 音楽ファイルの編集
(1) 音楽ファイルの分離
(2) 無音区間の削除
(3) 音量の統一
3 音楽CD、データCDとライティングソフト
4 レーベル面の印刷
5 CDジャケットの制作
最近のプリンタはレーベルプリント機能のある機種が少なくなってきているように感じます。
在宅時間の増えた今、気に入った曲を集めた自分だけの1枚を作ってみられてはいかがでしょうか。
場所をふさぐレコードですがレコードジャケットをそのまま縮小してCDジャケットのデザインに用いれば、あたかもレコードを小型にしたような感じに仕上げることができ、これなら思い切ってレコードを処分することもできるのではないでしょうか。

私の作品