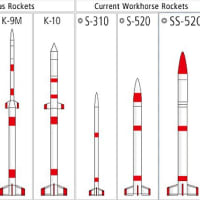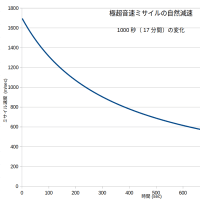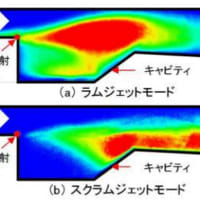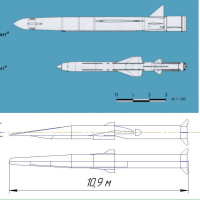静岡に「崩し字を読む」と言うPDFのテキストがあって、それを読んでいます。
その一方で、あれ?平安時代の文字の方が分かり易くない?と思うのです。
やっぱり、これも「推測する文字」なのだな?と思う次第です。
BS歴史館の「岩倉具視卿」を見ていたら「岩倉卿は公家らしくない公家で、武家のような文字を書く」とありまして、やっぱり、あの武家の江戸時代の文字は「異常」だったのだ?
と思う訳です。
ただ、この「推測する文字」は、どちらかというと昔では普通で2500年前のアルファベット運動(オリエントですね)と1000年前の漢字辞典の整備(唐の科挙の為)以前は、文字は「多分この文書は、こんな事を言っているんだろうね?」って程度のもので、それが今の文書と似たような「適切な伝達」をするのは、今も面倒なのですが、もっともっともっと面倒なカタチだったのです。
笑ってしまうのは宮城谷昌光氏の小説は、最初「書を送る」って事で手紙を書くシーンが描かれていますが、これが、後になると「使者を派遣する」となります。
この頃になると、字体が、適当で、文字で情報を伝える事は絶望的であると分かってきたのです。
文字は情報の一つで、その他の情報を照合して、推測するしか出来ないのです。
虫獄の古文書は、実は絶望的で、妙で妙で妙でした。
先ず、甲骨文字の時点では、特徴的な物事しか、文字化していないのです。
必要な文字数は圧倒的に足らず、その結果、足りない文字で何とかする事となり、音韻を表す文字を「借り文字」として使うのです。
江戸時代も似たようなものがあり「値」に「直」が当てられる事がありました。
ですが古代漢文では、何か記述するのに、音でしか割り当てられず、それが必ずしも、音を表記する文字の元の意味とは違うので「コレは、意味で、この字なのか?音で、この字なのか?」と言う推測で行う事が一般的となりました。
そんで「秦の始皇帝」が出てきたのですが、文字と度量衡と暦の統一のうち、度量衡と暦は何とかなったのですが、文字は、テキトーでして、最初まとめようと努力はしたのですが、そこはそれ、文書の内で官の文書って、一部中の一部で、結局、民が適当に色々やるので、文字が乱れました。
それで出てきたのは、文字の意味が場所によって異なると言う異常事態が1200年間ずっと続き、日本で言うと50文字の「いろは」が「変態仮名」となり100文字以上ある。と言う妙な状態でした。
1000年前、科挙の制度を確立する上に当たり、厳格な採点をする為には、文字の表現を改めると言う意味で辞典が確定され、その後文字が限定される事となり、文字の意味が明確化しました。
一方で漢字に纏わるエトセトラは、複雑化、多画化を行い龍を5つも書いたりする馬鹿?と言うような文字とかが出てきて、漢字は2万字とか3万字とか出来てきたのです。
そんで崩し字ですが、まぁ、チョンチョンって感じで、妙な手抜きしている奴ほど読み難いもので、崩すにしても崩しようがあろう!と怒りたくなります。候ってのが右と左のチョンチョンで終わりです。
分かるかよ!
そこで分かったのは「古文書」は「雰囲気で読む」みたいです。
読むというより感じる、感じるというより推測する。最終的には推理する。
機能的にはダメ人間ですわ…です。
文明開化、結構意外な展開でした。。。。。。。。。。。。。。