「ロスト・ワールド/ジュラシック・パーク」(1997)
「ジュラシック・パーク」の続編。今回も原作者は、マイケル・クライトンで、ベストセラーになった。脚本は、クライトン自身と前作同様にデビッド・コープが担当した。特にコープは、この時期にトム・クルーズ主演の「ミッション・インポッシブル」の脚本も書いている。特殊効果の担当は、これもまた前作同様にスタン・ウィストン、デニス・ミューレン、マイケル・ランティエリ。
インジェン社の会長がハモンド氏から甥のルドローにかわりジュラシック・ パークに恐竜を供給するための施設サイトBがある島に恐竜がいるとの情報をハモンドは知り前回の失敗を繰り返さないために視察団を現地に派遣した。メンバーは、マルコム、その恋人で古生物学者のサラ、ビデオジャーナリストのニック・フィールド、装備専門家のエディ、そして、マルコムの娘ケリー。ルドローは、アメリカのサンディエゴの近くに恐竜動物園をつくる大計画のため恐竜を生け捕りにきていた。
恐竜の数、種類とも前回の「ジュラシック・パーク」以上に登場し、しかも、凶暴な肉食恐竜が多数現れるとあって迫力が増している。
特に今回は「ジュラシック・パーク」以上に多くのスピルバーグの恐怖感の演出を堪能できるのが魅力だ。冒頭で、島で少女が小さい肉食恐竜コンビに襲われるシーン。島に上陸して初めてステゴザウルスと遭遇するシーン。そのステゴザウルスは、カメラの巻き上げる音に反応してサラを襲う、サラが子供に触れると親が暴れだし、尾にあるトゲに刺されそうになる。ここの尾を振り回しサラを襲うシーンはすごい。ティラノサウルスの登場のさせ方。最初に足跡だけを見せておいて前作へのオマージュが感じられる地響きとともに水溜りが振動する。ティラノサウルスが動き出す姿を俯瞰撮影でジャングルの樹が揺れる様子を見せて表現している。川辺でキャンプした一行をティラノサウルスが襲う。サラのシャツに付いたティラノサウルスの赤ん坊の血の臭いに誘われてやって来た。テントで寝ているサラとケリーを襲う。テントに映るティラノサウルスの影に気つ゛いたサラは、灯りを消すがそれが一層恐怖を増す。サラが2頭のラプトルと格闘し屋根から落ちるシーン。最後には、サンディエゴにティラノサウルスが上陸し、街を破壊するシーンなど。
そして、なかでも彼の演出が冴えるのは、サムとニックがティラノサウルスの赤ん坊の傷の手当をしているときに子供を奪われた事を知った親が、トレーラーを襲うシーン。サラは、赤ん坊を親の元へ返してやるが怒りはおさまらずさらに襲う。このシーンのすごいこと。スピルバーグの「激突!」や「ジョーズ」を彷彿させる。ティラノサウルスは、トレーラーを崖から落とそうとする。後部車両が宙ずりになる。真下には荒れ狂う波がある。樹上高く設置された避難用のカーゴから見ていたエディは、ケリーをカーゴに残しトレーラーの救出に行く。エディがロープを投げたがティラノサウルスに食われてしまう。一方のサラとニックは、手の重みでガラス窓にひびがめきめきと入り海へ落下する危険がせまる。
さらに、後半部分の草原のハンターたちをラプトルが襲う。ここも俯瞰撮影で草の揺れる動きとラプトルが通った痕跡を映す。ラプトルは、低い姿勢でハンターたちから見えないように隠れて背後からあるいは正面から跳びかかりハンターたちを食べる。本部地区通信センターでのシーン。ラプトルが迫ってきた。マルコムは、サラとケリーを屋内に逃がす。1人ラプトルと対決する。車に逃げ込むマルコムを襲うラプトル。特に助手席側にある窓ガラスをラプトルがぶち壊し、運転席にいるマルコムを襲うところは、「宇宙戦争」でも似たシーンがある。スピルバーグは、このカメラワークが好きなのだろう。一方、サラとケリーも屋内でラプトルに狙われる。しかし、ケリーがここで大活躍をする。学校で器械体操の賞を取ったほどの腕前を発揮する。鉄棒にぶらさがり回転してキックしてラプトルを倒す。ここは、伏線が張ってあり冒頭の方で父マルコムとの会話の中でこのエピソードが出てくる。
この時期は、スピルバーグにとって3年間の充電期間だった。3年間も映画を撮らなかったのは過去を振り返っても無い。前作の「シンドラーのリスト」が彼の精神に多大な影響を与えたのだろう。監督復帰作が、エンターティメント性の強いアクション・パニック映画のジャンルになったのは、何とも彼らしいし、ファンとしては嬉しい限りだ。
スピルバーグ監督作品の中でも一番カメラが生き物のように激しく動き回り彼の映像テクニックを存分に楽しめる映画。それもそのはず彼が得意とするジャンルの映画だからである。












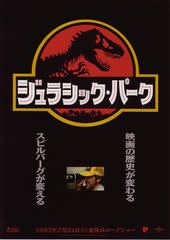
 「E.T」の興業成績を塗り替え、特にC・Gの素晴らしさが話題になった。それもそのはず
「E.T」の興業成績を塗り替え、特にC・Gの素晴らしさが話題になった。それもそのはず






 「トワイライトゾーン
「トワイライトゾーン