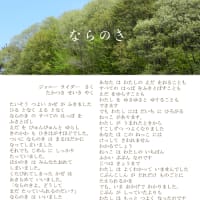私は長いあいだ詩を訳すというのは無理だと思って来た。私たちの世代はビートルズ世代だから、当時のアメリカのフォークソングなどをよく歌った。歌詞の意味を知ろうと思って辞書を引いた。ただ、意味はわかっても、それを日本語にしよとは思わなかった。それは「英語のほうがかっこいいから」というだけでなく、歌のもつ大きな要素である、ことばの響きが死んでしまうからである。
サイモンとガーファンクルの「スカボロフェア」という歌がある。歌詞と歌詞のあいだに背景のように「パセリ、セージ、ローズマリー、タイム」と香辛料の名前が入る。当時はこういうハーブ類もなく、なんのことだかわからなかったが、なんとなく響きがいいと思った。
香辛料の名前を訳しても、意味がわかっても、歌の魅力は伝わらない。そもそも食文化が違うのだから、こうした香辛料の名前を聞いて、味や匂いを連想することが、「スカボロフェアに行くところなのかい?」という歌詞とメルティングして歌になるのだろう。醤油と味噌の食体系に生きるわれわれにはその気分はわからないに違いない。
だから詩を訳すなんて乱暴なことだと思って来た。
でも、The Oak Treeを読んだとき、どうしても訳したいと思った。葉を失い、枝を折られ、樹皮さえ剥がされたナラの木はどうなるのだろうと思っていると、根には触らせないぞと意地をみせ、最後に感謝までして完全に風を打ちのめす。そのことが東北の人のみせる強さとやさしさと重なって、こみあげるものがあった。そして、うまく訳せなくても、その心は伝わるような気がした。
不思議な体験だった。