
奈良組の皆さんを中心とした見学会に初めて参加させてもらった。
「鎌倉新仏教・庶民信仰と浜の世界」(中世の祈りの世界)と題して、鎌倉駅の東南(本覚寺・比企ヶ谷の妙本寺・安国論寺・補陀洛寺・そして光明寺・元八幡)を材木座海岸方面に満開の桜を見ながら、鶴見大学文化財学科の福田先生の案内で歩いたのであります。
 (幹事さんの手製の地図・赤い矢印にそって見学したのです)
(幹事さんの手製の地図・赤い矢印にそって見学したのです)
 (本覚寺)
(本覚寺)
本覚寺のあるこの場所は幕府の裏鬼門にあたり、頼朝が鎮守として夷堂(えびすどう)を建てた所といわれている。この夷堂を日蓮が佐渡配流を許されて鎌倉に戻り布教を再開した際に住まいしたと伝えられている。その後鎌倉公方・足利持氏がこの地に寺を建て、寄進したのが本覚寺であるといい、二代目住職の日朝(にっちょう)が身延山から日蓮の骨を分けたので「東身延」と呼ばれている。(鎌倉市の説明板による)
 (妙本寺総門)
(妙本寺総門)
この寺一帯の谷を比企谷(ひきがやつ)といい、頼朝の重臣・比企能員(ひきよしかづ)らの屋敷があった。比企一族は二代将軍・頼家の後継者争いの際、北条氏を中心とした軍勢にこの地で滅ぼされた(比企の乱)。その後乱から逃れていた、末子の能本(よしもと)が日蓮聖人に帰依し、一族の屋敷跡であるこの地に法華堂を建てた。これが妙本寺の始まりといわれている。(鎌倉市の説明板による)
 (妙本寺総門にある比企能員館跡の碑)
(妙本寺総門にある比企能員館跡の碑)
源頼家の妻「若狭局」は比企能員の娘であり、源頼朝の乳母であった比企局は、この能員の伯母である。正治元年(1199)頼朝が急死し、幕府の実権は北条時政・政子親子にあった。若狭局に嫡男が産まれ、北条と比企との対立に発展していった。この「比企の乱」では歴史の変わり目を表しているのである。(ここで書くと長くなるので割愛する)
 (日蓮の御法窟)
(日蓮の御法窟)
松葉ヶ谷(まつばがやつ)にある安国論寺は、日蓮上人安房国から鎌倉に入り初めて庵を結んだ場所である。この石碑の後に『立正安国論』を執筆した洞窟「御法窟」が日蓮上人遺跡として史跡保存されている。
お昼は材木座海岸の砂浜でトンビに狙われないように皆で食べました。


鎌倉の材木座海岸の逗子よりの海岸は、「和賀江嶋」といい遠浅のため北条泰時の許可を得て往阿弥陀仏が石で嶋を築き、鎌倉の海上交通の拠点とした。現存するわが国最古の築港跡である。
 (光明寺山門)
(光明寺山門)
法然上人を祭った浄土宗天照山光明寺は、13世紀第四代執権北条経時の創建・山門は江戸時代の建築で間口16m、高さ20mで鎌倉の寺院の門では最大の格式を備えている。
 (山門の上からは鎌倉の海が見渡せる)
(山門の上からは鎌倉の海が見渡せる) (伝小堀遠州作の庭園)
(伝小堀遠州作の庭園)
 (参道工事で平成2年に発見された大鳥居の遺構)
(参道工事で平成2年に発見された大鳥居の遺構)
帰りは若宮大路の「浜の大鳥居跡」を見学して、鎌倉の庶民信仰を考えながら「湘南新宿ライン」で帰りました。
奈良組の幹事さん大変な盛況でありがとうございました。














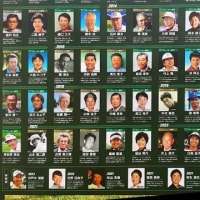











※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます