信州上田・・・稲倉の棚田の古墳に関連して・・・
彩の国吉見町にある古墳時代末期の横穴式墓群「吉見の百穴」(ひゃくあな)です。
※江戸時代の文献にも「吉見の百穴」が出てくるそうです。「ひゃくあな」か「ひゃっけつ」か・・・どうでもいいことですが地元の人は古くから「ひゃくあな」といってるそうです。
※弥生式土器の発見で有名な坪井正五郎博士が東京帝国大学の大学院生のころ地元の人の協力を得て1887年発掘調査、237の横穴を露頭させたといわれますが詳細な記録・写真が無いようです。坪井博士はこの横穴をコロボックル(アイヌ伝承に出てくる小人)の居住跡という説を発表、何とも幻想的でロマンあふれる説でしたが、この説は論議を呼び、大正時代の中ごろに横穴式墓群というのが定説になりました。1923年国指定史跡。
※大和王朝時代の600年前後から藤原京時代の700年前後までに造られたと推定されています。前方後円墳、円墳、方墳が姿を消した古墳時代の終り頃。このあたりの河岸段丘地は凝灰岩質砂岩が多く掘削が容易であるのが造られた理由であろうか。
※誰がこの方式を導入したのであろうか、大陸からの渡来人か、被葬者はどんな人たちか。謎は深まる。
彩の国吉見町にある古墳時代末期の横穴式墓群「吉見の百穴」(ひゃくあな)です。
埼玉県東松山市と吉見町の境界を流れる荒川水系市野川、その左岸の吉見町北吉見地籍。
市野川の河岸段丘、凝灰岩質砂岩が露頭した崖地に不思議な横穴が・・・現在219穴。

幻想的な風景・・・コカコーラやソフトクリームの看板が無ければ・・・
空色のベストのかたはボランティアガイドさんかな?

中央に墓穴よりひと回り大きい洞窟があります。戦時中に掘削された軍事工場跡です・・・その話は後程。
市野川の河岸段丘、凝灰岩質砂岩が露頭した崖地に不思議な横穴が・・・現在219穴。

幻想的な風景・・・コカコーラやソフトクリームの看板が無ければ・・・
空色のベストのかたはボランティアガイドさんかな?

中央に墓穴よりひと回り大きい洞窟があります。戦時中に掘削された軍事工場跡です・・・その話は後程。
※撮影日は10月24日、LUMIX DMC-G7。
※江戸時代の文献にも「吉見の百穴」が出てくるそうです。「ひゃくあな」か「ひゃっけつ」か・・・どうでもいいことですが地元の人は古くから「ひゃくあな」といってるそうです。
※弥生式土器の発見で有名な坪井正五郎博士が東京帝国大学の大学院生のころ地元の人の協力を得て1887年発掘調査、237の横穴を露頭させたといわれますが詳細な記録・写真が無いようです。坪井博士はこの横穴をコロボックル(アイヌ伝承に出てくる小人)の居住跡という説を発表、何とも幻想的でロマンあふれる説でしたが、この説は論議を呼び、大正時代の中ごろに横穴式墓群というのが定説になりました。1923年国指定史跡。
※大和王朝時代の600年前後から藤原京時代の700年前後までに造られたと推定されています。前方後円墳、円墳、方墳が姿を消した古墳時代の終り頃。このあたりの河岸段丘地は凝灰岩質砂岩が多く掘削が容易であるのが造られた理由であろうか。
※誰がこの方式を導入したのであろうか、大陸からの渡来人か、被葬者はどんな人たちか。謎は深まる。
※東京帝国大学の学生であった正岡子規が1891年11月、蕨、忍、熊谷、東松山、川越、所沢、田無と2泊3日の「武蔵野旅行」をした際、吉見百穴を尋ねています。
神の代は かくやありけん 冬籠 子規























 1333年、上野国新田庄で討幕の旗を挙げた新田義貞が鎌倉目指して進軍したのがこの鎌倉街道上ツ道。みごとに鎌倉幕府壊滅の立役者に。
1333年、上野国新田庄で討幕の旗を挙げた新田義貞が鎌倉目指して進軍したのがこの鎌倉街道上ツ道。みごとに鎌倉幕府壊滅の立役者に。


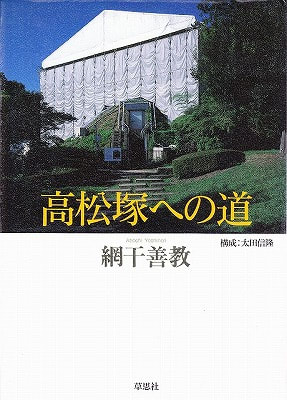 2004年に訪れた明日香村の「石舞台」古墳です。
2004年に訪れた明日香村の「石舞台」古墳です。 京都に泊り近鉄奈良線で「飛鳥駅」に、駅前のレンタサイクルで明日香村をブラリブラリ・・・
京都に泊り近鉄奈良線で「飛鳥駅」に、駅前のレンタサイクルで明日香村をブラリブラリ・・・





 ※尖石遺跡・・・1893年、明治時代に学会に発表されていた。1929年石囲炉跡発掘、1940年本格的な発掘開始、戦争の中断があったが1954年まで発掘。1952年国指定特別史跡に。竪穴式住居33ヶ所、石囲炉53、石斧46ほか出土。
※尖石遺跡・・・1893年、明治時代に学会に発表されていた。1929年石囲炉跡発掘、1940年本格的な発掘開始、戦争の中断があったが1954年まで発掘。1952年国指定特別史跡に。竪穴式住居33ヶ所、石囲炉53、石斧46ほか出土。



 「埼玉県」・・・どうしてそう呼ばれるか?・・・1971年(明治4年)、廃藩置県、いま埼玉というあたりは入間県、埼玉県と呼べと政府のお達しが出た。それから1976年埼玉県に統一。
「埼玉県」・・・どうしてそう呼ばれるか?・・・1971年(明治4年)、廃藩置県、いま埼玉というあたりは入間県、埼玉県と呼べと政府のお達しが出た。それから1976年埼玉県に統一。
 稲荷山古墳・・・前方後円墳、軸長120m、高さ11.7m、5世紀後半。1968年金錯(金の象嵌)銘鉄剣、帯金具、まが玉、鏡など出土、1978年X線により115文字を解読。1983年国宝指定。窒素ガス封入の下で管理。
稲荷山古墳・・・前方後円墳、軸長120m、高さ11.7m、5世紀後半。1968年金錯(金の象嵌)銘鉄剣、帯金具、まが玉、鏡など出土、1978年X線により115文字を解読。1983年国宝指定。窒素ガス封入の下で管理。






