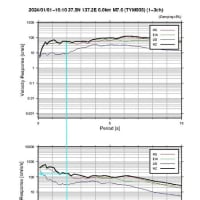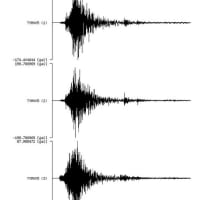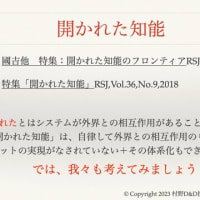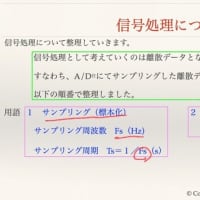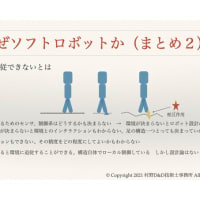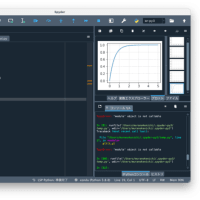3 過渡応答解析
過渡応答解析の目的は、システムの特性を時間軸で見ることである。
はじめにステップ応答について見てみる。
scilabでは過渡応答はcsimで簡単にできる。パラメータを’step’と指定するとステップ応答となる。
->t=0:0.05:5;
-->s=poly(0,'s');
-→S1=(2*s+10)/(s^2+2*s+10);
-->plot2d([t',t'],[(csim('step',t,tf2ss(S1)))',0*t'])
警告: csim: 入力引数 #1 は連続時間系で指定してください.
あれ、警告だ。ちょっと例題どおりなのに(ヘルプの)
今度調べます。
さて伝達関数は尾形先生の例題3−1のバネマスダッシュポット系です。

2次系のステップ応答の典型ですね。グラフのテクニックは別途勉強が必要ですね
過渡応答解析の目的は、システムの特性を時間軸で見ることである。
はじめにステップ応答について見てみる。
scilabでは過渡応答はcsimで簡単にできる。パラメータを’step’と指定するとステップ応答となる。
->t=0:0.05:5;
-->s=poly(0,'s');
-→S1=(2*s+10)/(s^2+2*s+10);
-->plot2d([t',t'],[(csim('step',t,tf2ss(S1)))',0*t'])
警告: csim: 入力引数 #1 は連続時間系で指定してください.
あれ、警告だ。ちょっと例題どおりなのに(ヘルプの)
今度調べます。
さて伝達関数は尾形先生の例題3−1のバネマスダッシュポット系です。

2次系のステップ応答の典型ですね。グラフのテクニックは別途勉強が必要ですね