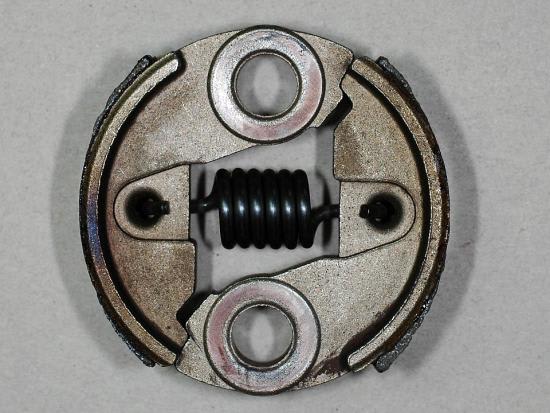親方より刈り払い機の吊り位置が良くないとの指摘を受け、メインの2711の吊り位置を
今までより5Cm程前に出し、それに合わせてハンドル位置も修正したら取り回しが楽に成りました。
まだまだセッティングの余地はありそうですが、とりあえず今の状態で様子見。
それに合わせて予備機のブラケット等の位置を合わせる為にブラケット周りの整備や
改良及び修理の紹介など。

☆予備機
予備機はBC2711G-DW TKキャブ仕様
TKキャブはバイク等に使われているピストンバルブ式キャブレターでテイケイ気化器株式会社
と言うメーカーが作っているキャブレター。
メイン機のロータリーキャブ仕様と比べるとアクセルレスポンスは良いが燃費が悪いという感じ。
アクセルレスポンスについては使い方次第で気になりませんが、
燃費の差は1日使って0.5リットル位有りそう。
60日使って30リットルの差になるので小さな差ではありません。

☆エンジン側ブラケット
写真の矢印の所はエンジンとパイプの位置決めのねじ穴。
パイプ側に穴が開いており、何も力が掛かる所ではないのできつく締める必要は無く
緩まないだけ締めればよいのですが、何度も脱着を繰り返すうちにネジ山が舐めてしまいました。
アルミは鉄より柔らかいので締め付けトルクは小さいのですが、ついつい締めすぎてしまいます。
舐めてしまった物は交換するしかないのですが、ヘリサートを入れて対処。
アルミに小径のヘリサートを入れるのは難しく、ある程度の慣れが必要です。


☆折れて修理したハンドル
村人の現場は伐根でキックバックを食らう事が良くあり、状況により左ハンドルがお腹に当たり
それを繰り返す事である日突然ハンドルが折れたり。
そんな時は慌てずハンドルブラケットを緩めて折れた部分をブラケットの真ん中に移動して対処。
その為六角レンチは常に携行しています。
2711のハンドルはかなり厚手なのですが折れます。
注:修理後のハンドルは修理部分がブラケットの中に入る様少し右にシフトして取り付け。
下の写真は4410の折れたハンドルで、こちらはセパレーツなので折れた部分を取り除いて
そのまま使えます。
2711のハンドルは一体型ですがパイプは同じ物。
内径が13mmなので13φの鉄パイプとエポキシ接着剤で修理できます。


☆ハンドルブラケットとネジ
プロユーザーは雨天でも仕事をするのでネジ部に水が入って錆びる事もあります。
写真はピンぼけですがブラケット右下のネジ部が錆びています。
ボルトも1本だけ錆がひどいのが分かるでしょう。
こんなボルトはワイヤーブラシでしっかり錆を落としましょう。
ボルト穴の方はケースバイケースでタップを通す事もあります。
その後さび止めと潤滑を兼ねて特殊なグリースを塗布して組み立て。

☆Hot bolt paste
このグリースは車のエキゾースト周りのボルトナットの固着を防止する物で、
ちょっと特殊なので一般の方が手に入れられるかは分かりません。
手に入れられるとしたらワーゲン・アウディの部品課からでしょう。
成分は亜鉛が配合されていると想像しますが詳細は不明。
私はアルミに鉄ボルトの部分に固着防止と潤滑を兼ねてこれを使っています。

☆アクセルワイヤー周り
刈り払い機はアクセルワイヤーが引っ張られた時、キャブレター側アウターが
アジャスターに乗り上げてアクセルが開きっぱなしになる事があります。
対策としてエアコンプレッサーのホースを短く切って被せるだけ。

☆BCZ270(現行機種はBCZ271)
その対策としてBCZ270では抜け止め対策のされたワイヤーに仕様変更されたようです。

☆アクセルレバー
2711は2台とも輸出仕様のアクセルに交換。
村人はトリッガーレバーのアクセルしか使いません。
理由はキックバックをおこした時にアクセルが開きっぱなしが怖から。
トリッガーレバー式でも慣れればどんなにブンブン振ってもアクセル一定で使う事が出来、
状況に応じての微調整は固定スロットルより楽かと思います。
一つデメリットがあるとすれば右手をずらしての仕事が出来ず、右上がりの急斜面等では
ちょっと辛いです。

☆色々なアクセルレバー
写真右下が日本仕様のオリジナルトリッガーレバー。
2711及び4410は同じ物で、キルスイッチはエンジン本体に付いているのが使いづらい。
左は旧型固定スロットルレバー。
右上は海外向けの仕様で、キルスイッチが手元にあります。
海外ではキルスイッチを手元に付けないと販売出来ないなどの規定がある物と想像します。
スチールの旧製品にも同じ物が使われている物が有るそうで、そちらはワイヤー付きでしか
出ないので割高だそうです。
このアクセルレバーはワイヤーのアウターに当たる部分が細く、アクセルレバーが定位置から
回るとポッキリ折れるので要注意。
いずれのモデルもアクセルワイヤーの取り出しやハンドルへの取り付け部分が違うので
そのままポンと付け替えという訳には行きません。
交換にはある程度の技量が必要となるので自己責任で!