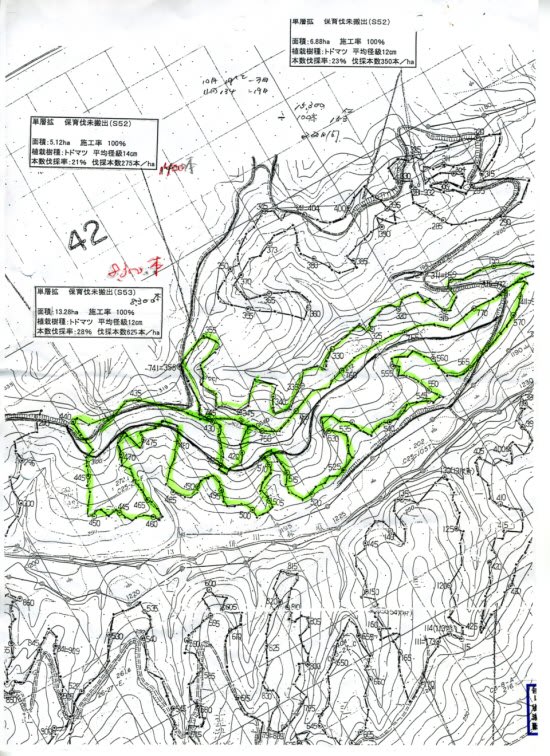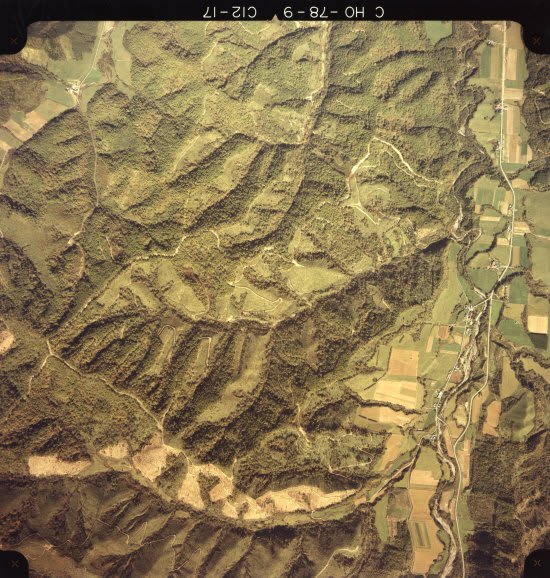私は2014年5月末を持って紋別郡西興部の北海緑化を退職しており、もう雇用関係という弱みも無いので労災保険の話をしたいと思います。
通常ならこんな話をすればもう会社に使ってもらえなくなるのでタブーな話でしょう。
私も在職中は労災保険に対して無知でどんな規定があるのか知りませんでした。
林業に限った事ではないと思うのですが、経営者は労災保険を使う事をとても嫌っているようです。私は経営者サイドの事情が分かりませんが軽微な事でも労災保険を使うとペナルティを課せられるのでしょうか。
死亡事故や重大な事故を起こした時には道有林の仕事を回してもらえなくなるとかが有るようです。
労災保険の適用範囲は通勤災害も含めて業務中の災害で病院に行った場合は全て労災保険を使うべきらしいです。
村の診療所には「労災隠しは犯罪です」という様なポスターが貼ってありました。
しかし実情は大きな事故以外で労災保険を使った事はありませんでした。
村の診療所の場合は労災保険を使うべきケースだと分かっているのかどうかは知りませんが、どんな場合でも何も質問されることなく社会保険での診療を受ける事が出来ます。
地ごしらえで負傷して一週間休んだ時が何度か有りますが社会保険で診療しております。
スズメバチに3カ所刺され、その晩は39度の発熱があり死にそうな思いをして一週間休んだ時も社会保険での診療でした。
労災保険の規定には「業務上災害については、労働基準法に、使用者が療養補償その他の補償をしなければならないと定められています。」と有る様で、当然蜂刺されも労災の対象でした。
休業(補償)給付の規定には「業務災害又は通勤災害による傷病に係る療養のため労働することができず、賃金を受けられない日が4日以上に及ぶ場合」とある様なので一週間休んだ場合は休業補償も受けられた筈です。
労災保険に無知だったので、この辺りの事は今回調べて初めて知りました。
しかし、労災保険が使えるケースだとしても、労災にして休業補償を受けるともう会社に使ってもらえなくなると言う雇用関係の弱みが有ります。
だから業務上の怪我も数ヶ月休業する様なケースでなければ会社は労災保険は使わせないでしょう。
林業はいくら気をつけていても怪我をするのは当たり前の世界。
ましてや蜂刺され等は刺されるまで気がつかないので日常茶飯事。
そんな世界なので、林業では重大事故以外では面倒な手続きやペナルティ等を無くして、
もっと気軽に労災保険が使えるようにするべきだと思います。
さらなる話は裏ブログに続く。