~~引用ここから~~
来月、定年となる東京高等検察庁の黒川弘務検事長の勤務が、ことし8月まで延長されることになりました。
検察官の定年は、検察庁法で検事総長は65歳、それ以外は63歳となっていて、東京高等検察庁の黒川検事長は、来月8日に63歳となり定年を迎えます。
これを前に政府は31日の閣議で、黒川検事長の勤務を国家公務員法の規定に基づいて、ことし8月まで延長することを決めました。
森法務大臣は記者団に対し「検察庁の業務遂行上の必要性にもとづいて、黒川検事長を引き続き勤務させることを決定した」と述べました。
検事長の勤務延長は極めて異例で、稲田伸夫検事総長の後任にするための措置ではないかという見方も出ています。
官房長官「人事プロセスの詳細控える」
菅官房長官は、午後の記者会見で「検察庁の業務遂行上の必要性に基づき、検察庁を所管する法務大臣から総理大臣宛に閣議請議があり、きょう決定されたものだ。人事のプロセスの詳細は差し控えたい」と述べました。
また、記者団が「官房長官の推薦はあったのか」と質問したのに対し、菅官房長官は「法務省からの請議によって閣議決定を行ったということだ」と述べました。
~~引用ここまで~~
官僚人事を官僚任せにして政治が介入しないことが「中立・公正」だとは思わない。それは官僚は善で政治家が悪と言わんばかりではないか。
大東亜戦争に負けて破滅した一因に軍部任せの政治がある。軍人官僚は民主的に選ばれた政治家ではない。昭和恐慌に対応できず、民選政治家が、政党政治が国民に愛想を尽かされたことがそれ以前の歴史として存在するが。
検察官は半独立した存在として政権や政治家にも睨みを効かせるべきだとする考えもあるが、所詮検察庁は行政の一機関に過ぎないのである。政権内部に切り込むことはない。
マスコミが持ち出すのはロッキード事件で田中角栄を逮捕したことだが、それは「東京地方検察庁特別捜査部」が米国の支配下にあったからだ。
田中角栄は資源ナショナリズムから資源調達に関して米国からの「独立」を目論んでいた。米国には邪魔な存在だったのだ。だから逮捕された。
アフガニスタンにも政治家や政府高官を捜査する部署がある。米国がアフガニスタン政府を傀儡とするために設置したのだ。米国はそのようなやり方を好むようだ。
田中角栄のロッキード裁判は証人に対する反対尋問さえされず、当時は「司法取引」が制定されていないのに超法規的措置で司法取引まで行った。本来刑事裁判ではそのようなものは証拠能力を持たないのだ。
だが左翼マスコミはロッキード裁判が異常な裁判であったことに触れない。御用マスコミもだが。「正義の検察庁が悪の政治家を逮捕起訴した構図」でしか報道しないのだ。無邪気なものだ。
だから今回の黒川弘務東京高検検事長が特例で定年を延長され、検事総長就任への道を開いたことに「政治介入」と批判するつもりはない。政治が介入して何が悪いのだ。慣例も法ではない。
法律は改正できるが、慣例は改正できないではないか。慣例に過ぎないものが絶対的価値を持つのはおかしい。
だが、だからといって安倍晋三の政治介入を肯定的に見ているわけではない。
検察庁は安倍晋三の玩具ではない。安倍晋三の「お友達」の官僚を検事総長に就任させようとすることが非難されるべきなのだ。
米国は閣僚と高級官僚の人事権は大統領にある。「回転ドア」と呼ばれる方式で大統領が代わるごとに閣僚と高級官僚がごっそり入れ替わるのだ。そのポストは4000にも及ぶとされる。
まああまりにも好き放題にはできず、共和党系、民主党系の人材をそれぞれ採用する。官僚方式なのは軍隊くらいだろう。いやFBIやCIAなども上から数人を任命するだけである程度はその組織任せかもしれない。
米国は民間企業もそうだが、トップとの相性がものを言う世界だからだ。
だが日本は違うはずだ。民間企業もそうだが、トップとの相性で人事は決めない。派閥論理や論功行賞はざらにあるが。
高級官僚人事の法律的な権限は担当大臣にあるのか、内閣人事局にあるのか、内閣総理大臣にあるのか今一つ不明確だが、政府にある。
だが黒川弘務東京高検検事長の定年延長を決めたのは明らかに安倍晋三だ。批判が高まれば止めるかもしれないが、検事総長に就任させる腹積もりだろう。
しかもそれを自分が責任を持って「余人に持って代えがたい人物だから定年を延長した」と明言すればまだ良いものを法相に丸投げだ。だから安倍晋三は嫌なのだ。自分は責任を負わない。手を汚さない。やり方が汚い。
あまりにも政府方針に逆らう官僚は更迭するしかないが、基本的には実力で決めるべきだと思う。「人」の客観的な能力は傍目にはわからないから、「実力」と称しても内閣総理大臣や主流派官僚に都合の良い人事が行われることはざらなのだが。
検事総長は任期2年で警察庁長官も2年だ。国税庁長官に至っては1年しかない。前統合幕僚長である河野克俊は3度も定年延長されたが、基本的には2年の任期だ(定年が62歳)。
官僚は必ずしも喜ばないだろうが、1期2年の2期4年の任期にしてはどうだろうか。検事総長、警察庁長官、国税庁長官、統合幕僚長(統合参謀本部総長に改名したい)は1期2年の2期4年とする。
特段の不祥事がなければ4年間任せるのだから次長級から昇格させるのではなく局長級から昇格させてはどうか。警察庁警備局長から警察庁長官にというように。それには別段こだわらないが。
任期が2倍になるということはトップに就任する官僚が半分になるということだ。だから官僚は喜ばないかもしれないが、日本の官僚機構はもっとトップが権限を握っても良いように思うのだ。
検察であれ、財務省であれ、最高裁判事であれ人事に政治が介入することが悪いわけではない。内閣総理大臣が自分の「お友達」を任命することが悪いのだ。
だから今回の黒川弘務東京高検検事長の定年延長と将来の検事総長就任には断固反対する。まあ日本の片隅からブログで反対しても変わらないかもしれないが。
来月、定年となる東京高等検察庁の黒川弘務検事長の勤務が、ことし8月まで延長されることになりました。
検察官の定年は、検察庁法で検事総長は65歳、それ以外は63歳となっていて、東京高等検察庁の黒川検事長は、来月8日に63歳となり定年を迎えます。
これを前に政府は31日の閣議で、黒川検事長の勤務を国家公務員法の規定に基づいて、ことし8月まで延長することを決めました。
森法務大臣は記者団に対し「検察庁の業務遂行上の必要性にもとづいて、黒川検事長を引き続き勤務させることを決定した」と述べました。
検事長の勤務延長は極めて異例で、稲田伸夫検事総長の後任にするための措置ではないかという見方も出ています。
官房長官「人事プロセスの詳細控える」
菅官房長官は、午後の記者会見で「検察庁の業務遂行上の必要性に基づき、検察庁を所管する法務大臣から総理大臣宛に閣議請議があり、きょう決定されたものだ。人事のプロセスの詳細は差し控えたい」と述べました。
また、記者団が「官房長官の推薦はあったのか」と質問したのに対し、菅官房長官は「法務省からの請議によって閣議決定を行ったということだ」と述べました。
~~引用ここまで~~
官僚人事を官僚任せにして政治が介入しないことが「中立・公正」だとは思わない。それは官僚は善で政治家が悪と言わんばかりではないか。
大東亜戦争に負けて破滅した一因に軍部任せの政治がある。軍人官僚は民主的に選ばれた政治家ではない。昭和恐慌に対応できず、民選政治家が、政党政治が国民に愛想を尽かされたことがそれ以前の歴史として存在するが。
検察官は半独立した存在として政権や政治家にも睨みを効かせるべきだとする考えもあるが、所詮検察庁は行政の一機関に過ぎないのである。政権内部に切り込むことはない。
マスコミが持ち出すのはロッキード事件で田中角栄を逮捕したことだが、それは「東京地方検察庁特別捜査部」が米国の支配下にあったからだ。
田中角栄は資源ナショナリズムから資源調達に関して米国からの「独立」を目論んでいた。米国には邪魔な存在だったのだ。だから逮捕された。
アフガニスタンにも政治家や政府高官を捜査する部署がある。米国がアフガニスタン政府を傀儡とするために設置したのだ。米国はそのようなやり方を好むようだ。
田中角栄のロッキード裁判は証人に対する反対尋問さえされず、当時は「司法取引」が制定されていないのに超法規的措置で司法取引まで行った。本来刑事裁判ではそのようなものは証拠能力を持たないのだ。
だが左翼マスコミはロッキード裁判が異常な裁判であったことに触れない。御用マスコミもだが。「正義の検察庁が悪の政治家を逮捕起訴した構図」でしか報道しないのだ。無邪気なものだ。
だから今回の黒川弘務東京高検検事長が特例で定年を延長され、検事総長就任への道を開いたことに「政治介入」と批判するつもりはない。政治が介入して何が悪いのだ。慣例も法ではない。
法律は改正できるが、慣例は改正できないではないか。慣例に過ぎないものが絶対的価値を持つのはおかしい。
だが、だからといって安倍晋三の政治介入を肯定的に見ているわけではない。
検察庁は安倍晋三の玩具ではない。安倍晋三の「お友達」の官僚を検事総長に就任させようとすることが非難されるべきなのだ。
米国は閣僚と高級官僚の人事権は大統領にある。「回転ドア」と呼ばれる方式で大統領が代わるごとに閣僚と高級官僚がごっそり入れ替わるのだ。そのポストは4000にも及ぶとされる。
まああまりにも好き放題にはできず、共和党系、民主党系の人材をそれぞれ採用する。官僚方式なのは軍隊くらいだろう。いやFBIやCIAなども上から数人を任命するだけである程度はその組織任せかもしれない。
米国は民間企業もそうだが、トップとの相性がものを言う世界だからだ。
だが日本は違うはずだ。民間企業もそうだが、トップとの相性で人事は決めない。派閥論理や論功行賞はざらにあるが。
高級官僚人事の法律的な権限は担当大臣にあるのか、内閣人事局にあるのか、内閣総理大臣にあるのか今一つ不明確だが、政府にある。
だが黒川弘務東京高検検事長の定年延長を決めたのは明らかに安倍晋三だ。批判が高まれば止めるかもしれないが、検事総長に就任させる腹積もりだろう。
しかもそれを自分が責任を持って「余人に持って代えがたい人物だから定年を延長した」と明言すればまだ良いものを法相に丸投げだ。だから安倍晋三は嫌なのだ。自分は責任を負わない。手を汚さない。やり方が汚い。
あまりにも政府方針に逆らう官僚は更迭するしかないが、基本的には実力で決めるべきだと思う。「人」の客観的な能力は傍目にはわからないから、「実力」と称しても内閣総理大臣や主流派官僚に都合の良い人事が行われることはざらなのだが。
検事総長は任期2年で警察庁長官も2年だ。国税庁長官に至っては1年しかない。前統合幕僚長である河野克俊は3度も定年延長されたが、基本的には2年の任期だ(定年が62歳)。
官僚は必ずしも喜ばないだろうが、1期2年の2期4年の任期にしてはどうだろうか。検事総長、警察庁長官、国税庁長官、統合幕僚長(統合参謀本部総長に改名したい)は1期2年の2期4年とする。
特段の不祥事がなければ4年間任せるのだから次長級から昇格させるのではなく局長級から昇格させてはどうか。警察庁警備局長から警察庁長官にというように。それには別段こだわらないが。
任期が2倍になるということはトップに就任する官僚が半分になるということだ。だから官僚は喜ばないかもしれないが、日本の官僚機構はもっとトップが権限を握っても良いように思うのだ。
検察であれ、財務省であれ、最高裁判事であれ人事に政治が介入することが悪いわけではない。内閣総理大臣が自分の「お友達」を任命することが悪いのだ。
だから今回の黒川弘務東京高検検事長の定年延長と将来の検事総長就任には断固反対する。まあ日本の片隅からブログで反対しても変わらないかもしれないが。











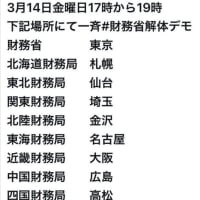









須田氏の社会の闇のコーナーで今回の件を詳しく詳解されていました。検事長と次官との上下位置関係、今回の措置が無かった場合朝日新聞シンパの林名古屋検事長が検事総長になる可能性の大きいことなど。。
今回の措置に対して朝日新聞が激怒して風評を大きくし国民の多くが知ることになったことなど。背景が良く理解できました。
朝日新聞の主張の反対を実践することが日本の国益であることから鑑みると今回の措置は正に正しい判断と認識せざるを得ないと思いました。
私はジャーナリストではありませんし、官僚組織にも精通していませんので、公開情報、マスコミ報道にネット検索程度の知識しかありません。
法務検察官僚首脳は林真琴名古屋高検検事長を早くから将来の検事総長候補と目していた一方、政治、官邸と法務大臣は林真琴名古屋高検検事長を忌避していたようですね。とくに上川陽子元法務大臣が林真琴名古屋高検検事長の法務省事務次官就任も拒絶したようです。上川陽子元法務大臣肝煎りの「国際仲裁センター」に招致に林真琴名古屋高検検事長が反対したから、とのこと。
私は検察が「政治の腐敗に睨みを効かせる正義の組織」と考えるほど若くはありません。政治が官僚人事に介入して慣例を崩すのも良いと考えています。ただ時の内閣総理大臣の「お友達」を抜擢することは悪いことだと考えているのです。
朝日新聞が反日極左の国賊であることは論を待ちませんが、その主張の反対なら国益ということはないでしょう。朝日新聞と犬猿の仲である安倍晋三が為したことで日本人の利益になったことはないからです。
消費税増税と緊縮財政で国民を痛めつけただけです。消費税増税の税収も社会保障の充実に使うわけではなく、法人税減税と債務返済に消えました。安倍晋三が推進したことは単純労働の外国人労働者の受け入れなど国民を苦しめるグローバリズムばかりです。
安倍晋三を批判するあまり黒川弘務東京高検検事長に辛くなってしまったかもしれませんが。