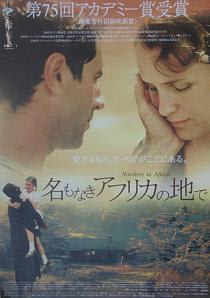いつも覗かせていただいている『はんなり・・・』で、
この映画をはんなさんが取り上げていらっしゃるのを読んでいて「!」。
見たいのに、見逃していたこの映画の一週間だけの
アンコール上映の情報が記事末尾にありました。
ちょっと無理しても、行って良かったぁ。
+ + +
東西ドイツの時代は、はや記憶から薄れつつありますが
後遺症のようなものを描いたドキュメンタリーTVを
みて、ショックを受けた事があります。
この映画の監督も母親が東ドイツ出身だったということで
幼少のころ、大人たちが感じていた恐怖はとても強い
印象として彼の中に残り、4年という年月を撮影前の
リサーチにかけたという、この映画の誠実な制作姿勢に
反映しているようです。
暗い映画・ツライ映画を覚悟していましたが、
酷い場面やある意味怖ろしいシーンはところどころ
あるものの、たんたんとストーリーが進む中にも
ところどころ日常的なユーモアが含まれていたり、
その後のストーリー展開への伏線があったり、
絵にかいたような悪役が出てきたり・・・引き込まれます。
名画と一緒で、無駄なひと筆がない感じ
セバスチャン・コッホとウルリッヒ・ミューエーはステキでした。
役とはいえ、困難を前にした時彼らのようにに冷静に
それでいて人間としての誠実さを失わず生きたいものです。
ウルリッヒ・ミューエー演じるヴィスラー大尉と
子供のツーショット、エレベーターのシーン、
(良かったなぁ。。。)
体制崩壊後、ラストシーンの最後の内面笑顔の無表情・・・
(あ~~思い出しても涙と鼻水が・・・。)
鼻をすすり上げる大泣きが、あちこちで聞こえましたが
他の人が同じものを観て共感し、なみだしていることを、
嬉しく感じた映画でした。
観た後にすがすがしさの残るステキなヒューマンドラマでした。
(クリスタは悲惨・あわれで、パンズ・ラビリンスの
母親を思い出しましたが。)