こんばんは。藤原です。
オープン稽古と題して、毎週月曜日に稽古をすることにした。
本日が第一回目。
4名の俳優さんが参加してくれました。ありがとうございました。
公演以外の時期に、色んな俳優さんと出会いながらクリエーションする時間を、定期的に設けたい、ということ、
ゲスト俳優さんを招いたときに、できるだけ座組の中で共有する言語や、方法を見出したい、というのが大きなモチベーション。
目下の稽古のテーマは、
『役としての身体感覚を探る』
イメージした環境や状況にリアクションする身体の変化、
それを豊かにするために、どんな言語化がありえるか、というのを俳優さんと探った。
●本日のシーン
舞台上に、Bがいる。シュチュエーションは、野外の大規模ライブ。
Aがやってくる。Bを見て、びっくりする。なぜなら、Bは、1年前に亡くなった、Aにとって大切な人と瓜二つだったのだ。
そこへ、Bと待ち合わせていたCがやってくる。BとCは和気藹々と話している。
その様子を見つめるA。
Cは、Aを見て、話しかける。AとCは、以前一度会ったことがあった。戸惑いながら話すA。
Cは、Aに、3人で一緒にライブを観よう、と誘う。そして、Cはトイレなどの理由で離席する。
AとB、2人になるーーー
改めて書いてみて、タスクの多いエチュードだな、というのと、
Aにフューチャーした筋書きなので、いつも一人の主人公を置いがちな自分の癖を省みるが、
とにかく、最初にこのエチュードをやってもらった。
その後、エアーのなわとび、エアーの棒遊びなどで一度身体をほぐしてから、
【カイジ】を。
ご存じだろうか。カイジのあの、名シーン。
『文句なく即死…っ!!!地上74メートル魔天の地獄……鉄骨渡り!!』
てな感じで、
ビルとビルの間にあるのは、一本の鉄骨。そこを渡る、というのを、
何もない空間で、イメージしてやってみる。高さをどうイメージするか、その緊張感を身体にどう持つか。
一歩目の出し方、そのあとの緊張の維持の仕方、足を出す時と、止まっているときの違い、
風を感じるか。向こう側(安全な場所)に近づいていくことでの緊張感の変化、など、
テンションをずっと張っていないといけないので疲れるが、全身を使ってできるので、
このワークはよくやるワークだ。
一人一人やってもらって、どう見えるか、をフィードバックした。
「高いところをイメージしたらできた」と言ってしまえば身も蓋もないのだけれど、
一回目、二回目と試して、二回目でより高さが出た俳優さんに、どう変化したか、きっかけになる言葉を聞いたら、
「なんかこう、すわぁっとする感じ。」と、身振りを交えて答えてくれた。
「すわぁ」という言葉は、下から何かが上がってくるイメージだ。
実際には床面だけれども、床面のもっともっと下のところから、“風を感じる”というのは、高さに具体的に近づくヒントになる。
一回目、二回目で、二回目の方が緊張感がうすれた俳優さんに、一回目と二回目の体感の違いを尋ねる。
「一回目は外をイメージできていたのに、二回目は、高さをイメージしようとしたらうまくいかなくなって、室内にいるみたいなイメージになってしまって、全然うまくいかなかった」と言っていた。
動きはほとんど変わらないが、外からもまったくそのように見えた。
タスクをこなそうとしてしまうと、とたんに身体は閉じる。
身体をイメージに開いておかなくてはいけない、それは、集中する宛先を、自分以外に向ける、ということか、
と思うけれども、自分以外に集中を向ける、というのを意識しすぎても、結局自分に意識が向いてしまうことになるので、
このあたりはどう言語化すればいいか。
●空間の変化
空間のイメージが変化すると、身体がどう変化するか、のワーク。
これもよくやるワークだ。
部屋の中を4人で自由に歩いてもらう。
1,2,3,4,5,とカウントをして、5までいくと、部屋の温度が、高温サウナ風呂まで高温になる。
−1,−2,−3,−4,−5、とカウントして、−5までいくと、部屋の温度が、冷凍庫ぐらいまで低温になる。
温度の変化は比較的うまくいった。観ている方まで暑くなったり、寒くなったりする。
次に、爆音のうるさい部屋から、音一つしない部屋への移動、という変化をやってみる。
これは、気温ほどには、うまくいかなかった。
高さのある鉄骨、というビジュアルなどはまだイメージしやすいし、
暑いや寒いもイメージが身近だけども、
ビジュアル化できず、しかも日常にあまりない感覚を結びつける、というのは難しいようだった。
うまくいっていた俳優さんに、どういう感覚でやっているか、と聞いてみたら、
「音の情報が入ってくると、頭がぐちゃっとなるので、それは嫌だから、それを排除しようとする感じ」
と言っていて、なるほど、と思った。
目には見えないけれど、「外からの情報を、どう処理したくなるか」という生理のリアクションも、
アプローチを考える上で、とてもヒントになりそうだ。
もっと色々やりたかったのだが、時間がなくなってしまい、
最後に一番始めにやったエチュードを、同じ組みでもう一度やった。
・野外のライブである、という環境に対するイメージ
・亡くなったはずの大事な人に再会した、という濃い関係性を、そこにいる相手との間にもつか
に、今一度留意して欲しい、とだけ伝えた。演出は特にしていない。
二回目、全体的におもしろくなり、特に二組が劇的におもしろくなった。
亡き人に再会したかもしれない、というAの緊張感や戸惑いを、Cに話しかけられている間もいかに切らさずにつなげるか、
というところが、客席から見たときに、とても大事なのだということが分かった。
うまくいった二組は、ここがうまかったので、説得力があった。
Cに話しかけられたときに、その緊張が切れてしまうなら、AのBに対する重要度は低く見えてしまう。
そして、パォーマティブな芝居が得意な俳優さんがAを演じたとき、緊張感を続けている中で最後に、
コメディーよりの泣きの芝居をしたときに、この温度感が、見ている人にとってはとても心地良いんだな、と思った。
リアリティーがあるから、切実さは信じれるんだけど、どこか突き放して見れる距離感。
ここはもっと研究したいところ。
あと、シーンをやってみて、全体的に言えることなのだけど、
発語する前まで(ただ、相手を見る、とか)の方が良く、発語すると何かギアが入ってしまう、という課題は、どう解決していくべきか、というのを考えた。
テキストがあった状態でやるよりも、エチュードは自分で言葉を選べるので、生理にあったものが出やすいはずなのだけど、
それでも、わたしたちは発語するときと、発語する前よりも何かスイッチを入れたくなってしまう。
それってなんだろう。
発語する、自分の音を聞いてしまって、リアクションだけで居られなくなり、調整を図ろうとするからなのか。
4人の中で、発語前ー発語のところに特に段階なく、うまくいっていた俳優さんは、唄を歌っている人だったので、
呼吸の仕方とか、歌う身体とか、何かヒントにならないかしら、と、今考えながら思った。
そんな感じで、見えないものに神経を使い続ける時間は、とてもとても疲弊するのだけど、(みなさんぐったりしていた)
みなさんの身体をみつめる時間は、わたしにとってはとても実りある時間だった。
ありがとうございます。
長々と書きっぱなした感じだが、備忘のため、今後も書ければと思う。
よし、寝る。
ふじわら











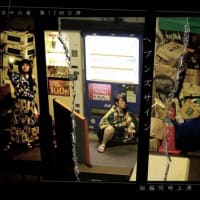

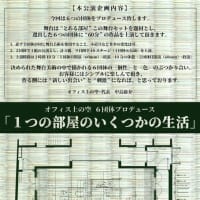






※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます