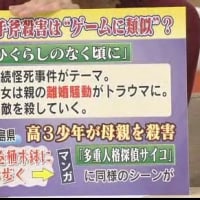民主・山岡氏、外国人参政権法案提出の意向 国会延長も(朝日新聞) - goo ニュース
民主党の山岡賢次国会対策委員長は6日、在日韓国・朝鮮人を中心とする永住外国人に地方参政権を付与する法案を、議員立法で今国会に提出する意向を示した。国会内で記者団に語った。永住外国人への地方参政権付与は民主党の小沢一郎幹事長の持論で、公明党も前向きだ。山岡氏は民主党の一部や自民党の根強い反対論に配慮し、採決時に党議拘束を外すことも検討していることを明らかにした。
山岡氏は同日、自民党の川崎二郎国対委員長と国会内で会談し、こうした意向を説明。今国会での成立に協力を求めた。この問題について鳩山由紀夫首相は5日の衆院予算委員会で、「前向きに考えていきたい」としつつ、各党の議論を見守る姿勢を示している。
今回は、外国人参政権について、これまでの関連判例を取り上げつつ、法解釈的に検討していきたいと思う。
まず前提問題として、憲法10条には「日本国民たる要件は、法律でこれを定める。」とある。ここで言う「法律」とは国籍法のことである。では国籍法では「日本国民たる要件」について、どのような考え方をしているのであろうか。
国籍法では、出生によって日本国籍を取得するとしている(1条)。すなわち、「日本国民たる要件」とは、日本国籍を有していることである。したがって、憲法10条にいう「国民」とは、日本国籍を有する者を指すということになる。
以上によって、憲法にいう国民とは日本国籍を有する国民であるということが明らかになった。では、次に具体的に外国人の人権が問題となった判例を取り上げてみよう。
まず取り上げたいのは、最高裁平成4年11月16日判決、いわゆる「森川キャサリーン事件」とよばれる事件である。
本件は、外国人である原告が韓国に旅行に行くために再入国の申請を行ったが、法務大臣は指紋押捺拒否を理由にこれを不許可としたことから、原告が処分の取り消しと損害賠償を請求したというものである。
本件について最高裁は、「我が国に在留する外国人は、憲法上、外国へ一時旅行する自由を保障されているものではない。」と判示し、原告の請求を棄却した。またここで最高裁は、国際人権規約12条4項にある「自国に戻る権利」の「自国」とは、「国籍国」であると解釈している。
次に取り上げたいのは、最高裁昭和53年10月4日判決、いわゆる「マクリーン事件」と呼ばれる事件である。
本件は、アメリカ人である原告が日本在留中にベトナム戦争反対等のデモに参加したことが我が国における政治活動を行ったことになるとして、在留許可の更新が拒否された事件である。
本件について最高裁は、「政治活動の自由についても、我が国の政治的意思決定又はその実施に影響を及ぼす活動等外国人の地位にかんがみこれを認めることが相当でないと解されるものを除き、その保障が及ぶ」が、「外国人に対する憲法の基本的人権の保障は、右のような外国人在留制度の枠内で与えられているにすぎない」と判示し、原告の請求を棄却した。
そして最後に取り上げるのが、くだんの最高裁平成7年2月28日判決(以下、「平成7年判決」という。)である。本件は事案を省略して判決のみを抜粋させてもらう。
本件について最高裁は、少し長くなるが、「地方自治について定める憲法第八章は、九三条二項において、地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の官吏は・・・(憲法の)国民主権の原理及びこれに基づく憲法一五条一項の規定の趣旨に鑑み、地方公共団体が我が国の統治機構の不可欠の要素をなすものであることをも併せて考えると、
憲法九三条二項に言う「住民」とは、地方公共団体の区域内に住所を有する日本国民を意味するものと解するのが相当であり、(九三条二項は)我が国に在留する外国人に対して、地方公共団体の長、その他議会の議員等の選挙の権利を保障したものということはできない」と判示し、原告の請求を棄却している(かっこ内は筆者加筆)。
以上、外国人の人権、特に政治的なことがらに関するものを取り上げたが、ここで明らかになったことは以下のとおりである。
まず、森川キャサリーン事件において最高裁は、国際人権規約にいう「自国」について、「国籍を有する国」と解釈した。この意味は大きい。
「外国人」参政権ということから当然に、選挙権の付与の対象は外国人である。ここでこれまでの解釈を踏まえて考えると、我が国で外国人差政権付与の対象となる人たちは、国籍は当然日本ではない(そもそも、日本国籍を有する外国人とは形容矛盾である)。
つまり、彼らの「自国」とは、彼らの国籍国であって日本ではない。そうであるならば、国籍法と憲法との関係を踏まえてみれば、彼らは我が国の「国民」ではない。したがって、外国人には参政権を付与することはできないということになる。
次に、マクリーン事件において最高裁は、「我が国の政治的意思決定又はその実施に影響を及ぼす活動等外国人の地位にかんがみこれを認めることが相当でないと解されるもの」と述べた。この意味も非常に大きい。
そもそも、この事件の原告であるマクリーンは、我が国でベトナム戦争反対のデモをしたという行為が政治的行為と認定され、在留許可更新を拒否した法務相の行為が裁量の範囲内とされている。それなのに、これよりもはるかに「政治的」な行為である外国人の参政権が、どうして容認できるというのだろうか。
また、現在では道州制の構想をはじめ、地方分権が平成7年当時よりもはるかに進む中で、国政の中に占める地方の役割はますます大きくなっている。
そうであるならば、まさに現在こそ、平成7年判決が言うように、「地方公共団体が我が国の統治機構の不可欠の要素をなすものであ」り、したがって、地方自治体の政治的意思決定の結果が、我が国の国政に多大な影響を与えるということになる。よって、現在では平成7年当時よりも、外国人参政権の違憲性は増しているとすら言える。
この平成7年判決を、参政権三賛成派はしばしば法的根拠として持ち出すことがあるが、これは全くの誤りであることをここで指摘しておきたい。彼らの主張が誤っている理由は以下のとおり。
外国人参政権賛成派は平成7年判決は外国人に対して選挙権を付与しても憲法上違憲ではないとするが、平成7年判決が引用したマクリーン事件判決では、「政治活動の自由についても、わが国の政治的意思決定又はその実施に影響を及ぼす活動等外国人の地位にかんがみこれを認めることが相当でないと解されるものを除き、その保障が及ぶものと解するのが、相当である。」としている。
現在でも判例としての地位を失っていないこの文言を反対解釈すれば、外国人参政権は違憲であり、到底認められないものという結論に至るのではないだろうか。
また、平成7年判決でも、「主権が「日本国民」に存するものとする憲法前文及び一条の規定に照らせば、憲法の国民主権の原理における国民とは、日本国民すなわち我が国の国籍を有する者を意味することは明らかである。そうとすれば、公務員を選定罷免する権利を保障した憲法一五条一項の規定は、権利の性質上日本国民のみをその対象とし、右規定による権利の保障は、我が国に在留する外国人には及ばないものと解するのが相当である。」と述べている。
このように先の文言が、参政権は「住民」すなわち「日本国民のみに」保障されていると解釈していたにもかかわらず、こう解釈した「住民」について、日本国民以外の「住民」に参政権を付与することが違憲ではないとする園部裁判官の解釈はこれに矛盾するものではないかと思う。
したがって、そもそもこの平成7年判決それ自体が矛盾を孕んだものであり、先例としての意味を有さないとしたほうが妥当ではないかと考えるからである。
このことを端的に表現すれば、Aすることは憲法上許されないとしておきながら、Aすることは憲法上許される解釈することが全くもって整合性を有していないということだ。
以上、法解釈的に外国人参政権がどうして許されないのか検討してきた。この検討が少しでも外国人参政権成立阻止に役立てば幸いである。
民主党の山岡賢次国会対策委員長は6日、在日韓国・朝鮮人を中心とする永住外国人に地方参政権を付与する法案を、議員立法で今国会に提出する意向を示した。国会内で記者団に語った。永住外国人への地方参政権付与は民主党の小沢一郎幹事長の持論で、公明党も前向きだ。山岡氏は民主党の一部や自民党の根強い反対論に配慮し、採決時に党議拘束を外すことも検討していることを明らかにした。
山岡氏は同日、自民党の川崎二郎国対委員長と国会内で会談し、こうした意向を説明。今国会での成立に協力を求めた。この問題について鳩山由紀夫首相は5日の衆院予算委員会で、「前向きに考えていきたい」としつつ、各党の議論を見守る姿勢を示している。
今回は、外国人参政権について、これまでの関連判例を取り上げつつ、法解釈的に検討していきたいと思う。
まず前提問題として、憲法10条には「日本国民たる要件は、法律でこれを定める。」とある。ここで言う「法律」とは国籍法のことである。では国籍法では「日本国民たる要件」について、どのような考え方をしているのであろうか。
国籍法では、出生によって日本国籍を取得するとしている(1条)。すなわち、「日本国民たる要件」とは、日本国籍を有していることである。したがって、憲法10条にいう「国民」とは、日本国籍を有する者を指すということになる。
以上によって、憲法にいう国民とは日本国籍を有する国民であるということが明らかになった。では、次に具体的に外国人の人権が問題となった判例を取り上げてみよう。
まず取り上げたいのは、最高裁平成4年11月16日判決、いわゆる「森川キャサリーン事件」とよばれる事件である。
本件は、外国人である原告が韓国に旅行に行くために再入国の申請を行ったが、法務大臣は指紋押捺拒否を理由にこれを不許可としたことから、原告が処分の取り消しと損害賠償を請求したというものである。
本件について最高裁は、「我が国に在留する外国人は、憲法上、外国へ一時旅行する自由を保障されているものではない。」と判示し、原告の請求を棄却した。またここで最高裁は、国際人権規約12条4項にある「自国に戻る権利」の「自国」とは、「国籍国」であると解釈している。
次に取り上げたいのは、最高裁昭和53年10月4日判決、いわゆる「マクリーン事件」と呼ばれる事件である。
本件は、アメリカ人である原告が日本在留中にベトナム戦争反対等のデモに参加したことが我が国における政治活動を行ったことになるとして、在留許可の更新が拒否された事件である。
本件について最高裁は、「政治活動の自由についても、我が国の政治的意思決定又はその実施に影響を及ぼす活動等外国人の地位にかんがみこれを認めることが相当でないと解されるものを除き、その保障が及ぶ」が、「外国人に対する憲法の基本的人権の保障は、右のような外国人在留制度の枠内で与えられているにすぎない」と判示し、原告の請求を棄却した。
そして最後に取り上げるのが、くだんの最高裁平成7年2月28日判決(以下、「平成7年判決」という。)である。本件は事案を省略して判決のみを抜粋させてもらう。
本件について最高裁は、少し長くなるが、「地方自治について定める憲法第八章は、九三条二項において、地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の官吏は・・・(憲法の)国民主権の原理及びこれに基づく憲法一五条一項の規定の趣旨に鑑み、地方公共団体が我が国の統治機構の不可欠の要素をなすものであることをも併せて考えると、
憲法九三条二項に言う「住民」とは、地方公共団体の区域内に住所を有する日本国民を意味するものと解するのが相当であり、(九三条二項は)我が国に在留する外国人に対して、地方公共団体の長、その他議会の議員等の選挙の権利を保障したものということはできない」と判示し、原告の請求を棄却している(かっこ内は筆者加筆)。
以上、外国人の人権、特に政治的なことがらに関するものを取り上げたが、ここで明らかになったことは以下のとおりである。
まず、森川キャサリーン事件において最高裁は、国際人権規約にいう「自国」について、「国籍を有する国」と解釈した。この意味は大きい。
「外国人」参政権ということから当然に、選挙権の付与の対象は外国人である。ここでこれまでの解釈を踏まえて考えると、我が国で外国人差政権付与の対象となる人たちは、国籍は当然日本ではない(そもそも、日本国籍を有する外国人とは形容矛盾である)。
つまり、彼らの「自国」とは、彼らの国籍国であって日本ではない。そうであるならば、国籍法と憲法との関係を踏まえてみれば、彼らは我が国の「国民」ではない。したがって、外国人には参政権を付与することはできないということになる。
次に、マクリーン事件において最高裁は、「我が国の政治的意思決定又はその実施に影響を及ぼす活動等外国人の地位にかんがみこれを認めることが相当でないと解されるもの」と述べた。この意味も非常に大きい。
そもそも、この事件の原告であるマクリーンは、我が国でベトナム戦争反対のデモをしたという行為が政治的行為と認定され、在留許可更新を拒否した法務相の行為が裁量の範囲内とされている。それなのに、これよりもはるかに「政治的」な行為である外国人の参政権が、どうして容認できるというのだろうか。
また、現在では道州制の構想をはじめ、地方分権が平成7年当時よりもはるかに進む中で、国政の中に占める地方の役割はますます大きくなっている。
そうであるならば、まさに現在こそ、平成7年判決が言うように、「地方公共団体が我が国の統治機構の不可欠の要素をなすものであ」り、したがって、地方自治体の政治的意思決定の結果が、我が国の国政に多大な影響を与えるということになる。よって、現在では平成7年当時よりも、外国人参政権の違憲性は増しているとすら言える。
この平成7年判決を、参政権三賛成派はしばしば法的根拠として持ち出すことがあるが、これは全くの誤りであることをここで指摘しておきたい。彼らの主張が誤っている理由は以下のとおり。
外国人参政権賛成派は平成7年判決は外国人に対して選挙権を付与しても憲法上違憲ではないとするが、平成7年判決が引用したマクリーン事件判決では、「政治活動の自由についても、わが国の政治的意思決定又はその実施に影響を及ぼす活動等外国人の地位にかんがみこれを認めることが相当でないと解されるものを除き、その保障が及ぶものと解するのが、相当である。」としている。
現在でも判例としての地位を失っていないこの文言を反対解釈すれば、外国人参政権は違憲であり、到底認められないものという結論に至るのではないだろうか。
また、平成7年判決でも、「主権が「日本国民」に存するものとする憲法前文及び一条の規定に照らせば、憲法の国民主権の原理における国民とは、日本国民すなわち我が国の国籍を有する者を意味することは明らかである。そうとすれば、公務員を選定罷免する権利を保障した憲法一五条一項の規定は、権利の性質上日本国民のみをその対象とし、右規定による権利の保障は、我が国に在留する外国人には及ばないものと解するのが相当である。」と述べている。
このように先の文言が、参政権は「住民」すなわち「日本国民のみに」保障されていると解釈していたにもかかわらず、こう解釈した「住民」について、日本国民以外の「住民」に参政権を付与することが違憲ではないとする園部裁判官の解釈はこれに矛盾するものではないかと思う。
したがって、そもそもこの平成7年判決それ自体が矛盾を孕んだものであり、先例としての意味を有さないとしたほうが妥当ではないかと考えるからである。
このことを端的に表現すれば、Aすることは憲法上許されないとしておきながら、Aすることは憲法上許される解釈することが全くもって整合性を有していないということだ。
以上、法解釈的に外国人参政権がどうして許されないのか検討してきた。この検討が少しでも外国人参政権成立阻止に役立てば幸いである。