
お待ちかね、やっと吉原へお出ましだ。
石浜神社、橋場不動尊からは、今戸神社まで戻って、山谷堀沿いの道を大門前まで行くという方法もある。
また、「世界救世教教祖生誕地」の石碑が見えたら、西に進路をとり、道なりに進んでいって、吉原大門に至るというバイパス的な方法もある。
バイパス路を通ると、途中、松吟寺という小さな寺があり、そこに、お化け地蔵が立っている。
なぜ、お化け地蔵なのか、伝承がいくつかあり、身の丈が3mもあるからとか、昔、笠をかぶっていて、笠の向きがよく変わったからというのもある。
解説案内板には、もともと浅茅ヶ原という茅が生い茂る場所に立っていたものを、大きな寺域を持つ「総泉寺」の入口に移したという記録があると書かれる。
浅茅ヶ原といえば、上田秋成の雨月物語の中の「浅茅が宿」を思い浮かべる。
浅茅が宿の舞台となる場所は、千葉県市川市真間・・・そう、“真間の手児奈”伝説のある真間、石浜・橋場からは、武蔵・下総の国境を隔てて目と鼻の先、もちろん浅茅が宿に登場する宮木は、手児奈をモデルとして書かれたのではないかといわれているのも、何かの関連がありそうだ。
地蔵は、子どもの守り本尊とされるが、地獄の責め苦から救済するとも信じられていたことから、女性の信仰を集める。
その辺りを考え合わせると、お化け地蔵が、浅茅ヶ原に立っていた所以も偲ばれるのではないだろうか?
さて、吉原大門前の交差点を渡ると、遙か先に東京スカイツリーが見える。
ガソリンスタンドの前に見返り柳(下写真右)が植えられている。
吉原大門といっても、実際に大門がある訳ではないので、この見返り柳が目印となる。
大門前の通りには、有名な天丼の伊勢屋など老舗がある。
ところが、肝心の新吉原遊郭のあったエリアに入っていくと、往時の名残をとどめるような古風な建物などはない。
ただ、遊興の場所として、風俗店が軒を並べている。
客引きをするでもなく、ポツリポツリと、独特の建物と看板が雰囲気を醸し出す。
売春防止法が施行される前は、吉原細見などという名のガイドブックが飛ぶように売れ、それを頼りに遊郭に揚がるお客さんもいれば、ただ冷やかしに来る人もいて、全盛を誇ったといわれる。
今も、何かの案内書が存在しているのかも知れないが、ただ単に通過しただけでは、淫靡さも、色香のかけらも感じられない。
吉原の大通りを奥まで進み、大門の入口と同じ、道がS字カーブに曲がろうとする手前、右側に吉原神社の鳥居が建っている。
明治5年に、新吉原遊郭の四隅に祀られていた4つの稲荷社(開運稲荷、九郎助稲荷、榎本稲荷、明石稲荷)と地主神として祀られていた玄徳稲荷を合祀して、吉原神社が創建された。
昭和10年には、吉原弁財天を合祀して今に至っている。
新吉原遊郭の盛衰とともにあって、常住の神職がいなかったため、千束稲荷神社まで行くか、もしくはあらかじめ連絡をとらなければ御朱印をいただくことはできなかったが、東京スカイツリー効果で、浅草名所七福神が、浅草散策のプログラムの一つとして注目されるようになったので、社務所も新築して、土日ぐらいは神職が常駐できるようになったという。
女性が信仰を寄せていたせいか、朱色の艶やかさが際立つ拝殿。
狛犬は、オリエント様式っぽい、獅子を思わせる厳つく堅牢なもので、往古の繁栄を彷彿とさせる。
こぢんまりした境内には、アナウンスの流れる新吉原遊郭の歴史解説板があったり、関東大震災か東京大空襲かで焼失した黒こげのあとが痛々しい天の邪鬼の石像が立っていたりする。
ご朱印は、弁財天だけに、蛇をあしらって、よし原と囲む。
ただし、小さな朱印帳では書ききれないため、大判のものだけに限って、書き込むのだそうだ。
今後も、東京スカイツリーのおかげで、参拝者が続くようであれば、賑わいのある新吉原遊郭時代を思わせるような神社に復興していきたいとも話されていた。
そうなれば、また楽しみに行ってみたいところだ。 (大祓詞)
(大祓詞)
7> 吉原神社「弁財天」ご朱印
日本大通りと富士山を被写体として、定点観測中です。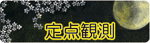















※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます