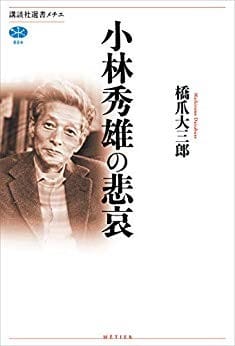
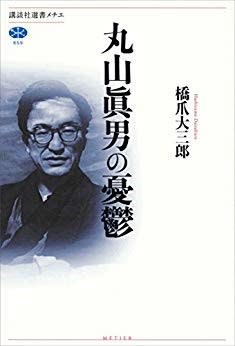
橋爪大三郎氏の『小林秀雄の悲哀』を読んだ。
刊行された当初は、出版元の講談社のサイトにある
試し読み
をざっと読んで、読む必要性を全く感じなかったのだけれども、図書館で『丸山眞男の憂鬱』を見つけ、ふとパラパラと中味を覗いて見たところ、俄然興味を惹かれたので、すぐ横にあった『小林秀雄の悲哀』とともに、借り出して来た次第である。
この『小林秀雄の悲哀』については、浜崎洋介氏の書評
(「直感」の「限界」について 小林秀雄の言葉を〝小林神話〟から救い出す)
がこれもネットで読むことが出来る。
そもそもテーマパークじゃあるまいし、なぜに文芸批評家に「日本最大の」なる形容詞を冠するのか?とか、<ベルグソン譲り>なら「直感」じゃなくて「直観」でしょ?といった些末な(よく考えてみると結構意味深な)”言いまつがい”はともかく、この本の骨子については実に的確な要約をしてくれている。そして、あえて裏を読んだ結語ーー<それなら本書は、小林の言葉を小林神話(批評の神様)から救い出し、『本居宣長』という本を、その本来の場所――つまり、文学論へと差し戻すためにこそ書かれたと言えはしまいか>という結語もなかなかエスプリが効いていると言いたいところだが、誤読もここに極まれりである。
私に言わせると、橋爪氏は小林の『本居宣長』という著作自体の意図が全然読めてはいないので、<これを批評とは言わない>、<批評と言うものを知らない>、<小林秀雄のことを、私は「批評家」だと認めない。批評めいた文体を繰り出すだけの、哀れな文筆家に過ぎない>と全編これ否定のオンパレードであるが、大雑把で図式的公式主義的な考察や三流週刊誌の様な動機分析が、のほほんと脳天気な無邪気さでもって語られるのには、読んでいて思わず笑ってしまった程である。いや、何も私はこの本に対抗して「橋爪大三郎の滑稽」と言う大論文をものするつもりはないが、そこに透けて見える橋爪氏のこの『本居宣長』に対する誤解というか無理解というものの性質が、この『本居宣長』という著作を論ずるのに誠に都合の良いものなので、取り上げる気になったということである。
私が根本的な疑問を感ずるのは、浜崎氏の言葉で言う<一切の論点>―<『古事記伝』には、良くも悪くも皇国イデオロギーを可能にしてしまうカラクリ>、さらに言えば<「江戸思想」と「国学」と「近代日本」とを結ぶ系譜学>、すなわち『古事記伝』が<「天皇」を介して後期水戸学(儒教的政治論)へと繋がり、近代日本のナショナリズムを、そして、昭和戦中期の皇国イデオロギーをも用意することになる>という<これらの論点の一切>を、小林の『本居宣長』は拾えていないというのであるが、明確に言及していないからと言って、果してそう断言できるのだろうか?という点である。むしろ、<これらの論点の一切>を暗黙の前提として、それに対抗するものとして小林の『本居宣長』は、書かれたのではないのか。
そしてまた私が浜崎氏にも疑義を抱くのは、
<なるほど、小林自身は「作者の肉声を聞く」ことによって、強張った皇国イデオロギー(政治)から、本居宣長本来の柔かさ(文学)を救い出し、自らの「批評」の起源にある姿を、つまり、伝統を味わい、それを生きる文学者の姿を定着したかったのかもしれない。>
といったような(政治)と(文学)を分断して対置し、後者に小林批評を限定し、そこに小林を押し込めようとする見方である。
これ等の点についてはおいおい見ていきたいと思うが、そうは言ってもやはりその前に、『本居宣長』が全く読めてない「橋爪大三郎の滑稽」と大口を叩くからには、しかるべき理由を書いて置くのが筋と言うものであろう。以下、判り易いと思われる論点を幾つか挙げるだけに留めるが、まあ、これくらいで必要にして十分であろう。
まずは、<8「日の神論争」>の部分(p238~)。
<小林は冒頭で、宣長の学問は≪難点を蔵していた≫と断言してしまう。これはないだろう。>
<小林はいかにも、宣長に理がないように言っている。・・・・これを勝手に「逃げ口上」と決めつけるのは、批評としてフェアでなかろう。>
「ええっ!?」と私は思わず吹き出してしまったのだが、いや、橋爪先生、文間が読めないというか、文脈が読めないというか、学者としてもちょっとこの読みはいくら何でもないんじゃないの?ここで引用されている『本居宣長』(四十)の記述は、論争自体が噛み合っていないという事を示すために、秋成の目には宣長の言うところがどういう風に映ったのかを描いている文章であって、宣長に対する小林自身の見解を述べた文章ではないことは明々白々だと思うのですけどね。
他のところで橋爪先生も引用している小林秀雄・江藤淳対談でも、このように述べられている訳で、ここの部分は読み落としたのか、或は意図的に無視したのか知りませんけど。
<江藤 ・・・そのときも、私は納得がいかなかったのです。なぜ、日本を相対化している秋成がだめで、宣長の言っていることが正しいということになるのか。私はこの論争が噛み合っている論争だとばかり思い込んでいたものですから、秋成の言うことにも一部の理はあるのではないかと考えていたのです。
ところが、今度御本を拝見して、はじめてなるほどと納得がいきました。・・・
小林 あの論争は、批評家にとっては好都合な論争なんです。それを私は利用したわけです。どうもあゝいうものを利用しないとなかなかわからぬ思想の上での機微がありますね。>
それから今一つは、<いまわれわれは、本書のもっとも中心となる内容を、論じつつある>という部分で、宣長の『馭戎概言』を引いて、その解釈を述べた部分(P389)である。この部分は、橋爪氏本人も言うようにこの著作のロジックの根幹となる部分なので、ここは避けて通ることの出来ない論点である。
<宣長は『馭戎概言』・・・で日本の統治システムについて、こうのべる。≪天皇のかぎりなく尊くまします御事は。申すもさらなれど。まづ大御国は。萬の国をあまねく御照らしまします。日の大御神の御国にして。天地の間に及ぶ国なきを。やがてその大御国の御末を。次々に伝えましまして。天津日嗣と申て。其御国しろしめし。万代の末までも。うごきなき御位になんましま≫す。
また、中国と日本のあるべき関係について、遣隋使の携えた手紙を例に、こうのべる。≪かのよしもなくみだりにたかぶりおる。もろこしの國の王など・・・へ。詔書たまはんには。天皇勅隋國王などとこそ有べきに。此度かれをしも。天子とのたまへるは。ゐやまひ給へること。ことわりに過たりき。≫≪そもそももろこしの國王が。いにしへよりかくのみゐやなきは。天皇のことなる御尊さをわきまへしらずて。ことわりにそむける。みだりごとなる物をや。・・・天皇とあがめ申さざらんかぎりは。こなたよりも。かの王を天子皇帝などと。あがめいふべきにあらず。又かの國につかはす書のみにもあらず。すべて皇国のうちにて。つねに物にかき。口にいふ詞にも。ましてかの王を尊みて。天子皇帝などとは。かりにもいふべきわざにあらず。そはかの王のさだめをうけ。したがふ國のもののいふ言にこそあれ≫
要するに、日本は、あるべき国際秩序の中心となるべきである。なぜなら、日本は、カミガミの意志をあらわす古言を受け継ぎ、そのもとに統治秩序を実現している唯一の国であり、世界の国々、世界の人々を指導すべき存在なのだから。
*
どうだろうか。実証的な作業として始まった『古事記』の読解が、実にスムーズに、なめらかに、超国粋主義的な主張に移行しているではないか。>
そして、<この移行の具体的なあり方は、これまで注目もされず詳しく論じられもしていないと思う>と述べ、橋爪氏はいささかドーダ・モードに入っているようだが、何をか言わんや、これは宣長の論理を勝手に延長した全く持って恣意的な解釈と言う他ないものである。確かに橋爪氏の言うように宣長は、日本の<このような国のあり方は、すぐれていて、正しく、また美しい。日本はそのことを自覚し、誇るべきである。他の国はそのことを認め、敬意をはらうべきである>とは述べているが、<日本は、あるべき国際秩序の中心となるべきで・・・世界の国々、世界の人々を指導すべき存在>だなぞとは一言も主張してはいない。一体全体、この引用文のどこにそんな記述があるんですかね?どうやら橋爪先生は、学者以前にそもそも文章自体がまともに読めない人ではないのか、読んでいてそういった疑義がしきりに頭に浮かんできてしようがないのであるが、こう思うのは私だけであろうか。
ここは宣長をどのように捉えるのか、分水嶺となる最も重要な論点なので、この文章を読んでいる方はぜひ実際に『小林秀雄の悲哀』に当たって、この該当部分を確認して頂きたいと思う。出来ればさらに進んで『馭戎概言』自体に当たって中味を直接読んで頂きたいとも思うが、これまでにも『馭戎概言』は「直毘霊」と並んで宣長の狂信的な国粋主義思想を典型的に示す文章というレッテルを張られてきた。このこと自体も、色々と考えさせられる問題だが、普通に読めば宣長の言っていることは、日本の外交史に見られる属国の様な卑屈な態度を嘆き、単に矜持を持って外交に当たれと主張しているのに過ぎないのであって、要は土下座外交をするなと言っているだけのことである。
従って、<実にスムーズに、なめらかに、超国粋主義的な主張に移行している>などとはデタラメもいいところで、橋爪先生、こんなことを言っていてはチコちゃんに叱られても知らないからね、そう私は忠告しておく次第である(笑)。これは『丸山眞男の憂鬱』の表現で言えば、明らかな<誤認逮捕>、意図的な冤罪のでっち上げであって、むしろ、こういった恣意的な飛躍した発想法こそが超国家主義的・超国粋主義的な主張の根幹をなすものではないのか、と橋爪先生には猛省を促したいと思うのである。
ということはまた当然に、先の<『古事記伝』には、良くも悪くも皇国イデオロギーを可能にしてしまうカラクリ>――『古事記伝』が<「天皇」を介して後期水戸学(儒教的政治論)へと繋がり、近代日本のナショナリズムを、そして、昭和戦中期の皇国イデオロギーをも用意することになる>というスキームが、根本的な見直しを要請される事にもなる訳である。実のところ、この橋爪氏のスキームは、山本七平のスキームを下敷きにした誤流用、その論理を逸脱した応用といって良いが、その逸脱ぶりは、宣長に対する平田篤胤のそれを思わせるものがある。この点についても後程述べることになろう。
ついでにもう一つ挙げておこうか。橋爪氏は宣長をボッブズになぞらえているが、これも相当に無理筋の思い付きである。「神勅」と「社会契約」に<通じるものがある>と言われれば、そりゃあ<通じるものがある>でしょうねと答えるだけの事であって、こんなことを言えば、人間とエリマキトカゲにだって<通じるものがある>。後肢だけで直立歩行出来るからね。この点はご本人も自覚しているようで、面倒なので一々引用しないが、直ぐに続けて社会契約と異なる「特異点」を、七つも!挙げているのはご愛嬌と言う他ない。橋爪氏は著名な社会学者らしいが、そもそも、これだけ異なる「特異点」があるのなら「社会契約」を持ち出してくる本質的な意味合いがどこにあるんですかね、と私は言いたい。『丸山眞男の憂鬱』で橋爪氏も述べているように、<お手本となる都合のよい西洋のもの差しは存在しないのだ>。これもおいおい述べていきたいと思うが、宣長は社会思想家としてはむしろ反対に、社会契約を批判した思想家の系列に列せられる思想家であって、その発想に置いて本質的に同質の西洋の思想家として引き合いに出すとすれば、それはエドマンド・バークであろう。
面倒なので他にも一々挙げないが、この『小林秀雄の悲哀』はこういった臆断・独断の連続技で構成されていて、それが理由であろう、「小林秀雄ゆかりの出版社」には断られたらしいが、これを出版した講談社の英断には或は拍手を送るべきかも知れない。ま、予期していた事とは言え、試し読みの時の、私のベルクソン譲りというほどでもない”直観”を確認するだけの読書に終わったのは、残念と言う他はない。やれやれ。従って、この本は『恵み』だとか『ドーダ』とか『戦争の時』だとかと一緒に「小林秀雄マウンティング本」と表示された分別コンテナに放り込んで置くのに如くはない。その裡、業者が然るべく処分してくれるだろう。
とまあ言ったような事で、この『小林秀雄の悲哀』という本の個別の価値自体はそれはそれとして、『丸山眞男の憂鬱』と通して読んでみると、そこにはこの『小林秀雄の悲哀』という著作の背後に、ある一冊の本が浮き上がってくるのもまた確かなことなのであって、むしろ私の目はそちらの方に向くのである。
その一冊とは、山本七平の『小林秀雄の流儀』である。









