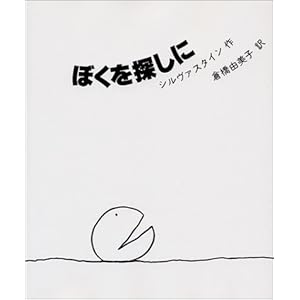最近あまりテレTVと言うものを見ていなかったのですが、久しぶりにNHKのスイッチインタビュー達人達を観ました。
昨年10月放送の再放送。
この時も番組の途中から観ていましたが、改めて是枝監督が話されていたことで、なるほど~と思ったことを書いてみます。
「そして父になる」
主演は福山雅治さんですが、実は福山さんの方から是枝監督に、一緒に仕事が出来たら・・と言うことをおっしゃっていたようですね。
福山雅治演じるエリートサラリーマンの一人息子は、実は赤ん坊の時に取り違えられた子供だったと分かった。。血を分けた子供は、地方の電気店を営む一家に育てられていた。。
対するこの父に、リリー・フランキーを抜擢するにあたり、悪人にも善人にも見える、そして、ああ自分の血を分けた子が、こんな奴に育てられていたのかと思わせるようなキャスティング・・と言うことだったそうです。
ところが、父性としては、リリー・フランキー演じる父親の方が上だった。
時間の経過とともに、父性と言うものを見つめ直してゆく。。と言うように組み立てられているようです。
電気店の一家の部屋は、ゴチャゴチャ感を出して、時間の経過を感じさせるように、エリートサラリーマンの家は、なるべく無駄を省きそれを感じさせないという演出が施してあるそうです。
子役については、日本の映画の中で、課題だと感じているそうで、ドキュメンタリー出身の監督は、「誰も知らない」「歩いても歩いても」等、多くの話題作を世に送っていますね。
映画はあまり見ない方ですが、「誰も知らない」は、観たことがありました。
主演の柳楽優弥が史上最年少の14歳という若さで、2004年度カンヌ国際映画祭主演男優賞に輝いた作品で、実際に起きた、母親が父親の違う子供4人を置き去りにするという衝撃的な事件を元に構想から15年、満を持して映像となったそうです。
内容もさることながら、子役の演技は非常にリアリティーが高く、作品を描く時の監督の視点がどのようなものなのか・・と・・
今どき、子役がもてはやされていますが、彼らの演技に違和感を感じているのは私だけではないようで、あれは大人が子供に対して、こうあるべき・・を押し付けているとさえ感じてしまいます。
或いは子役の子たちが、親や世間がこのようなものを期待しているのだろうということを演じている。。演じさせられている。。
「わざとらしさ」
ひとことで言えばそういうことで、「リアリティー」からは程遠い。。
その事が、監督の子供の演技に対する課題のように思いました。
演出、考え方など、非常に興味深く共感できるものでした。
「歩いても歩いても」
樹木希林さん演じる母親像。
是枝監督が、母の死をこの作品を通じて消化・・あるいは昇華していった作品のようです。
この映画を、海外で上映したら、「お前はどうして自分のママのことを知っているのか?」
と、言われるそうです。
ひとつのことを掘り下げることで、逆に普遍性につながってゆく。
自分の足元を見つめ続け深く掘り下げることで、インターナショナルな世界観へ通じる。。まさに今、私も日々考えているのですが・・ぁ・・そんなに大それたことじゃないですよ・・
ただ、私たちが日頃親しく接している作品たちは、あらゆる国のあらゆる時代のもの。。
時代考察ももちろん大事で、これも興味深いことなのですが、人として変わらない「何か」もあるわけで、そういう「本質的」なものが、時代の波でそぎ落とされ、結晶となっているものが、今の時代でも、生き残り愛されているのではと思うのです。
子供たちには、甘くてふわふわした口当たり良いものがいいのでしょうが、一見そうでも、ある意味、食べ物のように、色々な歯ごたえ、味、栄養素・・などを、心の栄養として与えてあげられれば良いのかな・・などと思ってみたり。。もちろんお菓子ばかり与えるなんて、お話になりません!
近代科学は、主体(人、あるいは自分自身とも考えられます・・)と客体が分離され、そのことで非常にうまく行ったこともあり、多くの症例から、共通する事象だけを取り出し普遍化し、それに当てはめて物事を見て判断する・・ということに、あまりにも傾き過ぎたことによる歪もきているといいます。
近代の心理学も・・と言うか、哲学などに比べ、心理学は非常に新しい学問で、試行錯誤がなされているようですが・・多くの症例から普遍化してゆくという方向より、一つの事象を非常に深く掘り下げることで、共通するもの、本質的なものを見極めようとしている・・と言えましょう。
心理学も色々な方向で試みがなされているので、事象により直接的に(物質的に・・と言えるのかな・・)関わってゆくということが、アメリカを中心とした国では重点が置かれているようで、一概には言えません。
現実目の前のことを考えると、深く掘り下げることに非常に共感を持ちます。
養老孟司先生も、「身体」「無意識」「共同体」・・と言う3つの要素を重要視していらっしゃるように、心の奥深くにあることに、目を向けてゆかなければならない時代なのでしょう。
何となくできていた昔・・と違って、物質と情報に溢れかえっていて、「深める」「本質を見極める」と言うことが、非常に難しい時代なのだと思います。
何となくできていた・・と言うのは、出来なかった・・とも言いかえられます。
便利なものがなくて、炊事も洗濯も掃除も道具ひとつとってみても手間がかかり、子供も多く、物もお金もなく、、かけようにもかけてやれなかった。。手出し口出し、物を与えお金をかけること。。
今は出来てしまうぶんだけ、もっと多くの心を使い知恵を使わなければ、子育ても難しい時代と言えるのです。
ぁぁ・・・また難しい話をしてしまいました。。
すみません~

さて、もう一つ・・「金スマ」より。
瀬戸内寂聴さんが出ていらっしゃった回。。
ぼけーっとみていたのですが、終わりの方で、素晴らしい物まねでブレイクした青木隆治さん・・が出てこられまして。。
美空ひばりやら、何でもかんでもそれらしく歌い、見た目もなかなかのイケメンなので、よくテレビに出ていたけど、最近はあまり見かけない。
実は物まねではなく、自分の歌で勝負したいのだけど、何枚か出したCDはかんばしくなく、同じ事務所の先輩で、芸能界に彼を入れるきっかけを作った研ナオコさんが指導する・・と言う趣旨での撮影。
あとどれくらい時間使うんですかね~という、番組の尺の話をする青木隆治さんに対して、どれだけのスタッフがあなたのために動いていると思うの・・と、研ナオコさんが激怒する・・みたいなところで、テレビからは離れましたが。。
ただ、研ナオコさんが言っていたことは、非常にまっとうなことだったと思います。
この「あたりまえ」なことが、分からずに、歌はうたえないよなぁ・・とも思います。
上手に歌うとか、いい声で歌うとか、そういうことじゃない。
歌詞の意味を深く読み、伝えるということ。
技術が先行してはいけない。。(もちろんこれはある程度技術があることが前提ですが・・)
感謝する心がなくて、人の心を揺さぶる歌がうたえるはずがない。
非常に共感・・当然ちゃぁ当然の話で・・
何を見ても、何を聴いても、ピアノ、音楽と、通じるんですよね。。
ではこの辺で。。
ぁ・・・
 猫は、獣医師の予言通り、、、
猫は、獣医師の予言通り、、、
先週看取りました。
何度も入退院を繰り返し、昨年11月末よりひと月以上通院し、薬を欠かさず飲ませ、一喜一憂しながら過ごしていましたが・・・
さすがにこの一週間は辛かった。。
うちの殆どの犬猫は、生涯を全うし寿命と言われる年まで生きて、眠るように閉じていきましたが、、、今回はそうはゆかず。。
本人(猫ですが・・)にとっては、今回は安楽死を選んだ方が楽だったのだと思いますが、それもできず、最後は癲癇(てんかん)を抑えるための座薬を頂き、少しでも楽なように・・とは思いましたが。。
縁がなければ、悲しくもなんともないのですが、居るべきところに居ない。。
ほかの猫も、分かるのか、呼んでいるようにないています。。
まぁ、だいたい心の方は回復しています。
今日も元気に!
ですかね~
では~~


 )
)