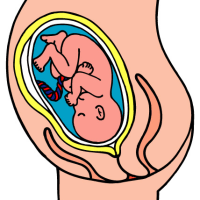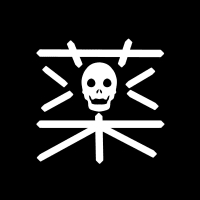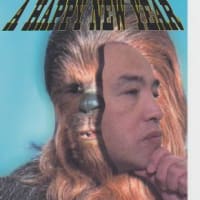脳卒中で何が怖いかというと、死ぬことよりマヒが残ることだそうで、むしろ死ねるのなら本望と言われる方もおられます。患者さんの年齢が高くなればなるほど、このような考えは多くなるようです。
実際に亡くなる方は少なくなりましたが助かった方は何かしらの後遺症はあります。
気を付けなければならないのが単身の方が卒中をおこされたときです。
手術などのリスクを伴う処置はたとえ緊急であったとしても原則として事前に本人に説明して同意を得ることが必要ですが、本人の意識が混濁していてはっきりしない場合は家族に確認してもらわなければいけません。しかし連絡がとれなかったり、
すぐに来れなかったりすると手術がおくれて最悪の場合手術できなくなるなどの
治療面で不利なことがあるようです。
なので脳卒中の経験がある方は後遺症の治療も大切ですが再発予防も重要となります。
鍼灸治療では後遺症に対して自律神経を整え脳や筋肉の血流改善をしますが、これは同時に再発予防にもなってます。このへんの治療法は今も昔もかわりません。
しかしリハビリに関しては方法や考え方が年々変化しています。
以前は、開始時期は容態が安定してからの回復期に行ってましたが発症直後、
なるべく早く開始することは常識になってます。
また 片半身が麻痺を起こしたとき、肘を曲げ腕を内側に捻り手は握られ、足では開いて爪先までピンッと伸ばした状態で固くなる、いわゆる、ウェルニッケマン肢位ですが、歩行などの日常動作においては、この異常肢位はむしろ補助的な役割をしているというのです。
一見、リハビリの弊害になるのではと思われますが、逆にマヒした腕や足の筋肉が柔らかく弛緩していたら、腕や足は、だらんとして邪魔になりたいへん不便で、 実際に脳性麻痺の患者の痙縮を起こした筋肉にボツリヌス菌を注射し筋肉を弛緩させたら歩けなかったという報告もあります。
すなわち麻痺した場合、残存機能で歩くための最適な状態にしているとも言えます。
この肢位を放置していたら関節拘縮を起こすのではないかと懸念されますが、むしろ無理な関節運動をするほうが拘縮しやすいと言われる専門家もおられます。
このように症状にも理由があるので何を持って正常かというのは考え直す必要が出てきます。
パーキンソン病でも手の震顫は末梢まで血液を送るための防衛反応だという専門医もおられますがこれは卓見だと思います。
ただ医学的にウェルニッケマン肢位の整合性を論じても介護的には衣服の着脱が難しくなるので拘縮しないようにしなければなりません。
ではどのようなリハビリがよいかということになります。
以前ここで書いた四つ足歩行によるリハビリは、健側との協調運動により脳の反射弓を返して麻痺側の運動神経を興奮させるというものでしたが、ちゃんと「原始的歩行中枢」という名前があり、これを応用したリハビリが昨年NHKで放映されたらしいのです。放送ではこの理論で製作された「足こぎ車いす」が紹介されたようです。
現在、後ろにスタンドがある自転車を持っておられる患者さんには四つ足歩行のかわりに停まった状態で自転車こぎをしてもらっています。しかし中には転倒したりする事故もあり困ってました、
この車いすなら安全で、さらに移動できるということは大きな喜びとなり心身ともによい状態を作り出せるものだと感じました。
リハビリに関しては無理して苦しい訓練をしなくてよいという専門家もおられるので日課にうまく取り入れることで充分とも言えます。
そして治療としてはこのようなリハビリがうまくいくように鍼灸治療で脳血管や麻痺筋群の血流を改善するとともに、運動療法とマッサージを加え最善の状態にしておきます。
なので治療するところを探す場合は施術者が鍼灸とマッサージの免許をもっているか、鍼灸師と理学療法士やマッサージ師がいる神経内科病院が理想です。
鍼灸治療で使う経穴は最後に列記してみますが運動療法で「上田法」というのがありまして、脳性麻痺に成果をあげています。
基本手技としては、首・肩・肩甲骨・上肢・下肢への五つのアプローチとなります。
特筆すべきは、これも今までのリハビリとは逆の方法になってます。
かたい筋肉にはよくストレッシが行なわれていたのですが上田法では逆のことをします。ただストレッチの逆をすればいいというものではなく、文書では説明しにくいので実地体験をお勧めします。
実際に「上田法」は書籍がなく、実地で体験学習するということを理念としてます。というのも実地体験なく書物による独学で施術し効果がなかった場合、「上田法」を否定されることを懸念されているからだそうです。
ということで方法の詳細は省略しますが、対象となる障害・疾患を列記しておきます。
1.脳性麻痺
2.脳炎後遺症
3.脊髄性けい性麻痺
4.筋の過緊張を伴う運動発達遅滞
5.末端けい性を伴うヒポトニー
6.その他に筋の過緊張を伴う症状の患児
7.脳血管障害の後遺症
鍼灸治療で使用している経穴をいちおう列記しますが「上田法」の理念のようにこれらの経穴を使ったが効果はでなかったということになると鍼灸自体に不信感がでる患者さんもでかねないので、治療成績をあげているベテランの先生に実地で指導を受けることをお勧めします。
頭頚肩部
百会、風池、天柱、肩井、肩外兪、巨骨、肩井、高校、肩りょう、天宗、秉風、
上肢
曲池、手三里、外関、用地、合谷、
腹部
中かん、天枢、大巨、気海、関元、
背腰部
膈兪、脾兪、胃兪、三焦兪、腎兪、小腸兪、
下肢
居りょう、環跳、風市、殷門、足三里、陽陵泉、懸鐘、外承筋、内承筋、崑崙、丘墟
今、ざっと思い浮かぶ経穴を列記しましたがまだまだあると思うので思い出したら更新しますのでチェックしといてください。
頭に刺鍼する「頭鍼療法」をやったことがありますが効果はよくわかりませんでした。
おっと!自分の技量をさておいて否定的なことを書いてはいけませんね。言ったさきから書いてしまった。
実際に亡くなる方は少なくなりましたが助かった方は何かしらの後遺症はあります。
気を付けなければならないのが単身の方が卒中をおこされたときです。
手術などのリスクを伴う処置はたとえ緊急であったとしても原則として事前に本人に説明して同意を得ることが必要ですが、本人の意識が混濁していてはっきりしない場合は家族に確認してもらわなければいけません。しかし連絡がとれなかったり、
すぐに来れなかったりすると手術がおくれて最悪の場合手術できなくなるなどの
治療面で不利なことがあるようです。
なので脳卒中の経験がある方は後遺症の治療も大切ですが再発予防も重要となります。
鍼灸治療では後遺症に対して自律神経を整え脳や筋肉の血流改善をしますが、これは同時に再発予防にもなってます。このへんの治療法は今も昔もかわりません。
しかしリハビリに関しては方法や考え方が年々変化しています。
以前は、開始時期は容態が安定してからの回復期に行ってましたが発症直後、
なるべく早く開始することは常識になってます。
また 片半身が麻痺を起こしたとき、肘を曲げ腕を内側に捻り手は握られ、足では開いて爪先までピンッと伸ばした状態で固くなる、いわゆる、ウェルニッケマン肢位ですが、歩行などの日常動作においては、この異常肢位はむしろ補助的な役割をしているというのです。
一見、リハビリの弊害になるのではと思われますが、逆にマヒした腕や足の筋肉が柔らかく弛緩していたら、腕や足は、だらんとして邪魔になりたいへん不便で、 実際に脳性麻痺の患者の痙縮を起こした筋肉にボツリヌス菌を注射し筋肉を弛緩させたら歩けなかったという報告もあります。
すなわち麻痺した場合、残存機能で歩くための最適な状態にしているとも言えます。
この肢位を放置していたら関節拘縮を起こすのではないかと懸念されますが、むしろ無理な関節運動をするほうが拘縮しやすいと言われる専門家もおられます。
このように症状にも理由があるので何を持って正常かというのは考え直す必要が出てきます。
パーキンソン病でも手の震顫は末梢まで血液を送るための防衛反応だという専門医もおられますがこれは卓見だと思います。
ただ医学的にウェルニッケマン肢位の整合性を論じても介護的には衣服の着脱が難しくなるので拘縮しないようにしなければなりません。
ではどのようなリハビリがよいかということになります。
以前ここで書いた四つ足歩行によるリハビリは、健側との協調運動により脳の反射弓を返して麻痺側の運動神経を興奮させるというものでしたが、ちゃんと「原始的歩行中枢」という名前があり、これを応用したリハビリが昨年NHKで放映されたらしいのです。放送ではこの理論で製作された「足こぎ車いす」が紹介されたようです。
現在、後ろにスタンドがある自転車を持っておられる患者さんには四つ足歩行のかわりに停まった状態で自転車こぎをしてもらっています。しかし中には転倒したりする事故もあり困ってました、
この車いすなら安全で、さらに移動できるということは大きな喜びとなり心身ともによい状態を作り出せるものだと感じました。
リハビリに関しては無理して苦しい訓練をしなくてよいという専門家もおられるので日課にうまく取り入れることで充分とも言えます。
そして治療としてはこのようなリハビリがうまくいくように鍼灸治療で脳血管や麻痺筋群の血流を改善するとともに、運動療法とマッサージを加え最善の状態にしておきます。
なので治療するところを探す場合は施術者が鍼灸とマッサージの免許をもっているか、鍼灸師と理学療法士やマッサージ師がいる神経内科病院が理想です。
鍼灸治療で使う経穴は最後に列記してみますが運動療法で「上田法」というのがありまして、脳性麻痺に成果をあげています。
基本手技としては、首・肩・肩甲骨・上肢・下肢への五つのアプローチとなります。
特筆すべきは、これも今までのリハビリとは逆の方法になってます。
かたい筋肉にはよくストレッシが行なわれていたのですが上田法では逆のことをします。ただストレッチの逆をすればいいというものではなく、文書では説明しにくいので実地体験をお勧めします。
実際に「上田法」は書籍がなく、実地で体験学習するということを理念としてます。というのも実地体験なく書物による独学で施術し効果がなかった場合、「上田法」を否定されることを懸念されているからだそうです。
ということで方法の詳細は省略しますが、対象となる障害・疾患を列記しておきます。
1.脳性麻痺
2.脳炎後遺症
3.脊髄性けい性麻痺
4.筋の過緊張を伴う運動発達遅滞
5.末端けい性を伴うヒポトニー
6.その他に筋の過緊張を伴う症状の患児
7.脳血管障害の後遺症
鍼灸治療で使用している経穴をいちおう列記しますが「上田法」の理念のようにこれらの経穴を使ったが効果はでなかったということになると鍼灸自体に不信感がでる患者さんもでかねないので、治療成績をあげているベテランの先生に実地で指導を受けることをお勧めします。
頭頚肩部
百会、風池、天柱、肩井、肩外兪、巨骨、肩井、高校、肩りょう、天宗、秉風、
上肢
曲池、手三里、外関、用地、合谷、
腹部
中かん、天枢、大巨、気海、関元、
背腰部
膈兪、脾兪、胃兪、三焦兪、腎兪、小腸兪、
下肢
居りょう、環跳、風市、殷門、足三里、陽陵泉、懸鐘、外承筋、内承筋、崑崙、丘墟
今、ざっと思い浮かぶ経穴を列記しましたがまだまだあると思うので思い出したら更新しますのでチェックしといてください。
頭に刺鍼する「頭鍼療法」をやったことがありますが効果はよくわかりませんでした。
おっと!自分の技量をさておいて否定的なことを書いてはいけませんね。言ったさきから書いてしまった。