OKバジさん(垣見一雅さん)が今年もネパールから帰って来る。
7月18日(水)
回転木馬 3F ガイアスペース(佐倉市王子台3-27-10)
講 演 10:30~12:30 (無料)
交流会 13:00~15:30 参加費 千円 (ネパールカレーとチャイの昼食付き)
主 催 OKさくら
申込み・問合せ 回転木馬 043-489-9618
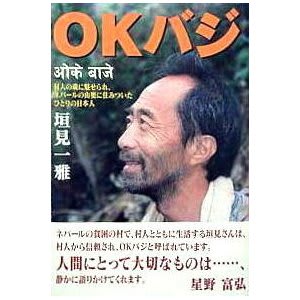
1939年東京生まれ。
早稲田大学卒業後、順心女子学園の英語教師を経て、93年ネパールに渡る。
ヒマラヤ登山中の怪我の介抱をしてくれたシェルパの出身地パルパ県ドリマラ村を根拠地に、19年以上、村人の健康、暮らしなどの支援活動を続けている。
当初、村人たちに頼まれると、何でも「OK,OK」と言っていたところから、「OKバジ(バジはネパール語でおじいさん)」と呼ばれるようになった。
ネパールの雨期(6月から8月)は、日本に滞在して、講演活動で現地の状況を伝えてくれる。
平成21年度吉川英治文化賞受賞
バジさんは山また山を歩いて超えながら、体力の続く限り、大型NGOなどの支援の網から漏れた「声のない村(支援の要望を出さない、出せない村々)」の人々の声を聞き歩き、「生きた支援」を続けている。
支援方法は、村人たちが自立できるよう、自分たちの手でできる事の手助けです。
OKさくらだよりから*********************************
ジャミレ郡ブトゥケ村の米基金が、今年も活躍する時が来ました。
天候不順、水不足などで米の収穫の少ない時、村人たちは米屋からツケで米を買います。
OKさくらが2007年に支援した10万円(当時6万ルピー)を米基金としたことにより、村人は米屋から高い金利で米を買わなくてもすむようになりました。
高い利息が払えずに、ついには農地まで取られてしまうという最悪の事態から救われることになったのです。
米屋に払うはずの利息を村の自己資金にプールする事により、6万ルピーの基金が現在7万5千ルピーにまで増えたことを昨年12月、バジさんがブトゥケ村に行って確認して、写真を送ってくださいました。
ジョラ基金
ネパールには、学校に行けない子どもたちがたくさんいます。
その理由は、裸足で行きたくない、制服がない、ノートとボールペンが買えない、などです。
そこで考えられたのが、ジョラ基金(ジョラとはネパール語で袋やカバンの意味)。
ジョラ基金は、1万円を支援していただければ、これを運用して、その利息が子ども達の支援に充てられます。
1カ月160円あれば、ノートや鉛筆、ボールペンが、また4カ月まとめて支援すれば、制服や通学用のゴム草履も支援できるようになります。
そして元金1万円はずっと子どもたちの奨学金のためのファンドとして、学校あるいは地域のNGOに据え置かれます。
貧しさのため、学校に行けない子どもたちを支援するジョラ基金にご参加ください。
賛同いただける方は「OKさくら」までご連絡ください。
連絡先 043-489-9618 回転木馬
*******************************************
国際貢献というといろいろな方法があるが、バジさんのやり方は村人たちが自分たちでやり遂げられることへの支援で、そこに私たちも参加できる。
バジさんは70歳になる体で、高い山また山を歩いて訪ね、声を聞き、一緒に考える。
そして、その支援がきちんとできたか確認し、報告してくれる。
私もジョラ基金に参加させてもらったが、毎年報告を聞けてうれしい。
7月18日(水)
回転木馬 3F ガイアスペース(佐倉市王子台3-27-10)
講 演 10:30~12:30 (無料)
交流会 13:00~15:30 参加費 千円 (ネパールカレーとチャイの昼食付き)
主 催 OKさくら
申込み・問合せ 回転木馬 043-489-9618
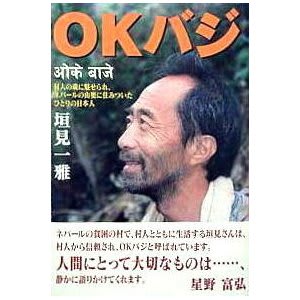
1939年東京生まれ。
早稲田大学卒業後、順心女子学園の英語教師を経て、93年ネパールに渡る。
ヒマラヤ登山中の怪我の介抱をしてくれたシェルパの出身地パルパ県ドリマラ村を根拠地に、19年以上、村人の健康、暮らしなどの支援活動を続けている。
当初、村人たちに頼まれると、何でも「OK,OK」と言っていたところから、「OKバジ(バジはネパール語でおじいさん)」と呼ばれるようになった。
ネパールの雨期(6月から8月)は、日本に滞在して、講演活動で現地の状況を伝えてくれる。
平成21年度吉川英治文化賞受賞
バジさんは山また山を歩いて超えながら、体力の続く限り、大型NGOなどの支援の網から漏れた「声のない村(支援の要望を出さない、出せない村々)」の人々の声を聞き歩き、「生きた支援」を続けている。
支援方法は、村人たちが自立できるよう、自分たちの手でできる事の手助けです。
OKさくらだよりから*********************************
ジャミレ郡ブトゥケ村の米基金が、今年も活躍する時が来ました。
天候不順、水不足などで米の収穫の少ない時、村人たちは米屋からツケで米を買います。
OKさくらが2007年に支援した10万円(当時6万ルピー)を米基金としたことにより、村人は米屋から高い金利で米を買わなくてもすむようになりました。
高い利息が払えずに、ついには農地まで取られてしまうという最悪の事態から救われることになったのです。
米屋に払うはずの利息を村の自己資金にプールする事により、6万ルピーの基金が現在7万5千ルピーにまで増えたことを昨年12月、バジさんがブトゥケ村に行って確認して、写真を送ってくださいました。
ジョラ基金
ネパールには、学校に行けない子どもたちがたくさんいます。
その理由は、裸足で行きたくない、制服がない、ノートとボールペンが買えない、などです。
そこで考えられたのが、ジョラ基金(ジョラとはネパール語で袋やカバンの意味)。
ジョラ基金は、1万円を支援していただければ、これを運用して、その利息が子ども達の支援に充てられます。
1カ月160円あれば、ノートや鉛筆、ボールペンが、また4カ月まとめて支援すれば、制服や通学用のゴム草履も支援できるようになります。
そして元金1万円はずっと子どもたちの奨学金のためのファンドとして、学校あるいは地域のNGOに据え置かれます。
貧しさのため、学校に行けない子どもたちを支援するジョラ基金にご参加ください。
賛同いただける方は「OKさくら」までご連絡ください。
連絡先 043-489-9618 回転木馬
*******************************************
国際貢献というといろいろな方法があるが、バジさんのやり方は村人たちが自分たちでやり遂げられることへの支援で、そこに私たちも参加できる。
バジさんは70歳になる体で、高い山また山を歩いて訪ね、声を聞き、一緒に考える。
そして、その支援がきちんとできたか確認し、報告してくれる。
私もジョラ基金に参加させてもらったが、毎年報告を聞けてうれしい。






































