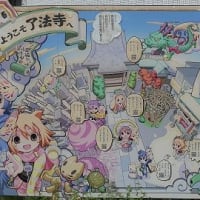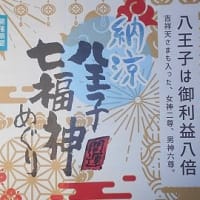追分から次に目指したのは、内藤新宿の仲町に位置する太宗寺。
【太宗寺】

これまた広い境内。そして奥にモダンな本堂。ここも想像していたよりも大きなお寺でした。
太宗寺は浄土宗の寺院で、1596年頃に太宗という僧がこの辺りに建てた草庵「太宗庵」を起源とします。その後、新宿に下屋敷(現在の新宿御苑ですね)を置いた信州高遠藩・内藤家とのつながりを深め、1668年に内藤重頼から寺領の寄進を受け建立されたのが現在の太宗寺とのこと。
【銅造地蔵菩薩坐像】

境内に入って、まず右手に鎮座ましますのが、江戸六地蔵の3番目として、1712年に造立されたお地蔵さん。像の高さは267センチ、六地蔵では小さい方とのことですが、それでも見上げるとじゅうぶんに迫力があります。
ちなみに六地蔵、深川の地蔵坊正元という僧侶が地蔵菩薩に祈願したところ、不治の病が治ったことから造立を思い立ったそうです。太宗寺のほかに、品川寺、東禅寺、真性寺、霊巌寺、永代寺にありましたが、永代寺の地蔵は明治の廃仏毀釈の犠牲となり残っていないそうです。
この六地蔵、五街道のそれぞれ江戸の出口付近に建てられたとか。そういえば品川寺のお地蔵さんは、随分前に偶然に見ていたのでした。
【閻王殿】

境内右手には閻王殿。モダンな本堂に対して、こちらはなんとなく中華風。そしてこの中におわすのが、泣く子も黙る閻魔様。そして妓楼の信仰を集めた奪衣婆像。
中を覗いても真っ暗ですが、扉のボタンを押すと1分間、中の灯りがともります。
【閻王殿の扁額】

江戸末期の中国人官吏の筆によるとか。
【閻魔像】

まずは閻魔様。高さ550センチ!これは迫力満点。1814年に安置されたそうですが、火災や関東大震災などにより、当時のものは頭部のみとのこと。
写真では伝わりにくいかと思いますが、ほんと、見下ろされるというか、迫ってくるというか、そんな感じです。
「内藤新宿のお閻魔さん」として庶民の信仰を集め、1月と7月の16日には縁日が出て賑わったそうです。
1847年には、酔っ払いが閻魔さまの目の玉を取ってしまうという事件が発生して、錦絵にもなったとか。
ちなみにこの不届き者、閻魔さまの目を取った代償に、自分の舌を取られたかどうかは定かではありません…。
【奪衣婆像】

閻魔大王像の左側に安置されています。高さ240センチで、こちらもかなりの迫力ですが、ちょっと見にくい位置にあるのが惜しい。
1870(明治3)年に作られたので、江戸時代にはありませんでした。
奪衣婆とは三途の川を渡る亡者から衣服を剥ぎ取った婆様。衣服を剥ぎ取るということから、妓楼の商売神として信仰を集めたそうです。なるほどね。
コードネームは「しょうづかのばあさん」。
【不動堂】

閻王殿と向かい合うように、境内に入って左手にあります。
お堂の中には、布袋尊像と三日月不動像が安置されています。
【布袋尊像と三日月不動像】

不動堂の中は、暗くて布袋様も不動像もよく見えませんでした。
手前が布袋さん。昭和初期に創設された新宿山の手七福神のひとつです。他のお寺を巡って七福神をコレクションしてみるのも楽しそうです。
ちなみに、新宿山の手七福神のお寺は次の通りです。
・善国寺…毘沙門天
・経王寺…大黒天
・厳島神社…弁財天
・永福寺…福禄寿
・法善寺…寿老人
・太宗寺…布袋和尚
・稲荷鬼王神社…恵比寿神
奥の三日月不動尊はまったく見えませんでした。額の上に銀製の三日月を戴くことから、この名がついたそうです。江戸時代の制作ですが詳細不明とのこと。高尾山へ運ばれる途中、ここで動かなくなり不動堂を建立し安置したとか。
【塩かけ地蔵】

お地蔵さんを覆う白い物質は塩。かなりカチカチになっています。
願掛けの返礼に塩をかける珍しい風習のあるお地蔵様。造立年代や由来については、はっきりしない…と、お寺でいただいたパンフレットには記されています。
このお地蔵様をしげしげと見ていたところ、
「いよ~兄ちゃん、元気?」
と威勢よく声をかけてきたのは、近所の飲み屋のマスター。朝10時前なのに営業中だって。新宿らしい。抜け出してきたのかな?
マスター曰く、
「お賽銭を供えて、ほんのちょこっと塩をいただいて、財布とか持ち物に振り掛けると、悪い奴が寄ってこないんだよ」
とのこと。
私もお賽銭を供えて、ひとつまみ、財布に振り掛けました。
【内藤家墓所】

太宗寺と縁の深い信州高遠藩主・内藤家の墓所です。
中央が5代正勝の墓で、新宿区指定史跡。正勝の時代の内藤家はまだ高遠藩ではなく、安房勝山藩(千葉県)の藩主でした。
正勝、亡くなったときはまだ20代。ここ、太宗寺で葬儀が執り行われました。子の重頼は幼少だったため、いったん、内藤家は大名としては廃絶となります。
その後、成長した重頼は若年寄、大坂城代などを歴任し、晴れて大名に返り咲きました。
めでたしめでたし。
ちなみに、内藤家が信州高遠に転封されたのは重頼の子、清枚(きよかず)のときでした。
【切支丹灯籠】

境内の奥、事務所(?)の建物の前にあります。
内藤家の墓所から出土したそうです。出土したのは竿部分(脚部)で、笠と火袋部は修復して補っているとのこと。
江戸時代中期の制作と推定され、全体の形状が十字架を表し、竿部の彫刻はアリア像だとか…。
さあ、あなたはマリア様に見えますか?
【マリア様?】

内藤家の墓所から出土した…ということは、意図的に埋められた?
内藤家は隠れキリシタンだったのか?
う~ん…埋められていたというのが、なんともミステリアス。しかも大名家の墓所に。
誰か、謎解きをしたひと、いないのかなぁ?
以上、長くなりましたが見どころいっぱいの太宗寺でした。
毎年7月15日・16日には閻王殿の扉が開けられるそうです。間近での閻魔大王と奪衣婆像。見に行ってみようかな…。