【あらすじ】 以下、amazonより引用転載(青字)
ノルウェー北部の田園地方。牧師館で、夫ヴィクトールと静かに暮らすエーヴァ。彼女は7年も会っていない母シャロッテを自宅に招く。世界的ピアニストのシャロッテは老いても美しく華やかだった。
再開した母子、しかしシャロッテはエーヴァから、脳性麻痺の妹ヘレーナが同居している事を知り、ショックを隠せない。夕食後、シャロッテはエーヴァに、ショパンのプレリュードを弾いてみせる。そして夜が更け、エーヴァは幼少から抱き続けた怒りを母にぶつけるのだった。
自分を玩具のように扱い、家族を省みず、駆け落ちしたこと。自分を糾弾する娘に、シャロッテもまた自己の本心を語りだす・・・。
以下、映画評
母と娘の確執を描いている。一人の女性(母)から生まれたもう一人の女性(娘)の感性と性格は、母とは正反対のように映し出されている。だが、会話を聞いていると、親子の本質は同じである。それは自分の感情を胡麻化すことができないという性格。
二人は7年ぶりに会うことになる。再会の契機を作ったのは娘の方だった。娘は過去に受けた苦しみや憎しみの感情を抱きながら、再会することで何らかの現状打破への希望を抱いていた。というか、自分の感情を閉じたまま、そのまま生き続けることが困難だったように思われる。その意味から、勝負に出た。
結果、その行動が憎悪剥き出しのバトルへと繋がっていく。その開始のゴングが鳴り始める。では、その結末はどうなるのだろう?この映画はそれを描いている。が、重い問題を含んでいる。僕は、それについて書いてみたい。映画評というより、その重い問題についての私見として。
ケリのつかない過去の怨念にケリを付けようとする娘。それは親子という立場の違いから生まれる感情の相違ではない。娘が受けた傷は、母親の自己中心的な性格に起因している。悪いのは間違いなく母親の方だ。母親は仕事での成功にしか興味がない。ピアニスト。過去も現在も娘たちの人生には関心がない。母親も自分の感情を胡麻化すことができない。好き勝手に生きているだけ。今風に言えば毒親である。
この映画で語られているような親子の過去の蟠(わだかま)り、そんな物語など、観たくもなかったし、聞かされた人間はタマッタものではない。重すぎて、口出しが出来きないからだ。根が深い。娘の夫の立場がそれにあたる。やんわりと遠くからものを言いうしか術がない。第三者である彼は、己の感情を殺しながら、妻を援護することしかできない。
その立場は、この映画を鑑賞している僕も同様だった。鑑賞していたとき、娘の言っていることは十分にわかった。苦しみもわかった。それらを痛い程理解できた。でも、二人(母と娘)の話していること自体が全く理解できなかったのである。
何故ならば、彼ら双方に自分たちの問題を解決すべきゴールを探ろうという気配がないからだ。過去の出来事に関して口論しているだけなのである。そして、その都度、己の感情を爆発させていくだけだ。そのような行為においては、怒りが新たな怒りの記憶を手繰り寄せ、新たな憎悪を誕生させていく。異なる怒りが重層化されていくだけである。
どうすれば和解できるか、その歩みよりの精神が存在しない。仮に母親が心から詫びても、娘の情念を晴らすことはできない。何故ならば、双方の意識が噛み合わないからだ。だから、実に重苦しい展開をとる。この映画に、僕は段々と戸惑ってしまった。この展開はいつまで続くのだろうか?気分が重くなるだけだ。次第に僕には、この映画を観続ける意欲が減退してきた。
そこで、視点を変えて鑑賞することにした。この重苦しい作品の役者たちの演技をじっくりと観察し、称えることにした。それしか逃げ場はなかった。すると、どうだろう。彼らの演技力に大いに感心するどころか、そこから見えてくるものがあった。それは驚くべき現象だった。僕が経験したあの経験と同じかもしれない。応用できるかもしれない。
見えて来たもの、それは、この手の問題の解決策であった。それが見えてきたのだ。こんなことがあるんだな、、、。いま、それを書こうとしている。
イングリッド・バーグマンの反応は極めて現実的な対応のように見える。演技であってもたぶん彼女のように、人は(このような口論においては)反応するだろう。そう思った。彼女の演技が凄いのは、投げやりで無責任な言動が、彼女の美貌の上に、恐るべき傲慢さを浮上させていくところにあった。美貌さゆえに不満の感情が分離してしていくのである。美貌の女優に浮かび上がる奇妙な表情。僕はそれを受信できたのである。美貌が醜悪に見えた瞬間がある。美しい顔の女性が、恐ろしい程、傲慢で醜い女の顔に変容してしまうのである。なんて不細工な女だ!人の情念は造形美を破壊するほどのパワーが内在しているのだ。
イングリッド・バーグマンの演ずる毒親の様子から、この親子の対立の原因はコミュニケーションの不在にあることがわかって来る。母親においては先天的に(それが)欠陥しているようだ。そのような人間のに見えてくるから、イングリッドバークマンは凄い。社交上、表面的にはそのような欠落はないように見える。彼女は相手の話を聞かないのではない。聞いてはいるのだが、掘り下げて聞けないのである。心を通わせることが出来ない人間なのである。
そのような人格障害が親の方に偏在していると、対話を試みても、関係の蟠(わだかま)りが氷解するどころか、より頑強なものとして変容していくようだ。更に、そのような人間に名声が備わっていれば、傲慢さは拍車をかけていく。一般的に、人は経年に伴いその性格を一層固陋(ころう)させていく。そうなると、益々手に負えなくなるのだ。
悪いのは(この映画では)母親である。間違いない。娘の解釈は経年と共に多様性を増していく。しかし、母親の当時の記憶はかなり減退していて、娘に(それを)指摘されても「責められるている、、」としか、言いようがないのである。
だって、そんなこと、考えてもいなかったことだから。想像もしていなかったことに、踏み込まれていく。そこを(娘に)突かれてしまった。不意を突かれた形となる。この手の支配者(母親)は都合の悪いことを忘れているのではない。そもそもイメージできていないのである。意識がそこに無かったからである。意識の履歴が心に存在していないのである。
しかし、傷を受けた方の人間は、その傷の解釈が多様な解釈を齎していく。恨みや辛みは増強されていく。親との別離している時期(映画では7年間)があったとしても、その期間に生まれたマイナスの感情は受けてきたトラウマに結びつけて考えてしまう。どうしても、そのように反応しまうのである。そんな弱さに人は飲み込まれる。しかし、それは弱さではなく、人間精神の一般的な傾向の一つかもしれない。何かの契機で過去のトラウマが更なるトラウマとして巨大化していくのである。被害者意識が更なる歪んだ解釈を上書きしていくのである。人の記憶とは実は捏造されていくものである。自分のことを考えてみればよい。自分に都合の良い方に解釈しているものだ。
この映画ではそれを解明できない。つまり、娘の誇大解釈かどうかは不明だ。それは一般的な話だ。過去の不幸も幸福も、人は過大解釈してしまうのだ、という一般的な汎用性を活用するなら、完全に毒親だけのせいではなく、娘の問題でもある。
ダークサイドに支配されたトラウマ形成時期から離陸できた時、つまり、別離できていた7年間において、娘は、本当は自身の思考の癖を修正すべきことが必要だったのだ。でも、そんなこと出来やしない。そんなこと理想論である。
そして、僕は感じたのである。このような親子間の情念の対立は、時は何も解決してくれない、、ことが分かってしまった。だから、ハッとしてしまった。自分でも吃驚した。時は何も浄化してくれない。時がたち、この問題を蒸し返すと、全くの逆効果になる可能性もあるわけだ。この映画のように。これはダークサイドである。
家族に潜むダークサイドは、時間では解決しない。それを当人に諭しても何も変わらない。それをこの作品の監督は描いている。しかし、いくら巧みに描いてみても、答えは初めから見えている。いつまで経っても解決などしない。それが答えなのだ。だから、質の悪いテーマを選んだわけだ。
映画の終盤でその答えが明確になされる。イングリッド・バーグマンが吐くセリフがそれを証明している。電車の中でのセリフだ。自分の娘に対して放つ、彼女の辛辣な言葉だ。このシーンは多くの鑑賞者に幻滅を与える。と同時に、母親の本性を暴露させることになる。
つまり、監督もこの問題の限界を深く強く理解しているのである。それでも監督はダークサイドを描いたのである。どうしてだろうか?
親・子という人間関係においては、子供が成人になるまでは、支配と被支配の関係にある。その期間にマイナスの感情として溜まってしまった子供の情念は、時を経ても、ダークサイドとして、いつでもパッくっと口を開けて待っている。
場合によっては、死ぬまで不可解な自己中心的なロジックで子供を支配しようとする毒親が存在している。その可能性を否定できない。無意識のうちに、彼らの想念は支配する立場から離れるようなことはない。できないのである。精神的に支配しないと満足しないのである。そのような親も存在している。彼らは自分の感情を胡麻化せないのである。自己中心的思考。その基盤を破壊されることは死に値するからである。
不幸にしてそのようなトラウマを注がれた子供においては、自分の親とはそのような存在である!と考えることができるようになれば、子供時代に自分が受信したダークサイドな気分を成人してから親に共有させるという強烈な一撃に何ら意味も効果もないことを悟ることは可能だ。何も解決しないのだ。この映画のように。ただ、子供の方で割り切るしかないのだ。
しかし、割り切っても、現実問題としては割り切れないものがあるだろう。
だから、大事なことは、そのダークサイドを蒸し返さないこと。この映画のようなことを行うと、何が起こるのだろうか?ダークサイドを掘り起こし、共有させることで、更に現実の関係は重くなるという構図だ。何も解決しない。この作品はそれを見事に提示して見せている。
何も解決しないと書いたが、諦念(ていねん)することで、ダークサイドな気分は隠れていく。あの人のことは諦めた。昔のことは忘れよう!と、ダークサイドの存在を日々の暮らしから追放することは可能である。人は諦念するスキルを磨くしかないのである。
そう書いて、嘘をつけ!と自分自身に言い放った。それはとても難しい行為だ。そんな簡単なことではない。諦念などできないのである。親子という血のつながりを無視して、しょうがない人間だ、、と諦(あきら)めることは出来ない。自分にもその血が流れていると身震いをしてしまうのである。
処方箋は別の場所にある。全く逆の行為を履行することだ。難しいからこそ、湧き上がる情念から、己の意識をそらしてはならないのである。深く厳しく見つめていく必要がある。記憶を歪曲したり捏造してはならない。詳細まで丁寧に記憶の糸を手繰るのだ。事実を見つめるのだ。
そして、その行為を行う時、たった一つのコツがある。それは、その事実が齎す憤怒や絶望を他人事のように、まるで雲が流れるように揺れる気分を見つめることである。そのトレーニングを繰り返すしかない。それしかないのである。
結果、気分の揺れを見つめることに慣れていくのを待つしかない。ああ、また揺れているな、、、そう感じられたら、免疫が出来た証拠である。次第に我慢できるようになる。そのスキルを習得するしか術はないのである。
これは応用は効く。例えば、会社での人間関係や日常生活の小さなイザコザに伴う憤怒から、身を守ることができる。理不尽な言動から生ずる怒りの感情をしっかりと見つめるのである。ただし、流れていく雲の風景として観察していくのである。不愉快な人間、波長の合わない人間に対して活用することで、自身の感情を保全できる。後は、レベルの問題だ。僕が昔使えた上司はモンスターのような男だった。権力を握り、パワハラ全開だった。その苦しい期間において、僕はこのスキルを身につけられるようになったのだ。
毒親に育てられても豊かな人格を作り上げることのできた人間も多いそうだ。であれば、彼らを知ることで、楽になれるかもしれない。しかし、そのような人物を身近に探すことは不可能だ。であれば、自分の境遇のレベルを比較し安堵できるもの(自分の方がましだ!という作品)を探すべきである。例えば、この映画がそのサンプルとして象徴的なものとなるだろう。
現実的に、家庭のダークサイドを抱えているならば、現実の辛さもこの映画をその視座でみることで、気分を濾過(ろか)できるハズだ。
想念や情念のコントロールの仕方も、行動力の一つだと言える。何も外に向かって動くことが行動力ではない。スポーツ選手が行うイメージ・トレーニングと同様、情念のコントロールを行うことも優れた行動力の一つである。同じ場所(気分)で悩むのではなく、解決するためには、イメージを変えることが行動することにつながる。
 |
秋のソナタ [DVD] |
| イングリッド・バーグマン,リブ・ウルマン,レーナ・ニイマン | |
| 紀伊國屋書店 |
映画でも小説でも、人間関係のトラブルのようなものを見せてくれる作品は、僕らに優れた何かを教えてくれる。だから、そのように解釈して、この映画を鑑賞すれば良いのではないだろうか。ヒントは身の回りに沢山潜んでいる。希望を失わないことだ。
評価;☆☆☆☆☆











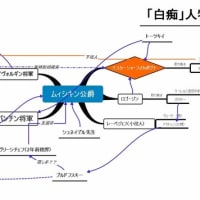
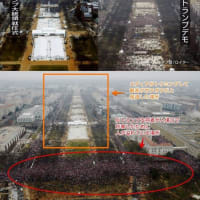













※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます