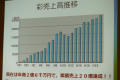こんばんは、木村ながとです。今日は簡単なご連絡のみです。
今日(9月27日)から江戸川区議会第三回定例会が始まりました。本日の本会議では、補正予算案や条例改正案などの各議案や、来週から始まる決算特別委員会で審議される報告案件たる22年度決算が、それぞれ議会に上程されました。
9月28日は議事整理日のため、本会議はありません。そして、29日と30日にかけて各会派、各議員より執行部(行政)に対する一般質問が行われます。
私も9月30日(金)に一般質問に立ちます。昨日、一般質問の通告を議会事務局に正式に行いました。
当日の時間についてですが、午後1時より複数議員が順次質問してまいりますので、私の質問が始まる時間は流動的です。おそらく3時前後からではないかと思われますが、何ともお約束はできません。私の持ち時間は24分(行政側の答弁時間は含まれません)です。
質問内容は放射線対策に関することです。放射線対策の改善を基軸とし、①予防原則による対応、②砂場の放射線測定、③学校給食をめぐる課題、などのポイントについて質問をしていく予定です。詳細は金曜日以降、順次お伝えしてまいります。
先週より原稿を執筆開始し、いま推敲を重ねているところです。前日までさらに原稿を練り上げたいと思います。
江戸川区議会議員 木村ながと
公式HP http://www5f.biglobe.ne.jp/~knagato-gikai/
ブログ http://blog.goo.ne.jp/knagato1/
ツイッター http://twitter.com/#!/NagatoKimura
今日(9月27日)から江戸川区議会第三回定例会が始まりました。本日の本会議では、補正予算案や条例改正案などの各議案や、来週から始まる決算特別委員会で審議される報告案件たる22年度決算が、それぞれ議会に上程されました。
9月28日は議事整理日のため、本会議はありません。そして、29日と30日にかけて各会派、各議員より執行部(行政)に対する一般質問が行われます。
私も9月30日(金)に一般質問に立ちます。昨日、一般質問の通告を議会事務局に正式に行いました。
当日の時間についてですが、午後1時より複数議員が順次質問してまいりますので、私の質問が始まる時間は流動的です。おそらく3時前後からではないかと思われますが、何ともお約束はできません。私の持ち時間は24分(行政側の答弁時間は含まれません)です。
質問内容は放射線対策に関することです。放射線対策の改善を基軸とし、①予防原則による対応、②砂場の放射線測定、③学校給食をめぐる課題、などのポイントについて質問をしていく予定です。詳細は金曜日以降、順次お伝えしてまいります。
先週より原稿を執筆開始し、いま推敲を重ねているところです。前日までさらに原稿を練り上げたいと思います。
江戸川区議会議員 木村ながと
公式HP http://www5f.biglobe.ne.jp/~knagato-gikai/
ブログ http://blog.goo.ne.jp/knagato1/
ツイッター http://twitter.com/#!/NagatoKimura