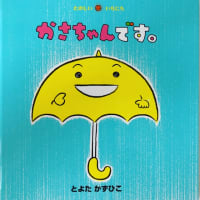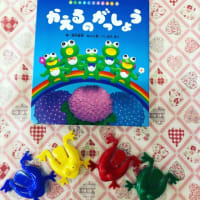「噛みつき」と「自我の芽生え」の関係性
噛みつきが起こる年齢は、一般的に1歳から2歳半頃と言われています。この頃になると、自我の芽生えが出るためです。
“自我の芽生え”とは一体何なのでしょうか?
赤ちゃんの頃は、他人に物を取られても怒ったり泣いたりはしません。成長と共に、“自分と他人”という意識が出てきて、自分の物に対して執着するようになります。
これがいわゆる“自我の芽生え”です。
1~2歳児は、自我が出始めたけれど、まだ言葉で思いを伝えることができません。
そのため、“噛む、叩く”など最も早く伝わる方法で自己主張をします。
手を出してしまった子どもは、とっさの行動で悪気があるわけではないのです。
「噛みつきをする子」の家庭のしつけ特徴と予防策って?
shutterstock_119084974
source:http://www.shutterstock.com/
“噛みつき”などのトラブルを減らすためには、実は“家庭での対応”というのがとても重要です。
おうちでは、子ども中心になっていることが多くありませんか?
赤ちゃんの時はそれで良くても、自我が出てきたら“子ども中心生活”からは卒業しましょう。
子どもがやりたいことを全て思い通りにしてあげていると、子ども同士のコミュニケーションがいつまでたってもうまくできない子になってしまいます。
ママが使っているものを勝手に取ろうとした時などには、「今は使っているから待ってね」ということをきちんと伝えてあげましょう。
“家庭ではわがままを言ってもOK”、“保育園では我慢しなければダメ”という使い分けは子どもには無理です。
絶対にしてはいけないNGしつけ法は?
それは“後から叱る”です。
保育園のお迎えの際、「今日は、お友だちを噛んでしまいました」と保育士から聞いたとしても、そこで叱ることは厳禁。
子どもは、噛んだ時のことを覚えていないため、何に対して叱られているかを理解できず、同じことを繰り返してしまいます。
逆に、もしも噛まれてしまった場合には、「可哀想に」ということを何度も繰り返し子どもに言うことは避けましょう。
噛まれることへの恐怖心が消えず、お友だちと一緒に遊ぶことができなくなってしまうかもしれません。
噛んでしまう子、噛まれてしまう子、どちらのママも不安な思いでいっぱいになることでしょう。
でも、このようなトラブルは子どもが自分の気持ちを言葉で伝えられるようになれば自然となくなります。
大切なのは、成長段階の一つだとママが理解をし、子どもの気持ちをくみ取ってあげることです。
子どもとたくさん会話ができるようになるのもあと少し。あまり神経質にならずに、その日を楽しみに待っていてあげてくださいね。
噛みつきが起こる年齢は、一般的に1歳から2歳半頃と言われています。この頃になると、自我の芽生えが出るためです。
“自我の芽生え”とは一体何なのでしょうか?
赤ちゃんの頃は、他人に物を取られても怒ったり泣いたりはしません。成長と共に、“自分と他人”という意識が出てきて、自分の物に対して執着するようになります。
これがいわゆる“自我の芽生え”です。
1~2歳児は、自我が出始めたけれど、まだ言葉で思いを伝えることができません。
そのため、“噛む、叩く”など最も早く伝わる方法で自己主張をします。
手を出してしまった子どもは、とっさの行動で悪気があるわけではないのです。
「噛みつきをする子」の家庭のしつけ特徴と予防策って?
shutterstock_119084974
source:http://www.shutterstock.com/
“噛みつき”などのトラブルを減らすためには、実は“家庭での対応”というのがとても重要です。
おうちでは、子ども中心になっていることが多くありませんか?
赤ちゃんの時はそれで良くても、自我が出てきたら“子ども中心生活”からは卒業しましょう。
子どもがやりたいことを全て思い通りにしてあげていると、子ども同士のコミュニケーションがいつまでたってもうまくできない子になってしまいます。
ママが使っているものを勝手に取ろうとした時などには、「今は使っているから待ってね」ということをきちんと伝えてあげましょう。
“家庭ではわがままを言ってもOK”、“保育園では我慢しなければダメ”という使い分けは子どもには無理です。
絶対にしてはいけないNGしつけ法は?
それは“後から叱る”です。
保育園のお迎えの際、「今日は、お友だちを噛んでしまいました」と保育士から聞いたとしても、そこで叱ることは厳禁。
子どもは、噛んだ時のことを覚えていないため、何に対して叱られているかを理解できず、同じことを繰り返してしまいます。
逆に、もしも噛まれてしまった場合には、「可哀想に」ということを何度も繰り返し子どもに言うことは避けましょう。
噛まれることへの恐怖心が消えず、お友だちと一緒に遊ぶことができなくなってしまうかもしれません。
噛んでしまう子、噛まれてしまう子、どちらのママも不安な思いでいっぱいになることでしょう。
でも、このようなトラブルは子どもが自分の気持ちを言葉で伝えられるようになれば自然となくなります。
大切なのは、成長段階の一つだとママが理解をし、子どもの気持ちをくみ取ってあげることです。
子どもとたくさん会話ができるようになるのもあと少し。あまり神経質にならずに、その日を楽しみに待っていてあげてくださいね。