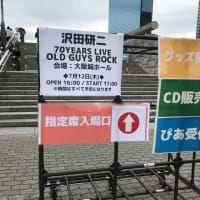御扇子
民踊だけど・・・団扇だけではなく御扇子も使う(-"-) ← 長さは通常29センチ程。

市丸姐さんのように艶っぽく扱えるようにまでは成れないだろうけれど
でも、少しは近づきたい
大丈夫なのか私???? 棘の道を突き進んでいるような気もするが…
御扇子にも色々とあるけれど

本来涼を取るための道具だけど
礼(儀式)や舞の際に用いることがある。
扇には、持ち方や置き方など色々な作法がある。
中啓・・・半開きの状態で作られた扇。
開いて使用することはない。
(道成寺「どうじょうじ」 や汐汲「しおくみ」、文屋「ぶんや」 などの能取物、
能から派生した演目で用いられる)
夏扇・・・朱色が主に用いられるので朱扇「しゅせん」とも呼ぶ。
普通の扇のように開くが、涼を取るためではない。
檜扇・・・「ひせん」とも呼ぶ。
檜の薄板を重ねて白絹糸で綴じ、白糸の両端に房をたらした扇。
雪洞・・・中啓の開きをさらに半分にした形をしている。
【舞扇は舞踊の小道具】
舞扇「まいおうぎ」とは、
日本舞踊や能楽・詩吟において舞を際立たせる小道具。
手に持って踊ったり、また仕舞・素踊などの際に、
本来の舞台において使われる小道具の代りとして用いられる扇子。
室町時代以降に、主に舞踊用として発展したほか、
全国各地の祭礼や民謡(盆踊り)、ダンス・ミュージカルやセレモニーなど様々な場面に登場。
日本人に安らぎと華やかさを与えるとともに、美意識の象徴(シンボル)として
最も親しまれている伝統工芸品の1つ。
【錘を入れてバランスを…】
舞扇の親骨の根元には、指で親骨をつまみ、
廻したり、上にかざしたり、
胸前で決めたりする要返し「かなめがえし」や扇を飛ばしたりする時に
バランスを良くし扱いやすくするために、
鉛の錘「おもり」が埋め込んである。
【骨(親骨・中骨)について】
舞扇の骨は、通常10本で、素材は竹や木を用いてる。
表面に何も塗らず竹の素材感を生かした白(竹)骨、シックで高級感のある黒漆の黒骨、
朱漆を塗ったエレガントで華やかな朱骨、燻した竹を使用し素朴で落ち着いた感じのする煤骨「すすぼね」、
琥珀色のニスを塗り艶やかな輝きを湛えた古典調のタメ骨のほか、
これらを組み合わせたコンビ骨などがある。
少し勉強しないと私ッ…