部屋を整理していたら、昔同人誌に書いたものが出てきた。出てきてしまったのでここにアップしておくことにした。文字遣いなど一部訂正しているが基本的にそのまま。
昔、とっても潔癖だったわたしには、光源氏の恋愛に対する態度がふまじめにみえてしかたがなかった。複数の恋愛を同時進行させることなどではない。「形代の恋」というやつだ。
本当に好きな女性は手の届かないところにいるので身代わりで我慢する、というパターンが源氏物語には繰り返し出てくる。これは偶然ではあるまい、紫式部には何かそういったコンプレックスがあったのかな、と思っていた。もちろん、個人的コンプレックスに原因を求めるのではなんの解答にもならない。
それについては、一応納得のいく説明を見つけた。
藤壺女御は、じつは、多くの男性に慕われながらも、手の届かない世界に去ってしまう古物語の女主人公を受け継いだものである。(中略) 紫上の創造はこういう物語の型を破ったのである。型は当初は秩序として存在する。しかしそれは制約と化すこともある。藤壺女御の創造はその型を生かし、紫上の創造はその制約を破ったものであったといえよう。つまり、作者は、藤壺女御と生き写しの紫上を登場させることより(ママ)、あこがれの追求を現実の中に求めたのである。そして古代人たちが、むしろあきらめることによって解決しようとしたことに対していどんだのである。
昇天するかぐや姫から、「わたしは貴方の青春の幻影……」などと呟くメーテルに至るまで、理想的女性が永遠へと去ってしまう話は無数に語られている。むしろ、去ることによって理想の女性であることを示しているといった方がいいかもしれない。手にとることのできぬものこそ、最もよく渇きを癒すことができる。現実のものとして手に入れたとたん、色あせてしまう。では憧れを憧れのまま手に入れるにはどうすればいいのか。
現実の中にそのレプリカを置いてみよう。――源氏物語はそういった実験をしたのだろうか。
では、恣意的になるかもしれないが、「形代の恋」を軸に物語をまとめてみる。
[桐壺帝の場合]
熱愛していた桐壺更衣は光源氏を産んだ後、死去。
帝は更衣そっくりの藤壺女御を入内させる。
藤壺女御は光源氏と通じて冷泉帝を産み、帝亡き後、出家。
[光源氏の場合]
源氏は藤壺女御こそ理想の女性だと思っている。
藤壺女御に似た紫上を見出し、妻とする。彼女は源氏の正妻として扱われるが、女三宮降嫁によりその座を追われる。源氏との間には溝ができ、やがて病死。
一方、女三宮は柏木と通じて薫を産み、出家。
[薫の場合]
薫が恋慕した宇治の八宮の大君は彼を拒絶、死去。
薫は大君に似た浮舟(大君の異母妹)を宇治に隠し置く。そこへ薫を装った匂宮が訪れ浮舟と契る。浮舟は入水を決意するが失敗、出家。
いずれの場合にも、理想の女性の代わりによく似た女性を妻としている。これが「形代の恋」である。
ところで、繰り返されるパターンはその他にもう一つある。「女君の裏切り」である。
裏切りというのは、単に情交や心を移すことだけをいうのではないだろうが(※1)桐壺帝や薫の場合は特に異論はでないものと思う。
光源氏の場合、紫上には裏切りはない。その必然性がないからだ。彼女は藤壺女御と肩を並べるほどの理想的女性であるのだから、そう簡単に過ちを犯すはずはない。藤壺女御の場合には、光源氏という特別な人物が相手だという必然性があった。紫上にはそれもない。 そこへ登場するのが、紫上の地位にとってかわる女三宮である。そもそも紫上というのは、「紫のゆかり」(藤壺女御に縁の深い女性)ということでつけられた名だが、女三宮もまた「紫のゆかり」なのである(紫上は藤壺女御の兄の娘。女三宮は藤壺女御の妹の娘)。また、彼女たちは二人とも幼くして源氏のもとへやってくる。そのときの二人を比較して、同じあどけないとはいっても紫上の方が相手のしがいもあったよなあ、などと源氏は思っている。そういったことから女三宮は紫上の――より劣った―― 分身と考えられないだろうか。彼女たちは二人で一人であり、女三宮はその中でも心弱い部分を表している。そしてその女三宮は、源氏ではなく柏木の息子を産んでいる。
以上のことを考えにいれてパターンをまとめてみる。
一、理想の女性とは運命的に(死、公的立場)隔てられている。
二、男君は理想の女性の面影を現実の女性の上に求める。
三、女君は彼を裏切り他の男の息子を産む。
四、女君は出家する。
では、なぜ女君は裏切るのだろうか。
そーんなのあたりまえじゃない、誰かの身代わりとしてしか見てない奴に縛られてれば浮気くらいしたくなるわよォ、という意見を彼女たちが持っていたとは考えにくい。彼女たちは出家するからだ。なぜ彼女たちは他の男のもとに走らなかったのか。
もし彼女たちが去った先が俗世界の男のところならば、取り戻すことは可能である。しかし仏の世界では取り返しがつかない。現実の女性も理想の女性と同じく、永遠へと去ってしまうのだ。ただ、現実の女性はより意識的に去っているといえる。理想の女性との隔たりの理由は死であり、父帝の女御という立場であり、運命的なものといっていい。それに対して現実の女性は密通の結果ほかのおとこの息子を産み、彼女自身の意志により出家する。
男君は理想の女性をあらかじめ失っており、さらにその形代にも去られる。それは女君の責任とばかりはいえない。二度めの失恋はその恋愛に内在しているからだ。密通という具体的事実がなくても、現実の女性は常に男君を裏切っている。彼は現実の女性を通して理想の女性を愛しているのだから。どんなに似ていても、彼女は理想の女性とは別の人間だ。つまり彼女は彼女であることで、彼女でしかないことで、彼を裏切りつづけている。
二度の失恋は、同じ対象に対する、けれど異なった失恋だ。はじめから手に入らないものよりも、一度は確実に手に入れたと思ったものを失うことの方が痛手だろう。
もう一度、より確実に失うために形代の恋はある。憧れの対象を現実の中に求めるということは、それを手に入れることは不可能だということを確認することなのだ。
ここまで書いてきて、わたしはひどく平凡な結論に達したようだ。人々は望ましいものの獲得よりも喪失の物語を好む。少なくとも文学的だと思っている。けれど、本当に? 好きな人といつまでも仲良く暮らしました、という陳腐な幸福はそれほど軽蔑すべきものだろうか。
※1 これを書いた当時、わたしは「女君の裏切り」とは、嫡出子として男子を(他の男との間に)産むこと、ではないかと考えていた。
男たちは、娘に自らの将来を、息子に自らの未来を託す。自分という社会的存在を、時間を越えてその先へつなげてくれるのは正統の男子だ(女子は、たとえば時の帝に入内するなどの形で自分の将来を保証してくれる)。そんなふうに生きている男たちにとって、未来を不安にされるのはさぞ怖ろしいことだろう。
昔、とっても潔癖だったわたしには、光源氏の恋愛に対する態度がふまじめにみえてしかたがなかった。複数の恋愛を同時進行させることなどではない。「形代の恋」というやつだ。
本当に好きな女性は手の届かないところにいるので身代わりで我慢する、というパターンが源氏物語には繰り返し出てくる。これは偶然ではあるまい、紫式部には何かそういったコンプレックスがあったのかな、と思っていた。もちろん、個人的コンプレックスに原因を求めるのではなんの解答にもならない。
それについては、一応納得のいく説明を見つけた。
藤壺女御は、じつは、多くの男性に慕われながらも、手の届かない世界に去ってしまう古物語の女主人公を受け継いだものである。(中略) 紫上の創造はこういう物語の型を破ったのである。型は当初は秩序として存在する。しかしそれは制約と化すこともある。藤壺女御の創造はその型を生かし、紫上の創造はその制約を破ったものであったといえよう。つまり、作者は、藤壺女御と生き写しの紫上を登場させることより(ママ)、あこがれの追求を現実の中に求めたのである。そして古代人たちが、むしろあきらめることによって解決しようとしたことに対していどんだのである。
昇天するかぐや姫から、「わたしは貴方の青春の幻影……」などと呟くメーテルに至るまで、理想的女性が永遠へと去ってしまう話は無数に語られている。むしろ、去ることによって理想の女性であることを示しているといった方がいいかもしれない。手にとることのできぬものこそ、最もよく渇きを癒すことができる。現実のものとして手に入れたとたん、色あせてしまう。では憧れを憧れのまま手に入れるにはどうすればいいのか。
現実の中にそのレプリカを置いてみよう。――源氏物語はそういった実験をしたのだろうか。
では、恣意的になるかもしれないが、「形代の恋」を軸に物語をまとめてみる。
[桐壺帝の場合]
熱愛していた桐壺更衣は光源氏を産んだ後、死去。
帝は更衣そっくりの藤壺女御を入内させる。
藤壺女御は光源氏と通じて冷泉帝を産み、帝亡き後、出家。
[光源氏の場合]
源氏は藤壺女御こそ理想の女性だと思っている。
藤壺女御に似た紫上を見出し、妻とする。彼女は源氏の正妻として扱われるが、女三宮降嫁によりその座を追われる。源氏との間には溝ができ、やがて病死。
一方、女三宮は柏木と通じて薫を産み、出家。
[薫の場合]
薫が恋慕した宇治の八宮の大君は彼を拒絶、死去。
薫は大君に似た浮舟(大君の異母妹)を宇治に隠し置く。そこへ薫を装った匂宮が訪れ浮舟と契る。浮舟は入水を決意するが失敗、出家。
いずれの場合にも、理想の女性の代わりによく似た女性を妻としている。これが「形代の恋」である。
ところで、繰り返されるパターンはその他にもう一つある。「女君の裏切り」である。
裏切りというのは、単に情交や心を移すことだけをいうのではないだろうが(※1)桐壺帝や薫の場合は特に異論はでないものと思う。
光源氏の場合、紫上には裏切りはない。その必然性がないからだ。彼女は藤壺女御と肩を並べるほどの理想的女性であるのだから、そう簡単に過ちを犯すはずはない。藤壺女御の場合には、光源氏という特別な人物が相手だという必然性があった。紫上にはそれもない。 そこへ登場するのが、紫上の地位にとってかわる女三宮である。そもそも紫上というのは、「紫のゆかり」(藤壺女御に縁の深い女性)ということでつけられた名だが、女三宮もまた「紫のゆかり」なのである(紫上は藤壺女御の兄の娘。女三宮は藤壺女御の妹の娘)。また、彼女たちは二人とも幼くして源氏のもとへやってくる。そのときの二人を比較して、同じあどけないとはいっても紫上の方が相手のしがいもあったよなあ、などと源氏は思っている。そういったことから女三宮は紫上の――より劣った―― 分身と考えられないだろうか。彼女たちは二人で一人であり、女三宮はその中でも心弱い部分を表している。そしてその女三宮は、源氏ではなく柏木の息子を産んでいる。
以上のことを考えにいれてパターンをまとめてみる。
一、理想の女性とは運命的に(死、公的立場)隔てられている。
二、男君は理想の女性の面影を現実の女性の上に求める。
三、女君は彼を裏切り他の男の息子を産む。
四、女君は出家する。
では、なぜ女君は裏切るのだろうか。
そーんなのあたりまえじゃない、誰かの身代わりとしてしか見てない奴に縛られてれば浮気くらいしたくなるわよォ、という意見を彼女たちが持っていたとは考えにくい。彼女たちは出家するからだ。なぜ彼女たちは他の男のもとに走らなかったのか。
もし彼女たちが去った先が俗世界の男のところならば、取り戻すことは可能である。しかし仏の世界では取り返しがつかない。現実の女性も理想の女性と同じく、永遠へと去ってしまうのだ。ただ、現実の女性はより意識的に去っているといえる。理想の女性との隔たりの理由は死であり、父帝の女御という立場であり、運命的なものといっていい。それに対して現実の女性は密通の結果ほかのおとこの息子を産み、彼女自身の意志により出家する。
男君は理想の女性をあらかじめ失っており、さらにその形代にも去られる。それは女君の責任とばかりはいえない。二度めの失恋はその恋愛に内在しているからだ。密通という具体的事実がなくても、現実の女性は常に男君を裏切っている。彼は現実の女性を通して理想の女性を愛しているのだから。どんなに似ていても、彼女は理想の女性とは別の人間だ。つまり彼女は彼女であることで、彼女でしかないことで、彼を裏切りつづけている。
二度の失恋は、同じ対象に対する、けれど異なった失恋だ。はじめから手に入らないものよりも、一度は確実に手に入れたと思ったものを失うことの方が痛手だろう。
もう一度、より確実に失うために形代の恋はある。憧れの対象を現実の中に求めるということは、それを手に入れることは不可能だということを確認することなのだ。
ここまで書いてきて、わたしはひどく平凡な結論に達したようだ。人々は望ましいものの獲得よりも喪失の物語を好む。少なくとも文学的だと思っている。けれど、本当に? 好きな人といつまでも仲良く暮らしました、という陳腐な幸福はそれほど軽蔑すべきものだろうか。
※1 これを書いた当時、わたしは「女君の裏切り」とは、嫡出子として男子を(他の男との間に)産むこと、ではないかと考えていた。
男たちは、娘に自らの将来を、息子に自らの未来を託す。自分という社会的存在を、時間を越えてその先へつなげてくれるのは正統の男子だ(女子は、たとえば時の帝に入内するなどの形で自分の将来を保証してくれる)。そんなふうに生きている男たちにとって、未来を不安にされるのはさぞ怖ろしいことだろう。










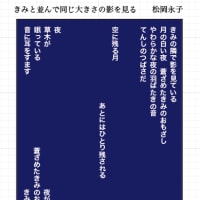
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます