平松混声合唱団 第38回定期演奏会 ~未来につなぐ~
昨日、2023/5/30(火)19:00~於東京文化会館小ホールでの、ヒラコン定期演奏会に参加しました。1年前の、昨年5月のヒラコン創立40周年記念演奏会にも参加したが、今回も素晴らしい演奏内容を堪能し、感動し、晩春の一宵を楽しく過ごすことができた。とりわけ今回は上演種目に、宮沢賢治“星めぐりの歌”があり、先ずソリストが舞台前に出てこの歌に込められた賢治先生の心象世界の解説をしたが、それがとてもよかった。賢治先生の病弱の妹としこに込めた思いは、いかがなものだったか、合唱を聞いているうちに、賢治先生の銀河鉄道の心象の世界の中へ吸い込まれていく思いであった。演奏会の冒頭に指揮者平松剛一先生が、ウクライナの戦争だけでなく、最近の内外・世界の混乱とギスギスした状況に思いをいたし、それだからこそ今“心に響く歌”が必要なんだとコメントしたが、全く同感で、ホールを埋め尽くした多くの参加聴衆の心に響いた。都立三田高校のOGで私が担任したこともある、この合唱団ではソプラノ担当の馬場理江さんが、毎回演奏会チケット送ってくれるので、参加できるこを感謝してる。馬場さんは更に円熟向上だが、押しも押されぬプロ演奏集団としてのヒラコンの一員として、今後の更なる飛躍発展を願ってる次第である。
話の視点は変わるが、いつも思うことだが、文化会館小ホールの音響は素晴らしい。側面・上面ともコンクリートに覆われたホールにしては、響きのよいホールである。プロが造ったわけで、当然と言えば当然だが、あれだけの音がよく出るものだと、いつも思う。上演中はホール内撮影は厳禁なので、開演前に撮影したが、構造は丁度ホーンスピーカーの構造に似てる。聴衆は、早い時間で
未だガラガラで埋まってないが、画像を示す。

ホーンスピーカーと言えば、高城重躬先生を思い出す。我が国オーデイオ界の第一人者で、というよりオーデイオのレジェンドというか伝説的な人物で、かつ数学教師・ピアニスト・収集家等々、多彩な活躍した。ピアニストとしてもNHKなどマスコミで活躍し、NHKFMのクラシック音楽番組「ハイフアイタイム」その後は「ハイフアイアワー」名の番組のナレーターとしても、5年間活躍した。実は、数学教師と書いたが、高城重躬先生は都立三田高校と切っても切れない関係にある。三田高校に、前身の第六高女に赴任したのが戦前の1936年であったから、戦後1988年離任まで、あしかけ28年間在任した三田を代表する先生である。私も、高城先生がわかば会(第六高女と三田高校の同窓会)総会に、1990年代だったが来られた時に、一度だけお会いしたことがある。あれほど教養と知性を感じさせる、本物の紳士は少ない印象であった。戦前・戦後の三田に、足かけ28年間在職だから、その他音楽界・オーデイオ界にまつわる先生の話題は尽きないが、詳しいのは先生の著書『音の遍歴』(1974,共同通信社)に譲るとして、先生とホーンスピーカーの関わりについて、一言だけコメントする。高城先生は、自らピアノ演奏だけでなく、音の忠実な再生に誇張でなく人生をかけたような人であった。低音部、中・高音部を忠実に再生するホーンスピーカーに、悪戦苦闘したわけである。先生は、様々な試行錯誤のうちに、最後は自宅新築に際して、自宅自体をホーンスピーカーに組み込むような形状の家を設計し、建築した。画像は、コンクリートぶち込みのその様子である。

高城先生が、文化会館小ホールの音響について、どうコメントするか、聞いてまたかった。
馬場理江さん、平松剛一先生、高城重躬先生、宮沢賢治先生、花からすっかり青葉溢れる上野での晩春の一宵は、素晴らしい時間であった。
昨日、2023/5/30(火)19:00~於東京文化会館小ホールでの、ヒラコン定期演奏会に参加しました。1年前の、昨年5月のヒラコン創立40周年記念演奏会にも参加したが、今回も素晴らしい演奏内容を堪能し、感動し、晩春の一宵を楽しく過ごすことができた。とりわけ今回は上演種目に、宮沢賢治“星めぐりの歌”があり、先ずソリストが舞台前に出てこの歌に込められた賢治先生の心象世界の解説をしたが、それがとてもよかった。賢治先生の病弱の妹としこに込めた思いは、いかがなものだったか、合唱を聞いているうちに、賢治先生の銀河鉄道の心象の世界の中へ吸い込まれていく思いであった。演奏会の冒頭に指揮者平松剛一先生が、ウクライナの戦争だけでなく、最近の内外・世界の混乱とギスギスした状況に思いをいたし、それだからこそ今“心に響く歌”が必要なんだとコメントしたが、全く同感で、ホールを埋め尽くした多くの参加聴衆の心に響いた。都立三田高校のOGで私が担任したこともある、この合唱団ではソプラノ担当の馬場理江さんが、毎回演奏会チケット送ってくれるので、参加できるこを感謝してる。馬場さんは更に円熟向上だが、押しも押されぬプロ演奏集団としてのヒラコンの一員として、今後の更なる飛躍発展を願ってる次第である。
話の視点は変わるが、いつも思うことだが、文化会館小ホールの音響は素晴らしい。側面・上面ともコンクリートに覆われたホールにしては、響きのよいホールである。プロが造ったわけで、当然と言えば当然だが、あれだけの音がよく出るものだと、いつも思う。上演中はホール内撮影は厳禁なので、開演前に撮影したが、構造は丁度ホーンスピーカーの構造に似てる。聴衆は、早い時間で
未だガラガラで埋まってないが、画像を示す。

ホーンスピーカーと言えば、高城重躬先生を思い出す。我が国オーデイオ界の第一人者で、というよりオーデイオのレジェンドというか伝説的な人物で、かつ数学教師・ピアニスト・収集家等々、多彩な活躍した。ピアニストとしてもNHKなどマスコミで活躍し、NHKFMのクラシック音楽番組「ハイフアイタイム」その後は「ハイフアイアワー」名の番組のナレーターとしても、5年間活躍した。実は、数学教師と書いたが、高城重躬先生は都立三田高校と切っても切れない関係にある。三田高校に、前身の第六高女に赴任したのが戦前の1936年であったから、戦後1988年離任まで、あしかけ28年間在任した三田を代表する先生である。私も、高城先生がわかば会(第六高女と三田高校の同窓会)総会に、1990年代だったが来られた時に、一度だけお会いしたことがある。あれほど教養と知性を感じさせる、本物の紳士は少ない印象であった。戦前・戦後の三田に、足かけ28年間在職だから、その他音楽界・オーデイオ界にまつわる先生の話題は尽きないが、詳しいのは先生の著書『音の遍歴』(1974,共同通信社)に譲るとして、先生とホーンスピーカーの関わりについて、一言だけコメントする。高城先生は、自らピアノ演奏だけでなく、音の忠実な再生に誇張でなく人生をかけたような人であった。低音部、中・高音部を忠実に再生するホーンスピーカーに、悪戦苦闘したわけである。先生は、様々な試行錯誤のうちに、最後は自宅新築に際して、自宅自体をホーンスピーカーに組み込むような形状の家を設計し、建築した。画像は、コンクリートぶち込みのその様子である。

高城先生が、文化会館小ホールの音響について、どうコメントするか、聞いてまたかった。
馬場理江さん、平松剛一先生、高城重躬先生、宮沢賢治先生、花からすっかり青葉溢れる上野での晩春の一宵は、素晴らしい時間であった。













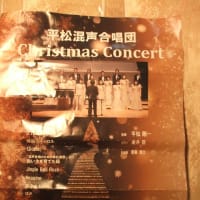










※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます