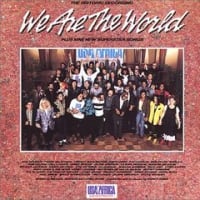ついに終わりそうでなかなか終わらないこのブログも再開後二回目の更新です。自分は休み時間をとるのが下手なので、これを書くことで気分転換(休み)にしたいという思いもあり、今日も書いています。
3・11東北関東大震災の直後は、僕が住む東京でさえ二次災害を受けていた。それは米やパンのカップラーメン、、ミネラルウォーター、電池などの不足、計画停電、また一時的ではあったが今住んでいる三鷹市でも乳児には水道水を飲ませるのを控えるように指示が出された。が、今振り返っても(やっと振り返れるくらいになったということか。ここ数日は東京では余震もないように思える)一番受けた影響は、あのテレビ絶え間なく流れている被災地の惨状を見続けたことにより受けた精神的ショックであった。もちろん阪神大震災、米ニューオーリンズの津波被害の映像も見ていたが、それを上回る重さ、あれはきっと東京も当日長く揺れたことと、その夜の交通機関のストップから始まる二次災害を受けていたことが視角に加えて、環境的にも揺り動かされたことが響いたゆえだろう。思えば特に四月に入ってからは、僕の場合大学院生活がスタートしたため、そちらの授業準備、事務手続き等で期限との闘いに入ったので、いくらかの余震でも不安になっていられないという状態で四月いっぱい走っていたため、以前ほどは震災について心配もできず、そしてGWは長野の実家に行っていたため、こうしてGW以後になってみて初めて冷静に震災について振り返っているのを感じている。
震災後、ネットや雑誌で著名人・識者の様々な寄稿文を読んだ。村上龍、ビートたけし、山折哲雄(宗教学者)、細川護煕(元総理)。村上龍のものは、僕が彼のファンだということもあるが特にインパクトがあったので、またどこかで話すか書くことになると思うが、今日ここで取り上げたいのは山折哲雄氏がAERAのたしか4/4号だったかな、そこに書いてあった寄稿文について。
美容院で髪を切っていただいている時に読んだものなので、手元に今それ自身が無いので記憶でたどるしかないが、宗教学者の視点で書かれているだけあって(おそらく彼は神道)、仏教的な視点やキリスト教的な視点それぞれから今回の震災と被災者に対する見方を記してあった。僕はクリスチャンであるので、クリスチャンではない視点で、山折氏がキリスト教的視点においても語っておられるところが、非常に客観的な内容であり、すべて同意できるわけではなかったが、頷かされるところが多々あり、目を開かされる内容であった。
さて、そこで山折氏が強調していたのは、日本人はこういう災害に強いということ、その理由は日本人には古来より「無常」「無常観」というものが精神構造のベースになっており、キリスト教のように「救い」をもたらそうとか「解決」をもたらそうとせず、その厳しいあるがままの震災の状況を、大きな自然の現象として、いわば、いた仕方ないもの、それと共存して生きていこうとするという現状と環境に対する無常観がいい意味で作用しているのではないか、という意味のことが書かれていたと記憶している。克明にはここで記せないが。そのわけは、災害後の被災者の?避難所の?人々の様子が、しばらく前に津波被害にあった米ニューオーリンズの様子と、今回の東北の人々との様子が違っていたところから、日本とアメリカ(キリスト教が強い国)の精神的・宗教的ベースの違いがそれに影響しているのだろう、ということを述べており、かつ、だから日本人のこのような時の強さ(=いたずらに解決のみを求めない、現状を受け入れる強さ)についてを今回の被災と我らが日本に対する励ましのメッセージとして書かれていたと思う。なんとかあの記事手に入れたいとは思っているが。
この山折氏による寄稿文については、今も述べたが、頷かされるところもあった。またこの記事については、思いがけず、僕の属する東京神学大学大学院1年のクラスの、年度始めの懇談会(担任教授二名同席)においても僕のほか担任教授の一人からも触れられ、山折氏とは違う理解でのコメントがなされた。おそらく僕のようなキリスト者でさえ、その記事に目が留ったのだから、多くの日本人であの記事を読んだ方は共感されるところが多かったのではないだろうか。ただし、実際の被災者の方々はあの記事をどう思うだろうか。たとえば、ご家族をこの震災で亡くされた方はどうだろうか。無常観はある部分確かに力にはなるだろう。復興まであとどのくらい時間がかかるのかわからないが、これを乗り越えたときに、やはり日本は強かった、となるのだろうか。それはそれで悪いことではなく、むしろ誇れることかもしれない。しかしそれが今回壊され、痛んでしまった建物や必要な物資や、社会システム(経済、学校等)が回復していくことのみであったら、壊されたものを作り直したのにすぎず、そこでまたいつか崩れることがあったらどうすれば良いのか。また無常観に立ち返るのだろうか。
細川護煕元総理が、先月半ばの朝日新聞の中のインタビューで22世紀、23世紀を見据えての、新しい日本の国づくりを価値観の再構築からも論じていたかと記憶の中にあるが、価値観の再構築ということになると、それは今あるものを元通りにすることが単に復興なのではなく、建物や物資や、社会システムは人間がどんなにがんばっても崩されることがあり、その崩された時でさえも、私たちが立ち行いていくことのできる価値観、別の言い方で言えば幸福観、が必要であるということだと思う。無常観に優る希望をもしわれわれが持てたとしたら、その時に起こる私たちの絆はどんなにか強いだろうか。しかし「これこれこうなったら幸福である」という”幸福の条件”の中で私たちが生きていくとしたら、その幸福はおそらくいつか崩れてしまうことになり、そのときにその絆はどこまで残るだろうか。目に見える現世利益的な幸福感にはどうしても限界がある。無常観も確かに助けになる部分もあるとは思う。
ただ幸福とは、目に見える状態がいい時を表すのでも、苦しみがあったらそれを受け入れていくーというだけでもなく、それに優るもの、いつもそこに変わらない安心感があるものなのではないだろうか。人はそんな幸福を求めて生きているのではないだろうかー。そんなことを考えて、また自分も学んでいきたいと思います。今日はここまで。
3・11東北関東大震災の直後は、僕が住む東京でさえ二次災害を受けていた。それは米やパンのカップラーメン、、ミネラルウォーター、電池などの不足、計画停電、また一時的ではあったが今住んでいる三鷹市でも乳児には水道水を飲ませるのを控えるように指示が出された。が、今振り返っても(やっと振り返れるくらいになったということか。ここ数日は東京では余震もないように思える)一番受けた影響は、あのテレビ絶え間なく流れている被災地の惨状を見続けたことにより受けた精神的ショックであった。もちろん阪神大震災、米ニューオーリンズの津波被害の映像も見ていたが、それを上回る重さ、あれはきっと東京も当日長く揺れたことと、その夜の交通機関のストップから始まる二次災害を受けていたことが視角に加えて、環境的にも揺り動かされたことが響いたゆえだろう。思えば特に四月に入ってからは、僕の場合大学院生活がスタートしたため、そちらの授業準備、事務手続き等で期限との闘いに入ったので、いくらかの余震でも不安になっていられないという状態で四月いっぱい走っていたため、以前ほどは震災について心配もできず、そしてGWは長野の実家に行っていたため、こうしてGW以後になってみて初めて冷静に震災について振り返っているのを感じている。
震災後、ネットや雑誌で著名人・識者の様々な寄稿文を読んだ。村上龍、ビートたけし、山折哲雄(宗教学者)、細川護煕(元総理)。村上龍のものは、僕が彼のファンだということもあるが特にインパクトがあったので、またどこかで話すか書くことになると思うが、今日ここで取り上げたいのは山折哲雄氏がAERAのたしか4/4号だったかな、そこに書いてあった寄稿文について。
美容院で髪を切っていただいている時に読んだものなので、手元に今それ自身が無いので記憶でたどるしかないが、宗教学者の視点で書かれているだけあって(おそらく彼は神道)、仏教的な視点やキリスト教的な視点それぞれから今回の震災と被災者に対する見方を記してあった。僕はクリスチャンであるので、クリスチャンではない視点で、山折氏がキリスト教的視点においても語っておられるところが、非常に客観的な内容であり、すべて同意できるわけではなかったが、頷かされるところが多々あり、目を開かされる内容であった。
さて、そこで山折氏が強調していたのは、日本人はこういう災害に強いということ、その理由は日本人には古来より「無常」「無常観」というものが精神構造のベースになっており、キリスト教のように「救い」をもたらそうとか「解決」をもたらそうとせず、その厳しいあるがままの震災の状況を、大きな自然の現象として、いわば、いた仕方ないもの、それと共存して生きていこうとするという現状と環境に対する無常観がいい意味で作用しているのではないか、という意味のことが書かれていたと記憶している。克明にはここで記せないが。そのわけは、災害後の被災者の?避難所の?人々の様子が、しばらく前に津波被害にあった米ニューオーリンズの様子と、今回の東北の人々との様子が違っていたところから、日本とアメリカ(キリスト教が強い国)の精神的・宗教的ベースの違いがそれに影響しているのだろう、ということを述べており、かつ、だから日本人のこのような時の強さ(=いたずらに解決のみを求めない、現状を受け入れる強さ)についてを今回の被災と我らが日本に対する励ましのメッセージとして書かれていたと思う。なんとかあの記事手に入れたいとは思っているが。
この山折氏による寄稿文については、今も述べたが、頷かされるところもあった。またこの記事については、思いがけず、僕の属する東京神学大学大学院1年のクラスの、年度始めの懇談会(担任教授二名同席)においても僕のほか担任教授の一人からも触れられ、山折氏とは違う理解でのコメントがなされた。おそらく僕のようなキリスト者でさえ、その記事に目が留ったのだから、多くの日本人であの記事を読んだ方は共感されるところが多かったのではないだろうか。ただし、実際の被災者の方々はあの記事をどう思うだろうか。たとえば、ご家族をこの震災で亡くされた方はどうだろうか。無常観はある部分確かに力にはなるだろう。復興まであとどのくらい時間がかかるのかわからないが、これを乗り越えたときに、やはり日本は強かった、となるのだろうか。それはそれで悪いことではなく、むしろ誇れることかもしれない。しかしそれが今回壊され、痛んでしまった建物や必要な物資や、社会システム(経済、学校等)が回復していくことのみであったら、壊されたものを作り直したのにすぎず、そこでまたいつか崩れることがあったらどうすれば良いのか。また無常観に立ち返るのだろうか。
細川護煕元総理が、先月半ばの朝日新聞の中のインタビューで22世紀、23世紀を見据えての、新しい日本の国づくりを価値観の再構築からも論じていたかと記憶の中にあるが、価値観の再構築ということになると、それは今あるものを元通りにすることが単に復興なのではなく、建物や物資や、社会システムは人間がどんなにがんばっても崩されることがあり、その崩された時でさえも、私たちが立ち行いていくことのできる価値観、別の言い方で言えば幸福観、が必要であるということだと思う。無常観に優る希望をもしわれわれが持てたとしたら、その時に起こる私たちの絆はどんなにか強いだろうか。しかし「これこれこうなったら幸福である」という”幸福の条件”の中で私たちが生きていくとしたら、その幸福はおそらくいつか崩れてしまうことになり、そのときにその絆はどこまで残るだろうか。目に見える現世利益的な幸福感にはどうしても限界がある。無常観も確かに助けになる部分もあるとは思う。
ただ幸福とは、目に見える状態がいい時を表すのでも、苦しみがあったらそれを受け入れていくーというだけでもなく、それに優るもの、いつもそこに変わらない安心感があるものなのではないだろうか。人はそんな幸福を求めて生きているのではないだろうかー。そんなことを考えて、また自分も学んでいきたいと思います。今日はここまで。
けいぞうツイッターはこちら→ http://twitter.com/keizzo
(関心のあるジャンル↓ にクリックお願いします。ブログアクセスランキングに反映されます。)
にほんブログ村 エッセイ・随筆
にほんブログ村 ロック
にほんブログ村 キリスト教・クリスチャン
![]() (←こちらもクリックよろしくお願いします。別ランキングに反映されます。)
(←こちらもクリックよろしくお願いします。別ランキングに反映されます。)