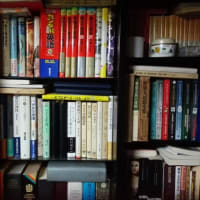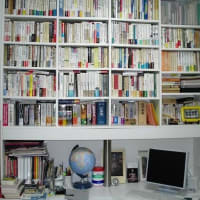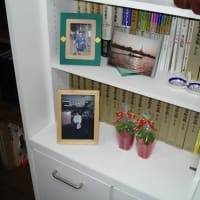今回のテーマは「省略」「挿入」「同格」。これらはすべてセンテンス内部の語順ルールの<例外のパターン>です。しかし、語の配列の<例外>ではあるが、それらはパターン化されている<ルール>であり、いつどこで誰が使用したとも一義的にセンテンスの意味内容が確定する語の配列のルール、畢竟、英文法体系の一部なのです。具体的に例文で確認してみましょう。
When young, Ms. Shimokitazawa traveled the US from coast to coast on business.
(若い時、下北沢さんはアメリカ中を仕事で旅行した)
Kyotodaisukihime, a 21-year-old college student, won the Seiron Prize for her first article published last year.(京都大好き姫は、21才の大学生だが、昨年出版された初めての論文で正論大賞を受賞した)
Vanille-san watched " Nausicaa of the Valley of Wind ", that is, one of the masterpieces of Hayao Miyazaki.(バニューさんは『風の谷のナウシカ』、つまり宮崎駿の傑作の1つを見た)
最初の例文は、When (she was) young, ・・・と、主節(=Ms. Shimokitazawa traveled the US・・・)と同じ主語とbe 動詞が省略されています。「When, While, 等が導く時間や条件を表す副詞節の中では、副詞節(=従属節)の主語が主節と同じ場合、主語とbe動詞は省略される」のです。目に見えねども西方浄土におわします阿弥陀如来が人々を極楽浄土に招いておられるのと似ていますね。
二番目の例文では、a 21-year-old college studentという主語をより詳しく説明する挿入句が組み込まれています。挿入句のポイントは、挿入句はあくまで「S→V→・・・」構造による語の配列の<例外>ですから、「ここからここまでは例外ですよぉー」という標識として挿入句は必ずカンマとカンマで区切られなければならないこと。
尚、英語や日本語等の自然言語(a natural language)の場合、ピリオド・カンマ・セミコロン等の記号や文字はなんらかの音声の反映ですから、「挿入句はカンマとカンマで区切られる」ということは挿入句の場合、カンマがないセンテンスに比べればカンマの箇所に微妙な音と音の間隔がある。ちなみに、ピリオド・カンマ・セミコロン・コロン・括弧等々の使い方のルールのことをパンクチュエーション言いますが、パンクチュエーションについては下記の記事を参照してください。
・再出発の英文法:パンクチュエーション
最後の例文は、「S→V→・・・」構造の目的語である" Nausicaa of the Valley of Wind "と同じ意味のone of the masterpieces of Hayao Miyazaki という語句が挿入されています。この同じ意味の言葉が続いていることを「同格」関係と言います。阿弥陀如来・大日如来・観世音菩薩等々数多の御仏がどれも一つの仏性の顕現であることを想起されればこのことはイメージしやすいのではないかと思います。
而して、「同格関係にある言葉(同じ意味を表す言葉)が後ろに続きますよ」という標識としてthat is(to say)(すなわち)という関係節から派生した接続副詞句が挿入句の前に更に挿入されている。ここでも二つの挿入句の前後(後方の挿入句の尻尾はピリオド)はカンマで区切られていることに注意してください。尚、二番目の例文の挿入句a 21-year-old college studentも主語のKyotodaisukihimeと「同格関係にある言葉」だったのです。

◆言葉の経済:省略・挿入・同格
言葉を話すこと書くことは人間にとって一大作業なのかもしれません。よって、あらゆる自然言語ではその意味が理解可能である限りより経済的な方向に向かう傾向がある。あのプロ市民の親玉である本多勝一氏が紹介したことで有名な、
どさ?
ゆさ!
は「どこに行っているの?」「銭湯に行ってるのさ!」の経済的変化ですし、世界一短い書簡のやり取りとして有名な、
?
!
も「私が書いた本の売り上げはどんな具合ですか?」「大評判で飛ぶように売れています!」の究極的な経済的変容と言えるでしょう。そして、この言語における経済性というのは音声面でも言えることなのです。英語教師が良く使う下の2例は、すべて「より低いエネルギー」を「より短い時間」使用して発声できる形態に変化しているものです。
A cup of tea:ア カップ オブ ティー → カパティー
Water:ワータァー → ワラー/ワダー
このような「言語はその意味が不明確でない範囲で経済的に変化する」ことが一般的に観察されるのは、しかし、(電報が極特殊な用途のものを除けばe-メールにとって変わられた現在)英字新聞に使われる文体だと思います。例えば、
Tokyo shrine a focus of fury around Asia
は、(A) Tokyo shrine (is going to become) a focus of fury around Asia.(東京のある神社がアジア中の怒りの焦点になりつつある)の経済的変化を受けたもので、一般的に(特に、その記事タイトルにおいては)意味が通じる限り、冠詞とbe動詞は省略されるのが英字新聞の原則と考えてもよいくらいです。尚、英語の音声面の特徴に関しては下記拙稿を参照してください。
・続・英語の正体を知ると少しは気が楽になるかも (音としての英語編)
・続々・英語の正体を知ると少しは気が楽になるかも (英語の音の特徴編)
自然言語ではその意味が理解可能である限りより経済的な方向に向かう傾向があり、「省略」「挿入」「同格」は英語におけるこの経済的変化の代表的パターンと言えると思います。仏像や名号、お題目というものが膨大な『大蔵経』に込められた釈迦牟尼や原始仏教の哲理のエッセンスを凝縮したものであることと「省略」「挿入」「同格」の役割はパラレルなのかもしれません。

◆省略
省略は文字通り語句の使用を節約することです。大切なことは、自分自身や極親しい人にだけ意味が通じるのであればどのような省略も可能であるけれど、英文法でいう所の「省略」はいつどこで誰が使用したとも一義的にセンテンスの意味内容が確定するものでなければならないこと。例えば、
Ai Otsuka.
という「センテンス」は、私や私とパートナーの寛子さんの間では「大塚愛ちゃんのベストアルバムを小田急線新百合ヶ丘駅前のヨーカー堂3階の山野楽器店で次の土曜日に購入すること」という意味を持つかもしれませんが、”Ai Otsuka.”のセンテンスがいつどこで誰が使用したとも一義的な意味内容を持つとは到底言えないでしょうし、土台、多くの人にとっては”Ai Otsuka.”は「S→V→・・・」構造を持つ「大文字から始まりピリオド・疑問符・吃驚マークまでの単語列」としての英語のセンテンスでさえない。
このことを念頭に置いた場合、英文法のルールとしての省略には3種類のパターンがある。そう考えることができる。すなわち、
(甲)文法的省略
(乙)語法的省略
(丙)修辞的省略
これらの用語は(他に使用しておられる方がおられるかもしれませんが)私が独自に考案したものですので、その定義を簡単に書いておきます。
畢竟、文法的省略とは「誰がそのセンテンスを作成しても、通常、省略が生じるケース」。語法的省略は「省略が許されるケースであり、省略するかしないかはそのセンテンスを作成している作者の自由裁量に任せられているケース」。そして、修辞的省略とは「センテンスの意味は多少不明瞭になるものの、そのコンテクストでは省略が間違いとはされないケース」です。
(甲)文法的省略:
【例】命令文の主語の省略・分詞構文の意味上の主語の省略・関係代名詞whatの先行詞の省略
Do it! (やっちまえ!:命令文の主語「You」の省略)
I don’t know what he wants to do.(彼がしようとしていることなど知らない:先行詞の省略)
(乙)語法的省略:
【例】関係詞や関係詞の先行詞の省略・仮定法におけるifの省略・副詞節の「主語+be 動詞」の省略
Ms. Matsumoto is not the woman (that)she once was.
(松本金属工業さんは昔の彼女ではない:関係節で補語になっている関係代名詞の省略)
(丙)修辞的省略:
【例】英字新聞における冠詞とbe 動詞の省略
(President)Kennedy (has been)shot.(ケネディー大統領狙撃される)
これらのポイントを例題を通して説明しましょう。
▼例題1:
< > for his help, we wouldn’t understand the situation.
(A)It was not
(B)Was it not
(C)It were not
(D)Were it not
訳:彼の助けなしでは、我々は状況を把握することなどとてもできない。
正解:(D)
説明:括弧の空欄の直後に前置詞の for がありますから、「If it were not for ~」「~がないとすれば」という定番の表現をご存知であれば簡単な問題なはず。ところが選択肢にはforを従える「If it were not」がない。そこで、仮定法の条件節では「Ifを省略した場合には必ず倒置が起こる」ことを思い出しましょう。よって、正解は Were it notの(D)。而して、この倒置は次のような言語の経済的変化の結果なのです。
復元された正式のセンテンス:
If it were not for your help, we wouldn’t understand the situation.
↓
Ifの省略:(この段階では文法的に間違ったセンテンス)
It were not for your help, we wouldn’t understand the situation.
↓
Ifの省略に伴い「主語→述語動詞」が「述語動詞→主語」と倒置した正しい英語のセンテンス
Were it not for his help, we wouldn’t understand the situation
▼例題2:
Though < >, I will finish this work today.
(A)tired
(B)is tired
(C)be tired
(D)I tired
訳: 疲れているけれどこの仕事は今日中に終らせてみせますよぉー。
正解:(A)
説明: 副詞節(thoughが導く節)では「主語+be動詞」が省略可能です。ただ、この場合、主節と従属節の主語が同じでなければならず、また「主語」か「be動詞」のいずれか一つだけが省略されることはなく、必ず、「主語+be動詞」のセットで省略されます。
◆挿入と同格
挿入と同格は、英語の文型、つまり、語順のルール(=「S→V→・・・」構造)を壊すことなくより詳しい説明をそのセンテンスの中の語句に加える、修正された語順のルールなのです。逆に言えば、というか白黒はっきり言えば、それは、「S→V→・・・」構造に変更を加える例外規定と言ってもよいでしょう。
挿入と同格は、文型構造に変更を加える例外規定
Milk-san was born and raised in the city of Obihiro, one of the most beautiful cities in Japan.
(みるくさんは、日本でも最も美しい街である帯広市で生まれ育った)
このセンテンスのthe city of Obihiroは、the cityとObihiroは同格関係にあり、また、カンマで区切られた挿入句のone of the most beautiful cities in Japanもまたthe city of Obihiroをより詳しく説明してはいるものの the city of Obihiroと同じことを述べている語句、つまり、the city of Obihiroと同格関係にあります。
ここでof の用法を確認しておきます。特に、冠詞がからむ場合、「同格の関係」と「部分-全体の関係」は混同しやすいので、この機会に前置詞のof のポイントを押さえておきましょう。本当、「定冠詞、あるのとないのと大違い」なのです。
the city of London (ロンドン市:同格)
the City of London(ロンドン市の一部たるシティー:部分-全体)
the love of God (神の愛、神から与えられる愛:Godは意味上の主語)
love of God (神への愛、神への献身的な帰依:Godは意味上の目的語)
冒頭で取り上げた例、Kyotodaisukihime, a 21-year-old college student, および" Nausicaa of the Valley of Wind ", that is, one of the masterpieces of Hayao Miyazakiや上のthe city of Obihiro, one of the most beautiful cities in Japanでも明らかなように挿入にはセンテンス内部のある語句と同格関係にある語句を挿入する用法と、そうではなく、全く別の感想や情報を加える用法があります。
これまた私の造語ですが、前者を同格的挿入、後者を修辞的挿入の二種類の挿入が区別できるわけです。これらを区別する(意識する実益)としては修辞的挿入はより文学的表現手法であり、ビジネス文書や学術論文の作成の際には「ここぞ」という所に限定して使う自己規制の目安になること。
例えば、「その時、空飛ぶカエルさんは八戸の青空を見上げた」というセンテンスを「麻生太郎前幹事長が新幹線の事故で八戸での講演会をキャンセルされたというニュースを耳にした時」を加えて「その時、麻生太郎前幹事長が新幹線の事故で八戸での講演会をキャンセルされたというニュースを耳にした時、空飛ぶカエルさんは八戸の青空を見上げた」とするのは曖昧ではないでしょうが、「その時、人生万事塞翁が馬、空飛ぶカエルさんは八戸の青空を見上げた、青い空白い雲」と変えるのは(少なくない読者にとって)些か鼻につく書き換えではないでしょうか。
他方、同格にはカンマとカンマで区切られた挿入句による同格表現(=同格的挿入)とthe city of Londonあるいは接続詞のthat等を使用した同格表現があります。後者は、限定修飾を流用した同格表現と呼ぶのが適切だと思います。以下、挿入と同格について例題を一緒に解いていくなかで理解を深めましょう。
【挿入】
・同格的挿入
・修辞的挿入
【同格】
・同格的挿入
・限定修飾を流用した同格表現
▼例題3:
Everyone knows the fact < > the minister, Minister of Health, Labour and Welfare, is trying to conceal the scandal.
(A) that
(B) which
(C) that is
(D) what
訳:その大臣、厚生労働大臣がスキャンダルを隠そうとしていることは周知の事実だ。
正解:(A)
説明:括弧の空欄以下は「S→V→・・・」構造のセンテンスとして文法的に成立しており、空欄には同格の that が必要。他の選択肢は関係代名詞としても疑問代名詞としても意味をなさない。逆に、conceal のあとに目的語がなければ(B)の関係詞whichが正解にりますが、その場合、復元された問題文、”Everyone knows the fact which the minister, Minister of Health, Labour and Welfare, is trying to conceal the scandal.”は「その大臣、厚生労働大臣が隠そうとしている、正にその事実は広く知れ渡っている」という意味になります。
尚、”the minister”と “Minister of Health, Labour and Welfare”は同格関係。“Minister of Health, Labour and Welfare”は挿入的同格の適例でしょう。挿入句がカンマとカンマで区切られていることを確認してください。
▼例題4:
She has kept the habit < > in the morning since she quit smoking at age 36.
(A) to jog
(B) jogging
(C) jog
(D) of jogging
訳:彼女は36才で禁煙して以来、朝のジョギングの習慣を続けている。
正解:(D)
説明:動名詞を使った同格表現です。 habit の同格表現は「名詞 + of + ~ing」の形になります。他に「名詞 + to 不定詞」で同格を表す場合もありますが、動名詞型と不定詞型のそれぞれで併用される名詞が決まっており、これは頻出ではないけれどTOEICにも出題される論点です。尚、前者の名詞はhabitの他に、 idea, difficulty, dreamなど、後者は desire, plan, hope など。
尚、「quit+動名詞」で「~をやめる」という意味、また、quitはretireとともに「会社などを辞める」(quit her job, retire from a company )はTOEICの最頻出ボキャブラリーです、いずれもこの機会に覚えましょう。
▼例題5:
According to "Defense of Japan White Paper," the Japan Self-Defense Force, Japanese Army, Navy, and Air Force, < > to set up the use of the PATRIOT Advanced Capability-3 System over the next three years.
(A) was
(B) were
(C) is
(D) are
訳:『防衛白書』によれば、日本の陸海空の三軍である自衛隊は、向こう3年以内にパトリオットPAC-3(パトリオット能力発展第3段階型)の運用を強化することになっています。
正解:(C)
説明:挿入句を使った同格表現です。ポイントは同格関係にある二つの項の単複が異なること。例えば、サッカー女子日本代表という単数の「なでしこジャパン」を主語にして、11名のスタメン選手名を挿入句で羅列することも可能です。その要素が例文のように三者(陸上自衛隊・海上自衛隊・航空自衛隊)であれ「なでしこジャパン」のように11人であれ、主語がそれら諸要素が観念の中で統合された単一体である単数の名詞なら、その主語にに対応する述語動詞(be動詞)は三人称単数を受ける is になることに注意しましょう。
尚、この例文であれば、文末の the next three yearsの前を空欄にして適当な前置詞を選ばせるパターンもTOEICではありえます。at, by は特定のある時点を表し、aboutは「ある時点の前後に」という意味なので、「向こう3年間で」という文意に沿うのはoverのみです。ちなみに、in (the next) three yearsは「3年後に」ですが、overとの違いは微妙でありTOEICの選択肢にover とin が同時に挙げられることは今までなかったと思います。冒頭のaccording to は「~によれば」と情報源を明示する挿入句。according to自体は難易度はそう高くはないのですが、逆に、必須のイデオム。もし、自信のない方はこの機会に覚えちゃいましょう。