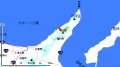毎年この季節に楽しみにしていることがある。
秋の魚、そう「秋刀魚」である。
一人暮らしの私が自宅で焼くことはないので、スーパーで焼いたものを
買ってくるか、外の定食屋で食すことになる。
フレッシュネスバーガーと同系列の定食屋「おはち」のウェッブサイト
をチェックして、秋の新メニューでさんま定食が始まっていることを知っていた。
早速買い物に出かけたついでに代々木の「おはち」に行った。
おはちのページ
味わった感想は最高!
これから毎週食べることにしよう。
私は秋刀魚を食べるのが得意で、ぐちゃっとしたところも皮も全部平らげる。
食べた後は実にきれいに骨と頭だけが残るのだ。
大戸屋はまだ始まっていないようだが、始まったら是非食べ比べてみよう。
貧相な楽しみと思われるかもしれないが、最近そうでもないと四季を実感する機会
は少ないのではないか。
スーパーに行くと四季いつでも手に入るものがほとんどだ。
秋を感じられるサンマは貴重になりつつあるのではないか。
と書いていてもう一つ秋から食べられる海産物があることを思い出した。
「牡蠣」である。
牡蠣はRがつく月に食べられるといわれている、と昔美味しんぼという漫画で
読んだ。(septembeR - apRil)
美味しいうちに食べられる間はせいぜい楽しむことにしましょう。
秋の魚、そう「秋刀魚」である。
一人暮らしの私が自宅で焼くことはないので、スーパーで焼いたものを
買ってくるか、外の定食屋で食すことになる。
フレッシュネスバーガーと同系列の定食屋「おはち」のウェッブサイト
をチェックして、秋の新メニューでさんま定食が始まっていることを知っていた。
早速買い物に出かけたついでに代々木の「おはち」に行った。
おはちのページ
味わった感想は最高!
これから毎週食べることにしよう。
私は秋刀魚を食べるのが得意で、ぐちゃっとしたところも皮も全部平らげる。
食べた後は実にきれいに骨と頭だけが残るのだ。
大戸屋はまだ始まっていないようだが、始まったら是非食べ比べてみよう。
貧相な楽しみと思われるかもしれないが、最近そうでもないと四季を実感する機会
は少ないのではないか。
スーパーに行くと四季いつでも手に入るものがほとんどだ。
秋を感じられるサンマは貴重になりつつあるのではないか。
と書いていてもう一つ秋から食べられる海産物があることを思い出した。
「牡蠣」である。
牡蠣はRがつく月に食べられるといわれている、と昔美味しんぼという漫画で
読んだ。(septembeR - apRil)
美味しいうちに食べられる間はせいぜい楽しむことにしましょう。