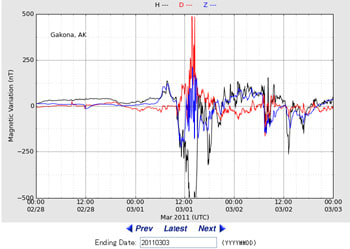久しぶりの投稿になります.このところ多忙でどうしょうもないです(^^;
それはさておき,VoIP無線を始めたときにこしらえた社団局や女房の免許が2回目の再免許時期にさしかかっています.一部は電波を出すことがほとんどないので,再免許しませんでした.その一部の社団局は,運用するような余裕ができたら新規に免許申請しようと思っています。その関係で,気になっていたのが一部で話題になっている新スプリアス規定です.結論から言えば、比較的新しい無線機じゃないと今までどおりの手続きでは免許されなくなるという規制です.
ちょっと調べてみました.
ウンチクやら策定趣旨は別として,免許制度上の実務的な面に着目してみねと...
● 平成19年11月30日以前に製造された無線設備(無線機)については、その使用期限は平成29年11月30日まで(それ以降は保証認定で免許)
● 平成19年11月30日以前に製造された無線設備(無線機)で新規開局もしくは変更の手続きをおこなう場合には、平成29年11月30日までは、「当該無線機が平成19年11月30日までに製造されている無線設備である旨を明記して」申請をおこなう(経過措置)
● 再免許(免許の更新)の場合は今のところ従来通り
ということだそうです.情報ソースはこのサイトです→http://www.jarl.or.jp/Japanese/2_Joho/2-2_Regulation/20070903.htm
■ 新規に局免許をオロスときや変更申請のとき,H.19.11.30以前に製造された無線機で申請するには?
その,平成19年11月30日以前に製造されたかどうかなんて無線機には書いてないので,判断が難しいのですが,一応,それを調べるサービスが総務省のサイトにあったので,それで判断すると面倒なことにはならないようです.許可するかしないか決めるのは役所の仕事ですから・・・ 以下それを意識して臨む手順です.
1) 工事設計欄に書く無線機の技術基準適合証明番号(技適番号)を根拠に平成19年11月30日までに製造された無線機かどうか調べる
総務省の検索サイト( http://www.tele.soumu.go.jp/giteki/SearchServlet?pageID=js01 )で技適番号だけを入力して検索するといつ技適を取ったのかわかります.
例えば,平成19年11月30日以前に製造された旧スプリアス規定の製品だと,検索結果の「スプリアス規定」の覧に「※印」が付されます.
※印が付された検索結果例→ FT-857DM(旧) ※印がない例→ FT-857DM(新)
ここに「※印」が付されなければ新スプリアス規定に沿って設計された無線機と判断して,そのまま工事設計欄に技適番号を書くだけでOKと考えられます.
余談ですが,メーカーでもこのあたりを意識して技適番号をWebに載せています( 八重洲無線 ・ アイコム ).
2) 工事設計欄に書く無線機が平成19年11月30日までに製造された無線機だったとき
申請書の備考欄に当該無線機が「平成19年11月30日までに製造された無線機である」旨を記入すればOKだそうです.自分の場合,事項書の備考欄(15.)に「第n送信機,第m送信機は平成19年11月30日までに製造された無線機です.」と申請書に書くことになりそうです.ただしこれも平成29年11月30日(Xデー)までに行う新規開局,無線機入れ替えなどの変更申請に限る期限付きです.この調子だと,Xデー以降の再免許申請も古い無線機が含まれているとすんなりとはいかないような気がします.
■ 平成29年11月30日以降の申請はどうなる?
その後はどうなるかは,ロビイ活動や関係各所の動きしだいという感じでしょうか.でも制度の趣旨からいって,スプリアスの関係なのでアマチュアだけが例外というのも考えにくいような? しかも国際的な取り決めとのことです.その証拠にXデーのちょうど5年後の平成34年12月1日以降は旧スプリアス規制の無線機は改良してそれを証明しないと使い続けることはできないと総務省が発表してしまっています.このような経過措置になったこと自体,ありがたいことかもしれません.
「Xデー」を迎えたときには,TSS(株)による保証認定制度でと発表されていますが,策定趣旨からすれば,送信部が新スプリアス基準の関係をクリアすることを保証しなければならないと思うわけで,TSSがOKを出しそうなレベルの一定の対策(改造)を自ら行って写真か何かでそれを証明するか,メーカーに対策を依頼して対策済みの書類を得るなどして保証してもらう,なんてことを想像してしまいます.このあたり,どうなのか,謎です.
なんにせよ,古い業務無線機やパーソナル無線機なんて,容赦なく産業廃棄物になっていきますから,自己解決の道が開かれていること自体,唯一「アマチュア無線」だけに許された解決策ということでポジティブに考えたいものです.
以上,メモ的な内容でしたが参考までにて.