










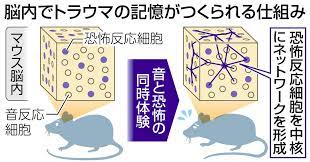

iPS細胞移植後に2人の運動機能が改善、脊髄損傷患者が自分で食事をとれるように…世界初
3/21(金) 17:05配信
https://news.yahoo.co.jp/articles/d0ee22b11e96202f5213bda4bf59c71cc2220bf4

313
コメント313件

読売新聞オンライン
慶応大などの研究チームは21日、脊髄損傷で体がまひした患者4人にiPS細胞(人工多能性幹細胞)から作製した細胞を移植した世界初の臨床研究で、2人の運動機能が改善したと発表した。2人は食事を自分でとれるようになり、うち1人は立つことができたという。チームは「移植した細胞が損傷を修復した可能性がある」とみている。
【図解】脊髄損傷を治療する慶応大の臨床研究
臨床研究を行ったのは慶大の中村雅也教授(整形外科)、岡野栄之(ひでゆき)教授(生理学)らのチーム。横浜市で開かれている日本再生医療学会で結果を報告した。
慶応大病院
発表によると、患者は受傷後2~4週間の18歳以上の4人で、受傷した首や胸から下の運動機能や感覚が完全にまひした。チームは健康な人のiPS細胞から神経のもとになる細胞を作り、2021~23年、患者1人あたり約200万個の細胞を傷ついた脊髄に移植。患者は機能回復を促す通常のリハビリなどを続けた。
移植の約1年後に有効性を検証した結果、運動機能の5段階のスコアが1人は3段階、1人は2段階改善した。残る2人は治療前と同じスコアだったが、改善はみられたという。
今回の臨床研究は安全性を確認するのが主な目的で、重い健康被害は確認されなかった。有効性はさらに精査する。チームはまひが固定した慢性期患者を対象にした治験を27年に行う方針を明らかにした。脊髄損傷は交通事故などが原因で、国内の新規患者は年間約6000人。慢性期の患者は10万人以上とされる。