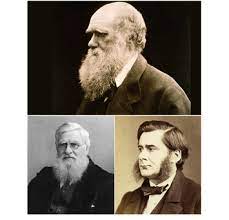この世界はウイルスでできている/武村政春氏(東京理科大学理学部教授)

6/2020
目下日本は、新型コロナウイルス感染症の蔓延を抑え込むことと、そのための行動制限の結果生じている経済的な影響にいかに対応していくかが、喫緊の課題となっている。
大半が症状が出ないか風邪程度の軽症なのに、その一方で一定割合が重症に陥り、高齢者や基礎疾患がある人は死亡してしまう場合もあるという新型コロナウイルスの非常に厄介な特性がある以上、社会全体としてまずは感染を抑え込むことに集中しなければならないのはやむを得ないことだ。そして、その結果生じる経済的な影響や生活困窮に対して、政府や社会が全力でこれをサポートすることも当然必要になってくる。
しかし、それだけでは問題は解決しない。どれほど厳しいロックダウンを強行しようが、それだけで新型コロナウイルス(SARS-CoV-2)が消えてなくなるわけではないからだ。医療崩壊を防ぐことで致死率を下げる努力を続ける一方で、遅かれ早かれこのウイルスと共存する方法を考えて行くことが不可欠となる。
しかし、よくよく考えてみると、われわれはそもそもウイルスがどんなものなのかについて、ほとんど何も知らない。そこで今週のマル激では感染症とは直接関係のないウイルスそのものの専門家をゲストにお招きし、ウイルスとはどんな”物”で、どのように人に”吸着”し、どのように”増殖”するのかなど、ウイルスのイロハについて話を聞いた。
そもそもウイルスが”物”だということを、どれほどの人が知っているだろうか。そう、ウイルスは自分自身では増えることができないので、”生き物”ではなく、あくまで”物”なのだそうだ。そしてウイルスは宿主(しゅくしゅ)を見つけてその細胞に入り込み、その中で増殖することによってのみ自らの子孫を残すことができる。だから、われわれから見ると”感染”に当たるものが、ウイルスにとっては自分の遺伝子を増やす唯一の手段、言うなれば再生産活動なのだ。
ただし、地球上には全ての生物の細胞の数を合わせた以上のウイルスが存在する。空気中にも水道水の中にも食べ物の中にも、無数のウイルスが存在する。そのほとんどは人間には無害なもので、そのうちほんの一握りのウイルスだけが、人間に害を及ぼす病原性を持っている。人間主体で考えるとウイルスは厄介な存在かもしれないが、ウイルス目線で見るとむしろ地球の主役はウイルスの方であって、ウイルスにとって人間もたまには役に立つことがある程度の存在になるらしい。
ウイルスは自分の意思を持たないので、ウイルスにとって”感染”というのは、どこかを浮遊していて、何かのタイミングである動物細胞に接触した時、たまたまそれが何億、何兆分の1の可能性で”吸着”できた時に起きる現象ということになる。ウイルスが他の生物の細胞に吸着できるかどうかは、ウイルス表面の形状と、その生物の細胞表面の物理的な形状がうまく噛み合うかどうかに依存するところが大きいのだそうだ。ウイルスが専門の武村政春・東京理科大教授によると、これは誰かが適当に鍵を振り回していたら、偶然それがすっぽり入る鍵穴にはまったというほどの、奇跡的と言っても過言ではないほどの偶然の産物なのだそうだ。
しかし、その偶然の結果、新型コロナウイルスは人間の細胞に入り込む鍵穴を見つけてしまった。ウイルスには意思はないので、見つけてしまったというよりも、ウイルス側の鍵が人間が持つ鍵穴に何かの偶然ではまってしまったというべきなのかもしれない。その偶然の結果、もはやこのウイルスと人間は遭遇してしまい、しかも人間という生き物は不顕性感染などという形で症状が出ないまま感染者を増やすことが可能なため、このウイルスにとってはとても好都合な宿主だったことになる。しかし、一度出会ってしまった以上、もう二度と出会う前の世界に戻ることはできない。
巨大ウイルスを専門に研究する武村氏はウイルスが生物の進化の鍵を握っている可能性があり、ウイルスの存在があったからこそ、現在の人類が存在するといっても過言ではないと語る。無論、病原性のあるウイルスについては致死率を下げる努力をしなければならないが、ウイルスを頭ごなしに悪い存在と位置づけ、これを撲滅すべき対象としてしか見れなくなってしまうと、大局を見誤るのではないかと武村氏は言う。
戦うにしても、共存するにしても、まずは敵を知ることが大切だ。今週はそもそもウイルスとは何なのかについてウイルス研究者の武村氏に、ジャーナリストの神保哲生と社会学者の宮台真司が話を聞いた。
-----
【プロフィール】
武村 政春(たけむら まさはる)
東京理科大学理学部教授
1969年三重県生まれ。92年三重大学生物資源学部卒業。98年名古屋大学大学院医学研究科博士課程修了。博士(医学)。専門は細胞生物学、分子生物学。名古屋大学医学部・大学院医学研究科助手、三重大学生命科学研究支援センター助手、東京理科大学理学部准教授などを経て2016年より現職。著書に、『生物はウイルスが進化させた』、『ヒトがいまあるのはウイルスのおかげ』、『レプリカ』など。
目下日本は、新型コロナウイルス感染症の蔓延を抑え込むことと、そのための行動制限の結果生じている経済的な影響にいかに対応していくかが、喫緊の課題となっている。
大半が症状が出ないか風邪程度の軽症なのに、その一方で一定割合が重症に陥り、高齢者や基礎疾患がある人は死亡してしまう場合もあるという新型コロナウイルスの非常に厄介な特性がある以上、社会全体としてまずは感染を抑え込むことに集中しなければならないのはやむを得ないことだ。そして、その結果生じる経済的な影響や生活困窮に対して、政府や社会が全力でこれをサポートすることも当然必要になってくる。
しかし、それだけでは問題は解決しない。どれほど厳しいロックダウンを強行しようが、それだけで新型コロナウイルス(SARS-CoV-2)が消えてなくなるわけではないからだ。医療崩壊を防ぐことで致死率を下げる努力を続ける一方で、遅かれ早かれこのウイルスと共存する方法を考えて行くことが不可欠となる。
しかし、よくよく考えてみると、われわれはそもそもウイルスがどんなものなのかについて、ほとんど何も知らない。そこで今週のマル激では感染症とは直接関係のないウイルスそのものの専門家をゲストにお招きし、ウイルスとはどんな”物”で、どのように人に”吸着”し、どのように”増殖”するのかなど、ウイルスのイロハについて話を聞いた。
そもそもウイルスが”物”だということを、どれほどの人が知っているだろうか。そう、ウイルスは自分自身では増えることができないので、”生き物”ではなく、あくまで”物”なのだそうだ。そしてウイルスは宿主(しゅくしゅ)を見つけてその細胞に入り込み、その中で増殖することによってのみ自らの子孫を残すことができる。だから、われわれから見ると”感染”に当たるものが、ウイルスにとっては自分の遺伝子を増やす唯一の手段、言うなれば再生産活動なのだ。
ただし、地球上には全ての生物の細胞の数を合わせた以上のウイルスが存在する。空気中にも水道水の中にも食べ物の中にも、無数のウイルスが存在する。そのほとんどは人間には無害なもので、そのうちほんの一握りのウイルスだけが、人間に害を及ぼす病原性を持っている。人間主体で考えるとウイルスは厄介な存在かもしれないが、ウイルス目線で見るとむしろ地球の主役はウイルスの方であって、ウイルスにとって人間もたまには役に立つことがある程度の存在になるらしい。
ウイルスは自分の意思を持たないので、ウイルスにとって”感染”というのは、どこかを浮遊していて、何かのタイミングである動物細胞に接触した時、たまたまそれが何億、何兆分の1の可能性で”吸着”できた時に起きる現象ということになる。ウイルスが他の生物の細胞に吸着できるかどうかは、ウイルス表面の形状と、その生物の細胞表面の物理的な形状がうまく噛み合うかどうかに依存するところが大きいのだそうだ。ウイルスが専門の武村政春・東京理科大教授によると、これは誰かが適当に鍵を振り回していたら、偶然それがすっぽり入る鍵穴にはまったというほどの、奇跡的と言っても過言ではないほどの偶然の産物なのだそうだ。
しかし、その偶然の結果、新型コロナウイルスは人間の細胞に入り込む鍵穴を見つけてしまった。ウイルスには意思はないので、見つけてしまったというよりも、ウイルス側の鍵が人間が持つ鍵穴に何かの偶然ではまってしまったというべきなのかもしれない。その偶然の結果、もはやこのウイルスと人間は遭遇してしまい、しかも人間という生き物は不顕性感染などという形で症状が出ないまま感染者を増やすことが可能なため、このウイルスにとってはとても好都合な宿主だったことになる。しかし、一度出会ってしまった以上、もう二度と出会う前の世界に戻ることはできない。
巨大ウイルスを専門に研究する武村氏はウイルスが生物の進化の鍵を握っている可能性があり、ウイルスの存在があったからこそ、現在の人類が存在するといっても過言ではないと語る。無論、病原性のあるウイルスについては致死率を下げる努力をしなければならないが、ウイルスを頭ごなしに悪い存在と位置づけ、これを撲滅すべき対象としてしか見れなくなってしまうと、大局を見誤るのではないかと武村氏は言う。
戦うにしても、共存するにしても、まずは敵を知ることが大切だ。今週はそもそもウイルスとは何なのかについてウイルス研究者の武村氏に、ジャーナリストの神保哲生と社会学者の宮台真司が話を聞いた。
-----
【プロフィール】
武村 政春(たけむら まさはる)
東京理科大学理学部教授
1969年三重県生まれ。92年三重大学生物資源学部卒業。98年名古屋大学大学院医学研究科博士課程修了。博士(医学)。専門は細胞生物学、分子生物学。名古屋大学医学部・大学院医学研究科助手、三重大学生命科学研究支援センター助手、東京理科大学理学部准教授などを経て2016年より現職。著書に、『生物はウイルスが進化させた』、『ヒトがいまあるのはウイルスのおかげ』、『レプリカ』など。