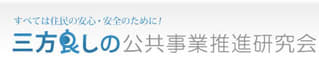今回の新潟行、わたしのメインミッションは三方良しの公共事業推進研究会理事会への参加だったのだが、その前日、それに先立って行われた新潟支部研修会でいくつかの気づきと学びがあった。そのなかのひとつがWIPボードの活用だ。プレゼンターのうちお二方(株式会社ユニフローの石橋さんと新潟県庁の瀬戸さん)が、自組織の改善ツール(のひとつ)としてWIPボードを紹介していた。

石橋さんの事例発表より

瀬戸さんの事例発表より
WIPとは、work in processの略。つまり、 「work」(仕事、開発、勉強など)が「in progress」(進行中、進行途中)であるということで、製造業では仕掛品であり、プロジェクトマネジメントでは仕掛かり作業ということになる。わたしがこの手法に着目したのは何年前だったろう。しかとは覚えてないが、すぐさまわたし個人の仕事の仕方はもちろん、わたしが属する組織にも取り入れた。結果としてもっとも有用だったのは個人的な使い方だ。タスクボードという形で自分自身が受け持つタスクを、「やらなければならないこと」「次にやること」「やっていること」「終わったこと」という各項目に振り分けてきた。そのおかげで、わたしにとっては避けようがないマルチプロジェクト環境において、「悪いマルチタスク」を排除して仕事の優先順位決めとタスクの交通整理が、かなりの部分で行えるようになった。そしてその繰り返しが「思考の癖づけ」になり、とてもありがたいツールとしてわたしのなかでのランクはかなり高い。
その一方で組織としての導入という面では完全に失敗してしまった。朝会(スタンダップミーティング)における現場報告で「きのうやったこと」「今日やること」「問題があるとすれば何がある」という項目を織り込み、それをホワイトボードに付箋で貼ることで、情報共有を図ろうとしたが、その目論見は見事に外れ、ただただ惰性的に「今日やること」だけを報告するという行為を「やれと言われているからやるのだ」という、いわば無自覚的に繰り返している現状が残滓としてある。だが、考えてみればそれも仕方のないことだ。「なぜそうするか?」「どうしてそれをすることが必要なのか?」という共通認識が、参加者全員とまではいかなくても、少なくとも主要メンバー間にないうちでの「思いつきの押しつけ」(発信側たるわたしの問題意識上そうではないにせよ、受信する方はたぶんそう受け取っていた)であれば、ハナからうまく行くはずがなかったのである(つまり、うまく行くための営為がほとんどなされてない)。
そんな現状に対して「そろそろ楔を打ち込まないとな」と考えていた矢先だっただけに、じつにタイムリーな「気づき」と「学び」をいただいた新潟行。であれば、それを活かさない手はない。もちろん「”WIPボード”という仕事の仕方」はそのなかの一例であり、それがすべてを解決してくれる万能のソリューションツールとしてあるわけではない。だが、リスタートしてみよう。まずは、「なぜそうしようとしたのか?」「どうしてそれをすることが必要だと思ったのか?」という自分自身への問いかけからだ。そしてその次は、いつものとおり「隗より始めよ」。個人的に模倣を試行してみたうえで、組織のメンバーに理解ができる「現地語」に「翻訳」して展開を図り「土着化」する。
もちろん、そんなに簡単ではないことは百も承知二百もガッテンだが、やらなければ何も始まらない。
まずやる
ふりかえる
気づく
学ぶ
またやる
ふりかえる
気づく
学ぶ
また・・・
あらあら、十年一日のごとく変わりがない結論だ。どうにもこうにも、あいも変わらず成長しないオジさんではあるが仕方がない。もともとそれほど程度が高いわけではないのだ。ぼちぼち行こう。
↑↑ クリックすると現場情報ブログにジャンプします
発注者(行政)と受注者(企業)がチームワークで、住民のために工事を行う。