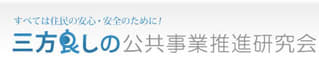「松に鶴」
花札ではない。
「松花伴鶴飛」における「松に鶴」だ。
「松花伴鶴飛」
「松花、鶴に伴って飛ぶ(しょうか、つるにともなってとぶ)」と読むのだそうだ。
TSUTAYAの中古本コーナーから金100円也で買い求めた『釈迦に説法』(玄侑宗久、新潮新書)から、かつて結婚式の屏風の定番だった「松に鶴」はどうしてめでたい絵柄の代表格となったか、という話を引用してみる。
 |
釈迦に説法 (新潮新書) |
| 玄侑宗久 | |
| 新潮社 |
松は六月ころ、ピンクの花をつけるのだが、たまたま飛来した鶴の脚に花がくっつき、鶴が飛ぶのに伴って見も知らない土地にその花が落ち、そこで目を出して根を張りはじめる。そのありようが、花嫁に似ているというのである。
痩せた土地であるほど松は深く根をおろし、花咲いた土地とは全く関係ない土地で力強く生きて行く。まあ、ここは嫌だからと思っても引っ越せないわけだからそうするしかないのだが、いわば偶然とも云えるご縁を愛でようという生き方を、松に見ているのだと思う。花嫁もかくあってほしいというのだろう。(P.60)
仙台空港から飛び立った機中でこのくだりを読むなり、「いいなあ鶴」と独りごちた。
自らの身体にくっつけた花を、身も知らない土地まで運び、そこで落とした種子がその地で芽生え、根を張る。その「ご縁」の媒介役としての鶴になりたいと思ったのだ。偶然の媒介役ではなく、自覚的な媒介者としてである。
いやいやかくいうわたしとて、そういう役目をこなしてこなかったわけではないし、そう思ってこなかったわけでもないが、よりいっそう強く、これまで以上に、「鶴たらん」と自覚して行動するのが、少しばかり他人さまより早く「三方良しの公共事業」について考え始め、他人さまより少しばかり深く「三方良しの公共事業」について考えてきた(かもしれない)、そしてそれを「伝える者」として存在しているわたしに課せられた使命でもあるのだろう。
てなことを考えたあと、新書から目を離して窓の外をながめ、
「たぶんいつもの勘違いなんだろうケド」と苦笑い。
(これで垂直尾翼に鶴丸が入ってたらよくデキた話だったのですが・・・)

↑↑ クリックすると現場情報ブログにジャンプします
有限会社礒部組が現場情報を発信中です
発注者(行政)と受注者(企業)がチームワークで、住民のために工事を行う