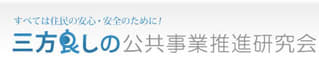メモ帳がわりの測量野帳に殴り書きされていた短い言葉。
「三方一両ぞんでもいいじゃないの」
見るなり苦笑を禁じ得ない。ただでさえ悪筆なのが酔って書いたときた日には、とても見られたもんではない。ミミズが這ったような字とはこのことだ。だがまあいい、誰に見せるもんでもないさ、と気を取り直し、そのときの会話の内容を思い出してみた。
とその前に、三方一両損について説明しなければならない。三方一両損、ご存知「大岡裁き」のひとつである。
念のため、ご存じない方に『落語の舞台を歩く』(第37話)を参考にあらすじを紹介する。
白壁町の左官の金太郎が、あるところで財布を拾う。なかには印形と書き付けと金三両が入っていた。
書き付けから神田竪大工町、大工の吉五郎と分かり届けてやると、吉五郎、鰯の塩焼きで一杯呑んでいた。
「勝負!」
と言いながら中に入る金太郎。
「落とした財布を届けてやった」
「書き付けと印形は俺の物だから貰うが、三両はもう俺のものじゃない。テメエにやるから持って帰ぇれ」
「金を届けてけんかを売られりゃ~世話がねぇや。」
「よけいなことをしやがる」
「なんだと~!」
けんかになり、大家が仲裁に入るが、吉五郎は受け取るどころか大家にも毒ずきはじめる。言われた大家も我慢がならず、
「大岡越前守さまに訴えて、白州の上で謝らせるのでお引き取りください」
ということで金太郎、帰ってくる。
今度はその話を聞いた金太郎の大家、
「おまえの顔は立ったが、俺の顔が立たない。こちらからも訴え出てやる」
双方から訴えが出て、御白州の場へ。
吉五郎も金太郎も三両はどうしても受け取らないと言う。
そこでご存知大岡裁き。
「ならば、この三両を越前が預かり、両名に褒美として金ニ両ずつ下げつかわす」
「金太郎がそのまま拾っておけば三両、吉五郎がそのまま受け取れば三両、越前守そのまま預かれば三両であるが、越前が一両を出して双方にニ両ずつ渡したから、三方一両損である」
これにて一件落着・・・
 |
大岡越前 第一部 [DVD] |
| クリエーター情報なし | |
| 竹書房 |
という話である。
さて、検証してみよう。まず大岡越前。この場合、お奉行さまが一両損をしたのは明確だ。3-(2+2)=-1である。次に大工の吉五郎。彼にはふた通りの解釈ができる。三両あったものが二両に減ったので一両損という解釈と、三両をなくなったものと考えれば二両返ってきただけでも御の字、一両損というのは過剰評価だという解釈だ。つづいて左官の金太郎。拾った三両を丸々もらうことができず、それが二両になったからといって一両損とまで言えるだろうか。彼については純然と二両の儲けと考えるほうが自然のような気がする。
なんて、訳知り顔で解説する、こういう輩を野暮という。
それを承知であえて書いてみたのは、純然とした一両損は大岡越前守ただひとりで、なおかつ彼は自らそれを発案し自分自身でそれを選択したということを際立たせてみたかったからである。
メモをしたあのときの酒場に戻ろう。
「あなたたちが提唱する”三方一両損”がさあ」
「いや”三方一両損”じゃないよ、”三方よし”」
「おんなじようなもんじゃない」
「いやいや全然違うし。”三方よし”は損しないの。みんなが良くなるところを目指すから”三方よし”」
「別にいいじゃない、”三方一両損”でも」
「ははあなるほどネ」。目から鱗がボロボロっと剥がれ落ちたわたしはすぐさまメモをした。
「三方一両ぞんでもいいじゃないの」
損という漢字が出てこなかったのはご愛嬌である。
目指すところとしての「三方よし」はそれでいい。しかし、「売り手よし買い手よし世間よし」と三方を区分した場合の「売り手」は、時として損をするものだ。いや、「三方よし」の場合は、むしろ選択的に損をするところから始まると言ってもかまわない。自分に転がり込んでくるであろう儲けを独り占めせずに世間に還元するという選択は、一時的に見れば、利益の損失を選んでいるということである。ただそれが、長期的に見た場合にどうか、持続可能かどうかとなれば話は別だ。信頼や信用という目には見えない利益が、そうすることによって生み出され、ストックされながら持続していく。「三方よし」という商売理念は、そういうものだとわたしは考えている。
ひるがえってわたしたち公共建設工事の構成員はどうか。「住民よし企業よし行政よし」あるいは「地域よし施工者よし発注者よし」と三方を区分した場合の「企業(施工者)」は、もちろん利益がなければ成り立たない。自らの利益を生み出すことを第一義として存在している。だが、だからといってすべてにおいて損をしてはならないかといえば、そうでもなかろうとわたしは思うのだ。「売り手」が時として損をするものならば、「企業」もまた同じである。自ら進んで損を選択することも、ある局所ある局面では必要な一手だ。現場で生まれた信頼を現場でストックしていくためならば、あえて目先の損を選ぶのも重要なのだ。
ここでひとつ断っておく。その損は、強いられたものであってはならない。自ら選択した損でなければならない。だからこそ、その損は明日へつながる。自ら一両損を選択した大岡越前が名奉行たり得たように(って、ちょっとこじつけかな ^^;)。
なんて回りくどい説明をしたが、なにもそれは「三方よし」の専売特許ではない。ジャパニーズ・ビジネスにおいては昔からよくあるモデルだ。そこには、「企業の目的は極大利潤の追及」という今という時代の常識は当てはまらない。利潤を追求するのは当たり前だとしても、その利潤は、少なくとも「極大利潤」ではない。
たとえば、
「損して得とれ」
あるいは、
なにより、昨今流行りの「ウィン・ウィン」というやつが、どうにも胡散臭く感じられるひねくれ者のわたしだもの、どこかで損してどこかで得して、誰かが損して誰かが得して、という営みのなかで落としどころを探りつつ、結局はみんながより良くなっていこうという筋立てのほうが性に合っている。そしてそのほうが、日本人の性にも合っているとわたしは思うのだ。
であれば・・・・
「三方一両損でもいいじゃないの」
(いやいや、住民の損だけは避けるべきだけど)
あのとき、あの酒場で、瞬時にここまで考えが至ったわけではもちろんない。メモ帳がわりの測量野帳にミミズが這ったような文字で殴り書きされていた短い言葉をもとに、現在の考えをまとめてみただけのことである。この先この考えが、自分のなかでどう展開していくか。
書き連ねているうちに、こんな展開を考えついた。大岡越前のとった解決方法はヒエラルキー・ソリューションで、三方良しの公共事業が目指すのはそれとは逆のコミュニティー・ソリューション、だから「三方一両損」と「三方よし」は似て非なるもの、根源的なところで異なっているのだ、という切り口からスタートし、とはいえ結局「三方一両損でもいいんじゃないの」(いやいや住民の損だけは避けるべきだけど)というフレキシブルな結論に至る、なんて展開だ。しかし、うまく論考がまとまらない。まとまらないうちではあるけれど、とりあえずリリースしてみるべきだと思い本日アップする。
つづきは・・・
いつかまた。
↑↑ クリックすると現場情報ブログにジャンプします
有限会社礒部組が現場情報を発信中です
発注者(行政)と受注者(企業)がチームワークで、住民のために工事を行う。