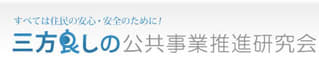NHK朝ドラ『とと姉ちゃん』で主人公の常子が和文タイプライターに挑戦しているのを見た。(といっても朝見るのはムリなのだけれど)
和文タイプライター、たとえばこんなんである。

小型邦文タイプライターSH-280(日本タイプライター製)
画像-『Wikipedia~和文タイプライター』より
じつはわたし、コレ得意だった。
「キーによる盤面操作で活字箱から任意の活字を取り出す」
「小型汎用機種でも大抵は2000を超える感じを含む活字から、適切な文字を探して一文字ずつ打ち込んで行く」
(Wikipedia~同)
ため、どの文字がどのあたりにあるのかを覚えているかどうかが速く打てるためのキーポイントで、当時「悪魔のような記憶力を持つ男」と呼ばれていた(自称ですが)わたしにとってそれは、もっとも得意とする分野だった(つまり、記憶力にもいろいろあるなかで「神経衰弱」が強い的な記憶力、みたいな)。
(あのころに比べて今は・・・、自分自身の体たらくが嘆かわしい・・・、嗚呼)
和文(邦文)タイプライター、
1915年(大正4年)、日本の十大発明家のひとり杉本京太により発明された。
日本語では文章を構成する文字数が多いため、文字数の少ない欧文タイプライターの機能はそのまま使えないと言う制約があり、当時タイプライターの開発は困難であった。杉本は文字の使用頻度を考慮し2,400字を選び出し独自の配列で文字庫に並べた活字を、前後左右に稼働するバーで選択しつまみ上げ、円筒に巻かれた紙に向かって打字すると言う機構を開発した。この方式の和文タイプライターで1920年代には政府公文書の多くが作成されるようになり、1980年代に日本語ワードプロセッサーが普及するまで官公庁や企業・教育機関などで使用され、日本における書類作成事務効率化に大きな役割を果たした。(『Wikipedia~杉本京太』より)
今から考えても、よくデキた道具だった。
あんなに凄いものでさえ、時代の移り変わりの前ではあっさり無用の物と化してしまう。
日本語ワープロにとって替られ、信じられないほどの速さで用済みとなった和文タイプライターを、喜々としてタイピングをしていた若かりしころの自分を思い出し、
ゆく川の流れは絶えずして、しかも、もとの水にあらず。
よどみに浮かぶうたかたは、かつ消えかつ結びて、久しくとどまりたるためしなし。
という方丈記の一節を思い浮かべ、いっとき黄昏れる。
いやいや、世の中にこんな例はゴマンとある。
いくら「変わる」ことに抵抗したとしても、「変わる」ことを拒否したとしても、「変わる」ものは否応なく「変わる」。
そんなもんである。
そしてその波は、若手にもベテランにも経営者にも従業員にも一様にやってくる。自分だけは埒外なのだ、もしくは対応するのは自分ではない、と思うのは人それぞれでけっこうなのだが、(少なくとも)わたしはその道を選ぶのを良しとはしない。
「変わる」ところは変える、「変わらない」ところも変える。
なんとなれば、今という時代に「(土木の)仕事をする」という行為自体が、漸進的に変わりつづけることに他ならないのだから。
(あらあら、和文タイプライターの思い出について書いていたら、いささか大仰な結論になってしまいました)
(ま、ええか)
↑↑ クリックすると現場情報ブログにジャンプします
有限会社礒部組が現場情報を発信中です
発注者(行政)と受注者(企業)がチームワークで、住民のために工事を行う。