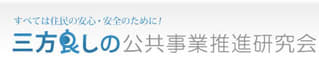知人から聞いた話。
息子さんが坂道に停めていた車が、運転手がおらぬまに動いて隣家の塀に突っこんだのだそうだ。
隣家の主は、「気にすんな。そんなこともあるわ。」と笑って許してくれたというが、知人、たいそうご立腹なのである。
原因はというと、サイドブレーキが甘かったこと、そしてタイヤの歯止め(車輪止め、ストッパー)をしてなかったこと、らしい。サイドブレーキについては何をか言わんやだろうが歯止めはどうだろう。わたしたちの世界では、今や常識のひとつとなりつつ感がある歯止めだが、一般的にはそうでもないような気がする。いやいや一般的うんぬんではない。思わず「常識のひとつ」と書いてしまったが、この片田舎では、そうでもない部分も散見されるのが現実だ。もちろん、そういうわたしとて例外ではない。
その「歯止め」、あまり知られていないことだが、いわゆる一般車両に関して法律上の規制はない。逸走防止措置が規定されているのは建設機械について、たとえば次のような条文である。
労働安全衛生規則第百五十一条の十一
事業者は、車両系に駅運搬機械等の運転者が運転位置から離れるときは、当該運転者に次の措置を講じさせなければならない。
一 (略)
ニ 原動機を止め、かつ、停止の状態を保持するためのブレーキを確実にかける等の車両系荷役運搬機械等の逸走を防止する措置を講じること。
2 前項の運転者は、車両系荷役運搬機械等の運転位置から離れるときは、同項各号に掲げる措置を講じなければならない。
同第百六十条
事業者は、車輌系建設機械の運転者が運転位置から離れるときは、当該運転者に次の措置を講じさせなければならない。
一 (略)
二 原動機を止め、かつ、走行ブレーキをかける等の車輌系建設機械の逸走を防止する措置を講ずること。
2 前項の運転者は、車輌系建設機械の運転位置から離れるときは、同項各号に掲げる措置を講じなければならない。
コチラは建設機械ではないが、こんな条文もある。
同第百九十五条
この省令で軌道装置とは、事業場附帯の軌道及び車両、動力車、巻上げ機等を含む一切の装置で、動力を用いて軌条により労働者又は荷物を運搬する用に供されるものをいう。
同第二百四条
事業者は、車両が逸走するおそれのあるときは、逸走防止装置を設けなければならない。
法律に限らなければ、『土木工事安全施工技術指針』(国土交通大臣官房技術調査課)にはこんなことが書かれている。
第4章第3節 建設機械の搬送
1.建設機械の積込み、積降し
(3) 積込み、積降し作業時には、移送用車両は必ず駐車ブレーキを掛け、タイヤに歯止めをすること。
ちなみに、道路交通法にある「車輪止め」に関する条文はこうだ。
第五十一条のニ
2 警察署長は、道路又は交通の状況から判断して車輪止め装置取付け区間における違法駐車行為を防止するためやむを得ないと認めるときは、当該区間における違法駐車行為に係る車両に車輪止め装置を取り付けることができる。
あ、これは違うな。わたしもかつてやられた経験があるアレだ。車輪止めと輪止め(歯止め)はまったく別物らしい。
知人の話に戻る。
聞くなりわたしの脳裏に浮かんだ例が2つある。ひとつはわたしの体験だ。
1989年だった。当時わたしは、杜の都仙台で丘の上にある一軒家を借りて住んでいた。仕事が終わり、帰宅したあと、4才の娘をクルマの助手席に乗せ近所をひと回りし、丘のてっぺん近くにある酒屋の自動販売機でビールを買おうとクルマを停めた。よ~し、今日も元気だビールがうまいとルンルン気分で。
ふと、妙な気配に気づいてふりかえると、ゆっくりとクルマが動き出していた。すぐさま運転席のほうへ走ったがかなりな急坂である、クルマは徐々にスピードが上がっていく。追いつくまでに何秒かかっただろう。とにかく追いついた。取っ手に手をかける。ドアをあける。そのあいだもクルマのスピードは上がっていく。飛び乗った。ブレーキを踏む。助手席にいた娘がダッシュボードにぶつかる。泣き叫ぶわが子が無事なことをたしかめ、天を仰ぎ目を閉じた。
助かった・・・。
あのとき何を考えていたかはよくわからないが、とにかく必死だったことは覚えている。60年のわたしの人生で、まちがいなくもっとも必死だった瞬間である。
何ごともなかったからいいようなものの・・・
思い出して、背筋がぞっとした。
2つめは福島の寿建設さんにおじゃましたときのことである。
すべての工事用車両が、後輪には歯止めをし、そのうえ前輪のタイヤを道路とは逆側へきっていたのだ。

『寿建設社長ブログ』より
万が一のための安全管理である。
さらにかの人たちは、これを傾斜がある場所だけではなく平坦なところでも実行している。「傾斜があるところだけは絶対やろう」などという声がけを百万遍したところで、実施の徹底を実現することはできないからだという。
正直にうちあけると、これを見たとき、「スゴイですねえ」と笑顔で褒めながら「何もそこまでしなくても」と思った。だが、今はちがう。「万が一」とは、まさにこういうことを言うのである。やるかやらぬか、また、どこまでやるかは法的規制がない以上、各自(各社)の判断にまかされるのだろう。だが、「備えあれば憂いなし」。月並みで使い古された言葉ではあるけれど、それが安全の基本であることはまちがいないということを踏まえてあらためて思い起こすと、寿建設の「凄み」を実感するのである。
くだんの知人の息子さんは、たぶん失敗から学ぶのだろう。たしかに、失敗は最良の教材にはちがいない。多くのことを教えてくれるし貴重な学びを得られるのもたしかだ。だからこそ、「失敗を経験させることが人材育成には必要」だとか「失敗を経験しなければ学べない(ので失敗させろ)」とかの意見がもっともらしくまかり通るのだし、その説に一理もニ理もあることはわたしとて認める。だが、事故(労働災害や交通災害)にかぎっていえば、その説を当てはめてはいけない。少なくとも「事故はあってはならない」という姿勢を崩すべきではない。
万が一のために備える。
そして、備えあれば憂いなし。
以上、「息子が坂道に停めていた車が運転手がおらぬまに動いて隣家の塀に突っこんだ」という知人の話を聞いて思い起こしたことと考えたこと。「もって他山の石とすべし」である。
↑↑ クリックすると現場情報ブログにジャンプします
発注者(行政)と受注者(企業)がチームワークで、住民のために工事を行う。