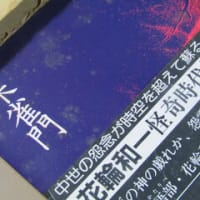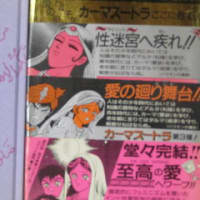『シン読解力 学力と人生を決めるもうひとつの読み方』(東洋経済新報社)
著者 新井紀子
1 第一印象
タイトルが怪しい。冗談半分か?
「シン」は『シン・ゴジラ』が始まりらしいが、あの映画はちっとも面白くなかった。数日前に紹介した『おいしい雑草図鑑』の帯にも「シン」が使われていた。あれは帯だから、我慢できる。
「シン」には、新、真、深、神、芯、信、清、新、慎、進などの含意があるらしいが、私にとっては辛だよ。
「もうひとつの読み方」は意味不明。「もう」ではない「ひとつの読み方」って何? 誤読のことらしいが、本書が解決しようとしているのは、誤読の弊害ではない。それも扱ってはいるが、ほとんどは稚拙な読み方だ。だから、「もうはひとつ」ではなく、〈三番目の「読み方」〉とすべきだ。
私は『AIvs.教科書が読めない子どもたち』と『AIに負けない子どもを育てる』を読んでいたから、この本も読む気になった。そうでなければ、手に取ることさえしなかったろう。
*
学力(言い換えればシン読解力)の状況が厳しい学校ほど、この単元には十分に時間を割くよう教えています。
(「トレーニング&コラム」p48)
*
意味不明。
「学力(言い換えればシン読解力)」というのなら、副題の「学力と人生を決めるもうひとつの読み方」は〈「シン読解力」と「人生を決めるもうひとつの読み方」〉と読解するのかい?
〈「学力」~「の状況」〉は意味不明。
「厳しい」は意味不明。財津一郎の「キビシー!」ってのと同じ雰囲気かな。
〈「単元には」~「時間を割く」〉も変だ。「単元には」は〈「単元」を教えるとき「には」〉の不適切な省略か。不明。
「教えています」の主語は誰? 教わっているのは誰? 〈私は教師たちに対して《あなた方が生徒たちにこの単元の内容を教える場合は十分に時間を割くようにしなさい》と教えています〉という意味だろうか。不明。
著者は、自分では丁寧に説明しているつもりらしいが、実際には意味不明の悪文がちらつく。また、意味は明解でも、根拠を示さずに決めつけることがある。癖みたい。
『夏目漱石を読むという虚栄』(2112 「その人」と「常に」)参照。夏目漱石を読むという虚栄 2110 - ヒルネボウ
この本は悪書ではない。だが、全幅の信頼を置くことは、キビシー!
ただし、役には立つ。叩き台として使える。
(続)