カフカの「変身」を再読して、やはりカフカはもっともっと読まなきゃなぁ。次は「審判」か「失踪者」を読んでみようと思っていました。
例によって、そのうちそのうちで読まずにおく可能性を感じつつ。
そんな時、山村浩二のアニメーション「田舎医者」の公開を知って、あわててこの「断食芸人」を購入して読みました。
「田舎医者」という短編集(14編)と「断食芸人」という4つの物語。そして<新聞・雑誌に発表のもの>11編からなる。
ショート・ストーリーというか実に詩的な散文があったり、やっぱりカフカは難しいんだなと認識。短いので手軽に読めるというよりむしろ短いからこそ難しい。
これが長編、たとえば「城」あたりになると長いので、読んでいくうち面白い所にぶち当たりたまらなく嬉しくなったりする。要するに誤読を楽しむ余地があるような所。この作品集の中には???で読み過ごしてしまった物もいくつかある。
また、カフカはどうしても分析をしたくなる手の作家。自分自身には分析する力が無いのでカフカ研究本を読んで手引きにすると面白そう。余計混乱するかな?
それでも1冊読み終わると充実感はあり、おや、結構楽しめたなといった感想。ここいらが不思議。
詩的な文体から情景の美しさを楽しむ事ができるのは池内紀氏の訳文に依る所が大きいのかもしれない。
今回アニメになる「田舎医者」は表題作だけに魅力的でした。
女中のローザが馬を貸してくれた馬丁に手篭にされていやしないかと不安を抱きながら少年の往診を勤める医者。少年の腹には女中と同名の色(ローザ色)の傷・・・
山村浩二のアニメはモノクロで雪深い田舎の情景を暗~いタッチで描いているようですが、果たしてどうなりますやら。今から楽しみです。
短編集「田舎医者」の中では他に「皇帝の使者」「家父の気がかり」「十一人の息子」が好きでした。
短編集としては「断食芸人」の4編の方が平均的に面白い。
中でも「小さな女」はせつない。
わたしのやる事なす事を我慢できない小さな女。わたしのすべてが彼女の美意識、正義感、習慣、習わし、望むところと反している。天敵のような物。これが配偶者、同居人、長年の恋人とかならよくある話でこうなると始末に終えない。でも配偶者や恋人ならピリオドという解決策もある。この小さな女は赤の他人。好かれたいとは思わないものの世間の関わり上わたし自身も変ろうと努力してみたりもする。
ここまで嫌がられるというのは、この小さな女自体が何かの象徴なのかしら。
「歌姫ヨゼフィーネ、あるいは二十日鼠族」音楽に疎いチューチュー族の中にあっての歌姫の悲哀。これも分析ネタとして面白そう。教えてください。
「断食芸人」少し流行を過ぎた芸の芸人。40日目を過ぎると客の関心が極端に落ちるため断食を中止させられる。もっと永く、かぎりなく永くつづけられるのに・・・
断食芸人が監督に語った最後の言葉が余韻を残す。

例によって、そのうちそのうちで読まずにおく可能性を感じつつ。

そんな時、山村浩二のアニメーション「田舎医者」の公開を知って、あわててこの「断食芸人」を購入して読みました。

「田舎医者」という短編集(14編)と「断食芸人」という4つの物語。そして<新聞・雑誌に発表のもの>11編からなる。
ショート・ストーリーというか実に詩的な散文があったり、やっぱりカフカは難しいんだなと認識。短いので手軽に読めるというよりむしろ短いからこそ難しい。
これが長編、たとえば「城」あたりになると長いので、読んでいくうち面白い所にぶち当たりたまらなく嬉しくなったりする。要するに誤読を楽しむ余地があるような所。この作品集の中には???で読み過ごしてしまった物もいくつかある。
また、カフカはどうしても分析をしたくなる手の作家。自分自身には分析する力が無いのでカフカ研究本を読んで手引きにすると面白そう。余計混乱するかな?
それでも1冊読み終わると充実感はあり、おや、結構楽しめたなといった感想。ここいらが不思議。

詩的な文体から情景の美しさを楽しむ事ができるのは池内紀氏の訳文に依る所が大きいのかもしれない。
今回アニメになる「田舎医者」は表題作だけに魅力的でした。
女中のローザが馬を貸してくれた馬丁に手篭にされていやしないかと不安を抱きながら少年の往診を勤める医者。少年の腹には女中と同名の色(ローザ色)の傷・・・
山村浩二のアニメはモノクロで雪深い田舎の情景を暗~いタッチで描いているようですが、果たしてどうなりますやら。今から楽しみです。

短編集「田舎医者」の中では他に「皇帝の使者」「家父の気がかり」「十一人の息子」が好きでした。

短編集としては「断食芸人」の4編の方が平均的に面白い。
中でも「小さな女」はせつない。
わたしのやる事なす事を我慢できない小さな女。わたしのすべてが彼女の美意識、正義感、習慣、習わし、望むところと反している。天敵のような物。これが配偶者、同居人、長年の恋人とかならよくある話でこうなると始末に終えない。でも配偶者や恋人ならピリオドという解決策もある。この小さな女は赤の他人。好かれたいとは思わないものの世間の関わり上わたし自身も変ろうと努力してみたりもする。
ここまで嫌がられるというのは、この小さな女自体が何かの象徴なのかしら。

「歌姫ヨゼフィーネ、あるいは二十日鼠族」音楽に疎いチューチュー族の中にあっての歌姫の悲哀。これも分析ネタとして面白そう。教えてください。

「断食芸人」少し流行を過ぎた芸の芸人。40日目を過ぎると客の関心が極端に落ちるため断食を中止させられる。もっと永く、かぎりなく永くつづけられるのに・・・
断食芸人が監督に語った最後の言葉が余韻を残す。

フランツ カフカ, Franz Kafka, 池内 紀 / 白水社(2006/08)
Amazonランキング:92882位Amazonおすすめ度:






















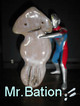





※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます