6月1日発行の鹿嶋市の広報、ちょっと珍しい企画をやっていました。
鹿嶋市内の中学生475名に対しての郷土料理の認知度アンケートというもので、エントリーされていたのは、①がりがりなます②海藻よせ③ごさい漬け④けんちん汁の4種類。
①は調理器具に由来していて、「鬼おろし」というものを使う。一般的な料理器具。木枠または竹枠の中に、山型の突起に加工した竹製の刃で、大根や人参を摺り下ろす。一般的な大根おろし器より、水分の流失が少ない。これを使った大根と、蛸などの魚介類を刻んだものを酢で和えたもの。これは郷土料理なのかねぇ。一般的には見かけると思うけど、知らないが91.8%。
②は、単に「かいそう」、「海藻こんにゃく」とも呼ばれるが、コトジツノマタという海藻を煮込んでドロドロになったものを、冷やして固めたもの。鰹節や唐辛子、醤油を掛けて戴く。ただ、これは千葉県の銚子の郷土料理だと思う。ちなみに銚子では「ケーソー」とよばれることもある。記憶が定かでは無いけど、品種が複数あって、安いもの高い物があったと記憶する。これも、知らないが91.8%。山田海藻店などの市販品もあるのだけど。
③は鹿島郡全般に見られるもので、秋口に大根のスライスと、秋刀魚や鰯の生の切り身を交互に重ねて保存したもの。風味付けに刻んだ唐辛子(「天井てっぺん」という品種?)と柚子を使う。これは、知らないが89.1%。
④知らないが6.1%。本当に?。言わずと知れた、根菜を主体とした汁物。基本的に精進料理なので、生臭物は使わない。出汁は椎茸など。
この中で、本当に鹿嶋市(鹿島郡)の郷土料理と言えるのは③の「ごさい漬け」だけだと思うのだけど、合併前の鹿島郡大洋村(現在の鉾田市)で、町興しに使おうという動きはあったけど、頓挫したようです。昔からやっている飲食店では、冬期に料理やお通しで登場するし、10年以上前の記憶だけど、一部の漬物メーカーが年末に販売するので、認知度がここまで低い理由はわからない。いや、簡単なことか。まず、子供は食べないだろう。好んで食べるなら将来が心配になる。どう見ても酒のツマミ。個人的には、生臭いし、生の魚の切り身の食感があまり良くない。鮪や鰹並みに弾力があれば気にならないんだが。
本来のサイクルは、秋口に銚子や大洗で水揚げされた秋刀魚や鰯が地域に運ばれてきて、保存食として加工する。大根と塩?と一緒に漬け込んで、数ヶ月掛けて乳酸菌作用で骨まで柔らかくして、正月に出されるといった感じ。だから、漬物メーカーは年末の限られた期間限定の製造販売。「ごさい」の由来は、はっきりしないものの、公報に書かれた記事によると、秋刀魚、大根、唐辛子、柚子、塩の5彩(菜)を使うことからというものがあるようだ。
余談だけど、獲れたての鮮魚を食べる地域と、加工保存をした魚を食べる地域は、鰹の叩きなどの食べ方で別けられそう。皮を食べるか残すかってことで。
それにしても、この認知度だと、残念ながら、近い未来に完全消滅しそうですね・・・










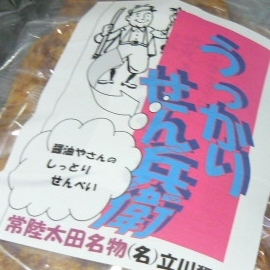





※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます