札幌市天文台は、観測室の内装工事などのため2023年3月13日(月)から3月24日(金)まで臨時休台中です。

2022年4月に札幌市天文台訪問した際、1984年10月に更新された2代目の口径20cmF12アポクロマート屈折望遠鏡を撮影させてもらいました。
ところで、2023年3月の内装工事開始の前に、天文台スタッフのYさんから私に問い合わせがありました。

「内装工事に際し、望遠鏡をカバーで覆ったのですが、これで合ってますか?」という問い合わせでした。(画像はYさん提供)
1984年の望遠鏡更新を担当したのは私なのですが、望遠鏡カバーのことは完全に忘れていました。大変失礼いたしました。
望遠鏡カバーは五藤光学さんの特注品です。東京都府中市の志村シートさんが製造し、1984年8月21日に五藤光学機械課さんへ納品されていることが、見せてもらった添付書類で確認できました。
添付書類に書かれていた納品日の1984年8月と、2代目望遠鏡を初公開した1984年10月とは時期的に重なり、私が札幌市天文台業務を所管していた時期です。つまり、私が望遠鏡カバーを受け取ったことは間違いないようです。
齢を重ねると記憶がどんどん消えていきます。(笑)
大型望遠鏡をすっぽり覆うカバーまで購入時の付属品としている五藤光学さん、さすがですね。
望遠鏡カバーを天文台の中から探し出し保管してくれたのは天文台スタッフのHさん。工事に備えカバーをかけてくれたり、普段から望遠鏡を丁寧に大事に扱ってくれている口径20cm屈折望遠鏡は、私の娘(息子?)みたいなものと私は勝手に思っています。天文台の4人の優しいスタッフの皆様、ありがとうございます。

2022年4月に札幌市天文台訪問した際、1984年10月に更新された2代目の口径20cmF12アポクロマート屈折望遠鏡を撮影させてもらいました。
ところで、2023年3月の内装工事開始の前に、天文台スタッフのYさんから私に問い合わせがありました。

「内装工事に際し、望遠鏡をカバーで覆ったのですが、これで合ってますか?」という問い合わせでした。(画像はYさん提供)
1984年の望遠鏡更新を担当したのは私なのですが、望遠鏡カバーのことは完全に忘れていました。大変失礼いたしました。
望遠鏡カバーは五藤光学さんの特注品です。東京都府中市の志村シートさんが製造し、1984年8月21日に五藤光学機械課さんへ納品されていることが、見せてもらった添付書類で確認できました。
添付書類に書かれていた納品日の1984年8月と、2代目望遠鏡を初公開した1984年10月とは時期的に重なり、私が札幌市天文台業務を所管していた時期です。つまり、私が望遠鏡カバーを受け取ったことは間違いないようです。
齢を重ねると記憶がどんどん消えていきます。(笑)
大型望遠鏡をすっぽり覆うカバーまで購入時の付属品としている五藤光学さん、さすがですね。
望遠鏡カバーを天文台の中から探し出し保管してくれたのは天文台スタッフのHさん。工事に備えカバーをかけてくれたり、普段から望遠鏡を丁寧に大事に扱ってくれている口径20cm屈折望遠鏡は、私の娘(息子?)みたいなものと私は勝手に思っています。天文台の4人の優しいスタッフの皆様、ありがとうございます。

















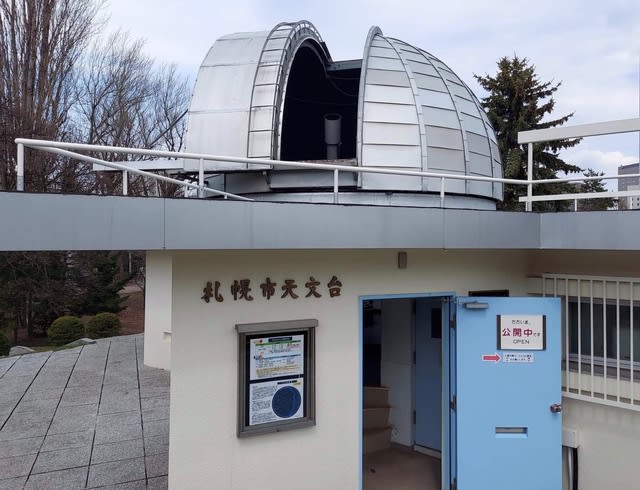

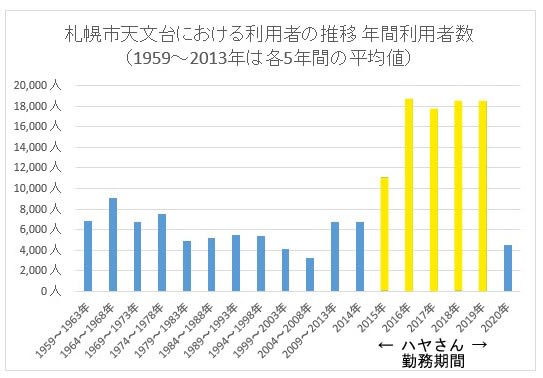
 51020122
51020122