
各季節の始まりの日(立春・立夏・立秋・立冬)の前日を指していましたが
江戸時代以降に成ると、特に立春(毎年2月4日頃)の前日を指す事が多く成ったと云われ
今迄爺やはこの「節分」の日は毎年決まっていて、2月3日だと思っていましたが
「節分」の日は固定されていなくて、「立春」の日が何時に成るのかに依って
「節分」の日が決まり、「立春」は1年間を太陽の動きに合わせて24等分した
「二十四節気」の内の一つで、国立国会図書館に依れば「二十四節気」は
1年を春・夏・秋・冬の4つの季節に分け、更に其々を6つに分けたもので
「秋分」や「冬至」等が含まれていて、日付の変動は地球の公転周期が
約365.2422日と、1年間の365日から約6時間ずつ遅くなる一方
地球が太陽を1周するのに365.242189日を要する為、1年365日のカレンダーとは
6時間のズレが生じて、これを4年に1度のうるう年でリセットしているものの
それでも端数分のズレが残ってしまので、「立春」は年によって3日や5日になり
それに伴って「節分」の日付も変わり、毎年の「二十四節気」に付いては
国立天文台が天文観測に基づいて定めていて、国立天文台が発表した
2025年の「暦象年表」に依れば、今年の「立春」は今年の節分は例年よりも1日早い
2月3日で、2021年に続いて「節分」の日はその前日なので2月2日と成り
今年は本日が「立春」なので「節分」は昨日と成り、一年の季節は「春夏秋冬」と書く様に
一年の始まりは「春」に成っていて、この「春」の始まりが「立春」なので
「立春」の前日が、「節分」として広く世間で認知される様に成り
その「春」が始まる前日、即ち新しい一年が始まる前日に「これから始まる
新しい一年が、不幸や災いの無い一年に成ります様に」との願いを込めて
神社仏閣や各家庭等では、「節分」の日には「鬼は外、福は内」と言いながら
豆撒きをして歳の数の豆を食べる習わしが有って、最近では「節分」の日に
その年の恵方に向かって、太巻きを鬼の金棒に見立てて「邪気を祓う」と云う意味の有る
切らずに長いまま太巻きを食べる事で、「縁を切らない」や「福を巻く」と云う意味も含めて
「祓鬼来福」を祈念しながら太巻き(恵方巻)寿司を無言で、まるかぶりで食べる
風習が定着する様に成り、2日の朝刊の間へ各スーパー等が恵方巻のチラシを差し込み
爺やんちでも、昨日の夕食時に家族揃って今年の恵方・西南西のやや西の方角を向いて
無言でまるかぶりして恵方巻を食べながら、新型コロナウィルス感染症の早期終息と
「祓鬼来福」を祈念した後に、「節分豆」を自分の歳の数だけ食べて「来福」をお願いしました












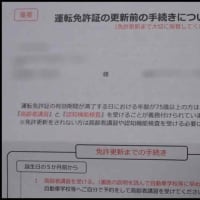



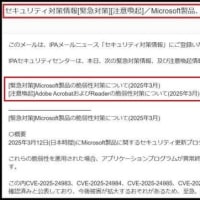

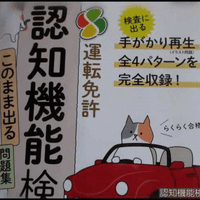

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます