
畑の隅、道端等の至る所で、見かける事が多い雑草で
余りにもその姿をよく見かけるので、遠くから眺めて
またツユクサかと、簡単に見過ごしてしまいがちだが
よく見ると、なかなか綺麗な青色した涼しげな花である
背丈は15~50cm程で、茎は直立する事はなく地面を這い
初夏の頃から1.5~2cm程の青い花を付け
花弁は3枚からなり、上部の2枚は青色で大きくて良く目立ち
下部の1枚は白色で、上部の2枚に比べて余りにも小さいので目立たない
「ツユクサ」の花は、早朝の5時頃から開花して
ほぼ午前中には閉じてしまうと云われ
余りにも短命なので、「露の草」と云う名前が付けられたのか
それとも朝露に濡れて咲く事から、「ツユクサ」なのだろうか
名前の由来が、どちらなのか良く解らないが
また別名を、「ボウシバナ」とも云われていて
おそらく、花を包む半円形の二つ折れになった編笠の様な苞の形から
この別名が、付けられのではないだろうかと云われている

現存する日本最古の歌集として知られている万葉集に、こんな歌が残されている
万葉集・作者未詳
「また後で会おう」と言われるのですか
(私にはこうしてあなたと一緒に過ごせる今がすべてなのに・・・)』と云われ
この万葉集では9首の歌が詠まれていて、昔から歌人には馴染みの花だったと思われる
ツユクサ(露草)はその昔、染め物の染料として盛んに使われていたが
その後、中国から藍染めの技術が伝わった頃から
染料としてではなく、友禅の下絵を描く絵の具として使われる様になったと云われ
もともとツユクサの花から採れる染料は、水に溶けやすいという性質があり
染め物の染料としては不向きだったが、しかし下絵を描く絵の具としてであれば
水に溶け易いという性質が、むしろ好都合だったのだろうと云われ
実際には、ツユクサの花は、染料を採取するには余りにも小さくて
絵具として使用するには多くの量が必要で、この量を確保出来ない事から
今は「ツユクサ」と同じ仲間で、大型の「オオボウシバナ」が使われていると云う












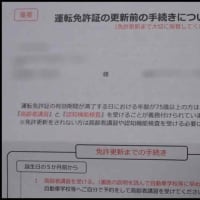



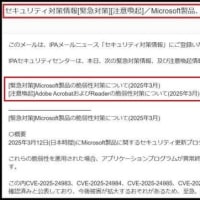

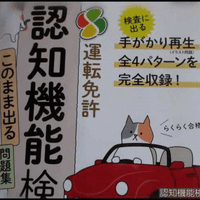








※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます